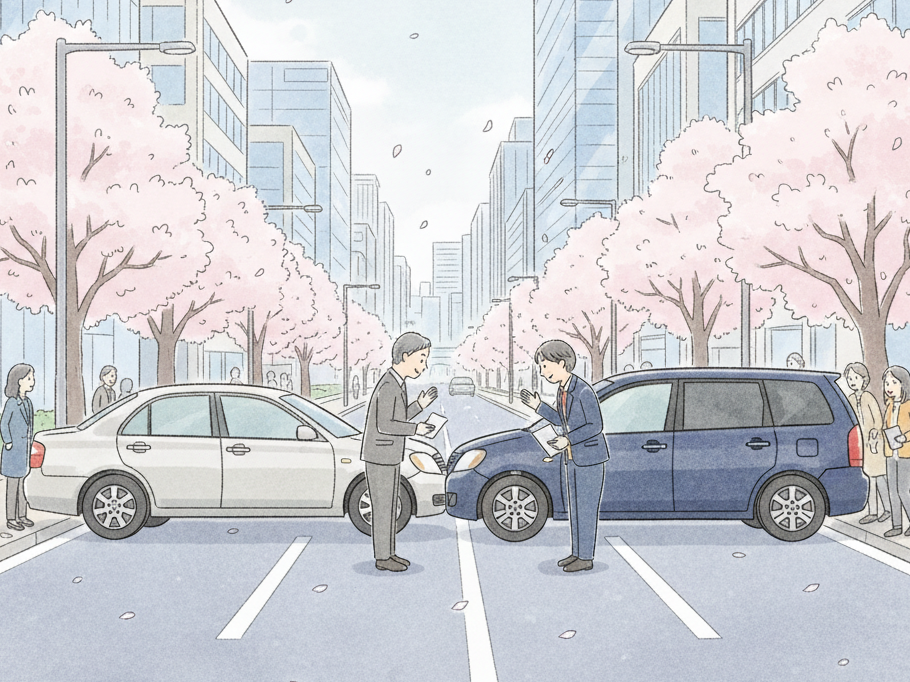企業活動において、従業員が自動車事故などを起こしてしまうことは、残念ながら「あり得ること」です。従業員が交通事故を起こしてしまった場合、会社(使用者)や車の所有者には、「使用者責任」と「運行供用者責任」という2種類の責任が問われる可能性があります。それぞれについて詳しく解説します。
使用者責任とは?(民法715条)
これは、従業員など「被用者」が業務中に事故などを起こして損害を与えた場合に、その「使用者(=会社)」が損害を賠償しなければならないというルールです。
要件
使用者責任が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.被用者が不法行為を行ったこと
従業員が、故意または過失によって他人の権利を侵害し、損害を与えたこと。具体的には、交通事故における運転上の過失(前方不注意、速度超過など)がこれにあたります。
2.使用者と被用者の間に指揮監督関係があること
雇用契約などに基づき、使用者が被用者に対して事業に関する指揮命令を行う関係にあること。通常、従業員であるだけでこの関係は認められます。
3.事業の執行についてなされたこと
最も重要な要件です。従業員が交通事故を起こした行為が、客観的に見て使用者の事業活動と関連性があると認められる必要があります。まったく個人的な運転による交通事故に使用者責任は発生しません。
具体例
肯定されるケース:営業中の移動、荷物の配達中、得意先への訪問途中、通勤途中(事業主が通勤手段や経路を指示・管理している場合や、事業遂行に密接に関連する通勤である場合)。
否定されるケース:私的な目的での使用、会社の業務とは全く関係のない個人的な行為(例えば、勤務時間外に会社の車を無断で私用で利用し、事故を起こした場合など)。ただし、外形的に業務執行と関連があると見られる場合は、使用者責任が肯定されることもあります(外形理論)。例えば、会社のロゴが入った社用車を私的に利用していて事故を起こした場合などです。
責任の性質
・無過失責任ではないが、過失の立証は不要:使用者自身に過失がなくても責任を負うため、「無過失責任」と誤解されがちですが、厳密には「使用者自身に過失がなくても責任を負う特殊な責任」と解釈されます。従業員の不法行為が成立すれば、使用者の過失を立証する必要はありません。
・免責事由:使用者は、「被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」は免責されるとされていますが、判例上、この免責が認められることは極めて稀です。事実上、免責は困難と考えられています。
・求償権:使用者が被害者に損害賠償をした場合、その使用者は、不法行為を行った従業員に対して支払った賠償額の全部または一部を請求する権利(求償権)を持ちます。しかし、従業員の過失の程度や会社の利益なども考慮され、全額の求償が認められることは稀です。
運行供用者責任とは?(自賠法3条)
次に重要なのが「運行供用者責任」です。こちらは交通事故による被害者救済を目的とした「自動車損害賠償保障法(自賠法)」に基づく特殊な責任です。
「運行供用者」とは、自動車の運行によって利益を受け、かつその運行を支配・管理している立場にある者のこと。要するに、自社名義の車を業務で使っていれば、その所有者である会社が原則として責任を負うという制度です。
要件
運行供用者責任が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
自己のために自動車を運行の用に供すること
自動車の運行を支配し、運行によって利益を得ている者。具体的には、以下の者が該当します。
・車の所有者:原則として運行供用者となります。
・使用者(会社):従業員に業務で車を運転させている場合、その車が会社の所有物であるか否かにかかわらず、会社も運行供用者となります。
・運転者:実際に車を運転している者も運行供用者となります。
・その他:車を借りて利用している者なども該当し得ます。
「運行」とは、自動車を一般の交通の用に供することを指し、エンジンをかける、停車中のドアを開けるといった行為も含まれることがあります。
他人の生命または身体を害したこと
運行によって、他人に人身損害を与えたことが対象になります。物損(車の損害、電柱の損害など)のみの場合は、運行供用者責任は適用されません(民法の一般原則で処理されます)。
責任の性質
・無過失責任に近い厳格責任:運行供用者は、以下のいずれかの事由を証明しない限り、損害賠償責任を負います。
1.自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2.被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
3.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。しかし、これらの全てを証明することは非常に困難であり、実質的には無過失責任に近い厳格な責任とされています。
・賠償範囲:人身損害に限定されます。
・共同不法行為責任:複数の運行供用者がいる場合(例:車の所有者である会社と、運転者である従業員)、それぞれが共同して責任を負います(連帯責任)。被害者は、そのうちの一方または双方に対して損害賠償を請求できます。
使用者責任と運行供用者責任の違いと関係性
違い
| 項目 | 使用者責任(民法715条) | 運行供用者責任(自賠法3条) |
| 根拠法 | 民法 | 自動車損害賠償保障法 |
| 対象 | 全ての不法行為(物損・人身損害問わず) | 人身損害のみ |
| 責任者 | 従業員を使用する者(会社) | 自己のために自動車を運行に供する者(所有者、使用者、運転者など) |
| 要件 | 従業員の不法行為、指揮監督関係、事業の執行との関連性 | 自動車の運行、人身損害の発生 |
| 責任の性質 | 実質的に免責が困難な責任(過失は不要) | 無過失責任に近い厳格責任 |
| 求償権 | 従業員に対する求償権あり(ただし制限されることが多い) | 他の共同不法行為者に対する求償権あり |
関係性
従業員が会社の車で業務中に交通事故を起こし、他人に人身損害を与えた場合、会社は「使用者責任」と「運行供用者責任」の両方を問われる可能性があります。
被害者は、どちらの責任に基づいて賠償請求をするかを選択できますが、通常は被害者保護の観点からより責任が重い運行供用者責任(自賠法)が適用されることが多いです。
ただし、物損のみの事故であれば、自賠法は適用されないため、民法の使用者責任や一般の不法行為責任が問われることになります。
経営者として押さえるべき対応策
会社にとって、従業員の事故は突然の大きなリスクになり得ます。しかし、「知らなかった」では済まされません。
法的責任を理解し、事前の備えをしっかり整えることで、会社を守ることができます。
会社としては、従業員が交通事故を起こしてしまったら、これらの責任を負う可能性があることを認識し、適切な自動車保険への加入や、従業員への安全運転指導を徹底することが重要です。