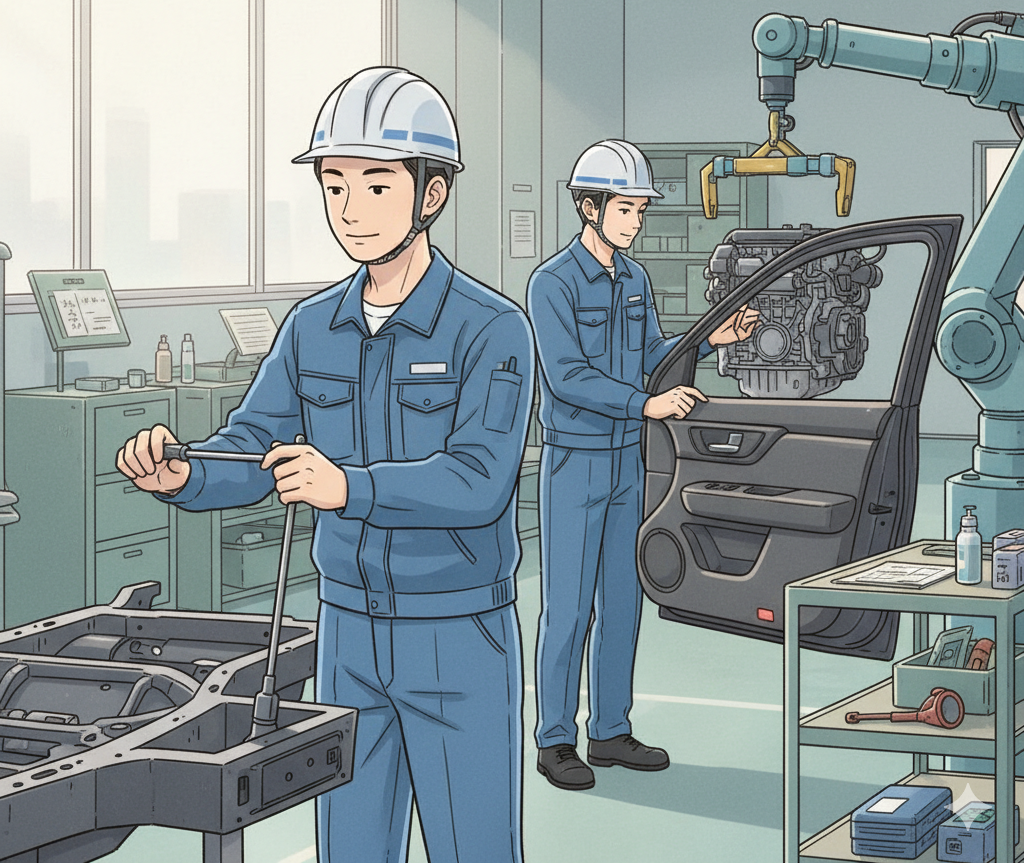救急用具
労働安全衛生規則衛生基準第九章に「救急用具」についての定めがあります。
この基準は、工場、店舗、展示場などの屋内作業場に適用されます。
(救急用具)
第633条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
救急用具は、休憩室や現場事務所に置くことが多いと思いますが、設置場所に「救急用具」などの記載がある市販のプレートを掲示するのが一般的です。
常備している救急用具の種類と使用法を記載した書類を救急箱近くに備置しましょう。雇入れ時の安全教育などに救急用具の使用方法を組み入れましょう。
不足や期限切れが無いように、常備している救急用具の種類と数量を記載したリストを用意し、担当者を決めて定期的に点検して補充しましょう。
次の634条は2021年12月の改正で削除されました。事業場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けることになりますが、参考までに旧規定を残しておきます
(救急用具の内容)=削除されています
第634条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
市販の救急箱に入っている量では、重大な事故が発生した時には対応できません。作業場の業務内容によりますが、ガーゼや包帯などは業務用を箱買いし、未開封の毛布やシーツも複数用意しておくなど、多すぎると思うくらいの備えをしておきましょう。
厚生労働省のパンフレットでは、マスクやビニール手袋、手指洗浄薬など、応急手当の際の感染予防に必要な品目も用意することを推奨しています。
救急箱に風邪薬などの医薬品を備えている会社もありますが、医薬品は副作用が伴うものであるため、会社が常備して自由に服用させていると、万一のときに会社の責任が生じかねません。もし医薬品を常備する場合は、使用者と服用量を把握する仕組みをつくり、薬品の数量と使用期限の管理を行いましょう。
関連記事: