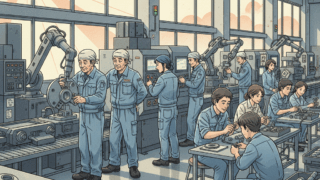 安全衛生管理
安全衛生管理 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付けについて解説
労働安全衛生法の改正により、特定の状況下で作業場所管理事業者に新たな義務が課されることになります。これは、複数の事業者が一つの場所で作業する際の労働災害防止を目的とした重要な改正です。主な内容と施行時期は以下の通りです。義務の内容:作業場所...
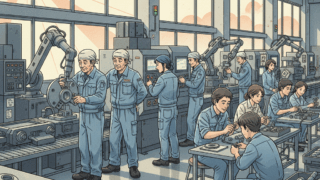 安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理  安全衛生管理
安全衛生管理