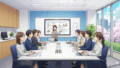新人:課長、お時間よろしいですか?
配属されたばかりで、男女雇用機会均等法について少し勉強してるんですけど、いまいちピンと来なくて……実務でどう気をつければいいか教えていただけますか?
男女雇用機会均等法とは
採用時に性別で差をつけてはいけない(第5条)
新人:まず、採用のところから。求人票に「女性歓迎」とか書いてるの、だいぶ前に見たことあるんですけど…あれってOKなんですか?
課長:今はあまり見かけないね。基本的にはNGだよ。第5条で、募集・採用時の性差別は禁止されてるからね。中立的な表現にしなきゃいけない。
新人:なるほど、能力で判断しろってことですね。
配置・昇進・研修も性別で扱いを変えてはダメ(第6条)
新人:じゃあ、入社後の配置とか昇進でも、性別を理由に変えちゃダメですか?
課長:そのとおり。第6条では、配置・昇進・降格・教育訓練などにおける性差別が禁止されてる。
「女性は出産があるから昇進は控える」とか、「男性だけ管理職研修に参加させる」とかは違法になるよ。
新人:ちゃんと評価基準を男女問わずに統一することが必要なんですね。
妊娠・出産・育児で不利益にしてはいけない(第9条)
新人:マタハラとかも問題になってますけど、あれもこの法律の中ですよね?
課長:そう。第9条では、妊娠・出産・産休・育休などを理由に不利益に取り扱うのは禁止されてる。
たとえば「妊娠したから契約更新しない」とか「育休に入るから別の部署に異動させる」とか、全部NG。
新人:実際にそういう相談ってあるんですか?
課長:あるよ。対応を間違えると、会社全体の信頼にも関わるから、人事としては特に注意が必要だ。
セクハラ対策は会社の義務(第11条)
新人:セクハラも均等法の対象なんですね?
課長:うん、第11条で会社に防止措置義務があるとされている。
具体的には、就業規則に禁止規定を入れる、相談窓口をつくる、実際にトラブルがあったらすぐ調査して対応することなどがある。
新人:なるほど。相談しやすい雰囲気をつくるのも大事ですね。
間接差別にも気をつけて(第7条)
新人:「間接差別」っていう言葉、あまり聞いたことがないんですが、どういうことですか?
課長:第7条で禁止されているのは、一見性別に関係ないように見えて、結果的に特定の性に不利になる制度だ。
たとえば「全国転勤可能であること」を昇進の条件にした結果、女性だけが除外されてしまう場合などがある。
新人:表向きは中立でも、結果として差が出るような制度は見直しが必要ってことですね。
女性の活躍を後押しする取り組みはOK(第8条)
新人:差別を心配して女性だけを優遇すると「逆差別」になるんじゃないかと心配になるんですが…
課長:そこは安心して。第8条で「ポジティブ・アクション」っていう考え方が認められていて、現状の格差を埋めるための取り組みはOKなんだ。
たとえば「女性管理職育成プログラム」なんかもその一例だよ。
まとめ
新人:なるほど…なんとなくわかってきました!要するに「性別にとらわれずに、公平な扱いをする」ってことですね。
課長:そのとおり。それに加えて、「制度だけじゃなく職場の雰囲気」も大切なんだ。
人事としては、ルールの整備も必要だし、社員が安心して相談できる環境づくりも担ってる。
この法律は、単なる義務じゃなく、いい職場をつくるための土台なんだよ。
課長:今日は、男女雇用機会均等法の主要な部分だけを説明したから、実務ではこれだけでは不十分だ。これを機会によく勉強してほしいね。厚生労働省ホームページの「均等法Q&A」は入門として適していると思うよ。
新人:はい、ありがとうございます!