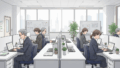団体交渉(だんたいこうしょう、団交)とは、労働組合が、使用者(会社)またはその団体と、労働条件その他の待遇や、労使関係の運営に関する事項について、対等の立場で話し合い、労働協約の締結などを目指す交渉のことをいいます。
これは憲法および労働組合法によって労働者に保障された権利であり、会社側は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできず、また、誠実に対応する義務があります。
団体交渉に臨む際の心構え
会社側は、団体交渉に臨むにあたり、以下の心構えで、事前準備を徹底することが重要です。
- 誠実交渉義務の履行:
- 会社は、労働組合の要求に対し、真摯に対応し、具体的な根拠をもって回答や主張をすることが義務付けられています。感情的にならず、冷静に合理的な説明を繰り返すことが求められます。
- 正当な理由なく交渉を拒否したり、交渉に不誠実な態度をとったりすることは、「不当労働行為」として禁止されています。
- 決定権限を持つ者の出席:
- 交渉の場で、「社長に聞かないと決められない」といった回答を繰り返すことは、不誠実な態度と見なされる可能性があります。
- 会社の決定権限を持つ人、またはその権限を委任された人が出席する必要があります。
- 交渉の長期化を念頭に置く:
- 団体交渉は一回で終わるとは限らず、粘り強く交渉を続ける姿勢が必要です。安易な約束はその後の交渉を不利にする可能性があるため、慎重な対応が求められます。
団体交渉の事前準備
団体交渉の成功は、事前の準備にかかっていると言っても過言ではありません。
- 要求内容の正確な把握と分析:
- 労働組合から送付された「団体交渉申入書」や「要求書」の内容を詳細に確認し、要求事項が義務的団交事項(賃金、労働時間、配転、懲戒など)か、任意的団交事項(経営戦略など)かを吟味します。
- 特に、義務的団交事項については、対応方針と回答案を具体的に準備します。
- 事実関係の調査と資料収集:
- 要求事項に関わる事実関係(例:対象従業員の勤務時間、給与の支払い状況、過去の対応事例など)を迅速かつ正確に調査し、必要な証拠資料を収集・分析します。
- 交渉チームの編成と役割分担:
- 出席者は、決定権限を持つ人(または代理人)を含め、人数を限定し、発言者を一本化することが望ましいです。複数名が出席する場合は、発言者、書記(記録係)などの役割を明確に定めておきます。
- 法律的な助言を得るため、弁護士などの専門家の意見を聞き、必要に応じて同席を依頼することも検討します。
- 交渉ルールの取り決め(予備折衝):
- 交渉に先立ち、開催日時、場所(中立的な場所が望ましい)、出席者数、交渉時間、議事録や録音の有無などの基本的なルールについて、労働組合と事前に調整します。
- 交渉戦略と想定問答の作成:
- 会社の解決方針を明確にし、譲歩できる点とできない点を決定します。
- 労働組合からの質問や主張を想定し、それに対する具体的な回答や反論を文書化(想定問答集の作成)しておきます。
- 記録の準備:
- 交渉内容は、後々のトラブルを防ぐため、議事録を作成するか、双方の合意の上で録音することが非常に重要です。