 労働保険
労働保険 労災の手続きは病院の受付で申し出るだけ!?
従業員が医療機関の受付で「仕事上のケガ(労災)である」と申告し、所定の手続きを進めた場合、会社側が一方的にその労災手続きを取り消すことはできません。従業員が指定病院で労災受診した場合労災保険の給付を決定し、実施するのは労働基準監督署長であり...
 労働保険
労働保険  労働保険
労働保険  労働保険
労働保険 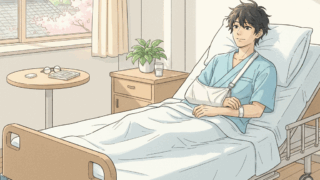 労働災害
労働災害 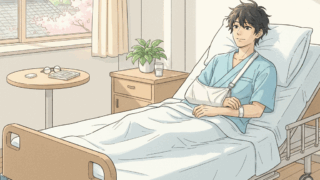 労働保険
労働保険  安全衛生管理
安全衛生管理