 会社の運営
会社の運営 オフィス清掃を外注するときの注意点
オフィスの清掃を外部業者に委託する際には、契約内容と日々の運用において、トラブルを未然に防ぐための注意点がいくつかあります。契約上の注意点契約書は、清掃業者との認識のズレを防ぎ、後々のトラブルを回避するための最も重要な書類です。以下の点を明...
 会社の運営
会社の運営  会社の運営
会社の運営 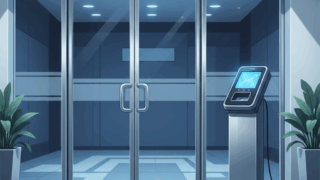 会社の運営
会社の運営 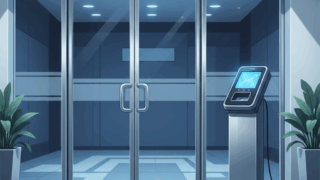 会社の運営
会社の運営