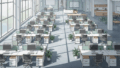成果主義賃金制度は、社員の年齢や勤続年数ではなく、仕事の成果や業績に基づいて給与を決定する賃金制度です。主に1990年代以降、年功序列賃金制度の対極にある考え方として日本企業に導入が進みました。
この制度では、個人やチームが設定した目標の達成度合い、売り上げへの貢献度、またはプロジェクトの成功といった客観的な指標によって評価がなされ、その結果が直接給与やボーナスに反映されます。
メリットとデメリット
成果主義賃金制度のメリットとデメリットについて解説します。
メリット
- 従業員のモチベーション向上: 成果を出せば直接収入が増えるため、社員は目標達成に向けて意欲的に働きます。
- 生産性の向上: 成果が明確に評価されることで、社員は効率的に業務を進めるようになり、組織全体の生産性アップにつながります。
- 優秀な人材の確保: 実力や成果に見合った報酬が得られるため、能力の高い人材にとって魅力的な職場となります。
- 人件費の適正化: 業績に連動して人件費を配分できるため、無駄なコストを抑えられます。
デメリット
- 評価基準の設定が難しい: 成果を定量的に測りにくい職種(事務、研究開発など)では、公正な評価基準を作るのが困難です。
- チームワークの低下: 個人の成果が重視されるあまり、社員間の協力が薄れ、個人主義的な行動が増える可能性があります。
- 短期的な成果への偏重: 長期的な視点での人材育成や、目先の利益に直結しない業務が軽視されるリスクがあります。
- 離職率の増加: 成果が出せない社員の給与が下がることで、不満やストレスを感じやすくなり、離職につながる可能性があります。
導入企業の例
成果主義賃金制度は、特に個人の成果が明確な営業職や専門職で多く導入されてきました。代表的な導入企業には、富士通、花王、本田技研工業、サイバーエージェントなどがあります。これらの企業では、評価の透明性を確保し、目標管理制度をうまく組み合わせることで、成果主義のデメリットを補いながら運用しています。
給与決定の方法
成果主義賃金制度における給与決定は、一般的に「基本給」と「成果給」を組み合わせた仕組みで行われることが多く、単純に売上が2倍になったからといって給料が2倍になるわけではありません。
多くの場合、給与は以下の構成要素から決定されます。
- 基本給(固定給): 年齢、勤続年数、職務内容、能力などに応じて定められる、毎月安定して支払われる部分です。この基本給が大きく減額されることは通常ありません。
- 成果給(変動給): 個人の成果や企業の業績によって変動する部分です。賞与(ボーナス)、インセンティブ、報奨金などがこれにあたります。
営業職の給与決定例
例えば、営業職の場合、給与は以下のように構成されます。
1. 基本給 + 歩合(インセンティブ)制
これは、基本給に加えて、個人の売上実績に応じて歩合給が上乗せされる仕組みです。
- 売上が目標を大きく上回った場合: 例えば「売上目標を10%超過するごとに、超過分の10%をインセンティブとして支給」といったルールが設定されます。この場合、売上が倍になれば、インセンティブは大幅に増えますが、基本給は変わらないため、給料全体が倍になることは稀です。
- 売上が目標を下回った場合: 達成できなかった月でも基本給は保証されるため、給料が大幅に減額されることは通常ありません。ただし、賞与の評価に影響したり、成績が長期間低迷すると役職や基本給の見直しにつながる可能性はあります。
2. 年俸制
年単位で給与総額を決定する制度で、成果主義の代表的な形態の一つです。
- 給与決定: 1年間の成果を評価し、次年度の年俸を決定します。このため、成果が上がれば大幅な昇給が見込める一方、成果が出なければ年俸が下がることがあります。しかし、企業は多くの場合、急激な生活水準の低下を防ぐため、給与の減額には上限を設けています。
結論として、成果主義賃金制度では、基本給がセーフティネットとして機能し、個人の頑張りが賞与やインセンティブといった形で給与に上乗せされる仕組みが主流です。これにより、売上を大幅に伸ばした場合は給与アップにつながる一方、売上が落ちても生活が困難になるほど給料が下がるケースは少ないと言えます。
成果を数値化できない職種には不向き
成果を定量的に測りにくい職種には、成果主義ではない別の賃金制度を併用したり、成果主義の評価方法を工夫したりする企業が多いです。一つの会社で複数の賃金制度や評価方法が混在することは、もはや珍しくありません。
評価しにくい職種への対応
成果を数値化しにくい事務職や研究開発職などでは、以下のような評価方法が取られます。
1. 行動評価(プロセス評価)
目標達成に至るまでのプロセスや、業務に取り組む姿勢を評価する方法です。たとえば、「チームへの貢献度」「業務改善の提案回数」「自律性・積極性」「スキルアップの努力」といった、数値化しにくい項目を評価します。
2. 定性評価と定量評価の組み合わせ
成果主義は「売上」や「コスト削減額」といった定量評価(数値で測れる評価)が中心ですが、それだけでは公平な評価が難しい場合があります。そこで、先述の行動評価のような定性評価(数値で測れない評価)と組み合わせて運用します。
多くの企業では、従業員と上司が協力して目標を立て、その目標の達成度を定期的に話し合う目標管理制度(MBO)などを活用し、評価の客観性や納得感を高めています。
職種別賃金制度
特に大企業では、職種ごとに異なる賃金体系を設ける職種別賃金制度を導入しているケースもあります。
- 営業職: 売上目標の達成度を重視する成果主義的な評価と賃金体系
- 事務・管理部門: 職務遂行能力や専門性、勤続年数などを加味した賃金体系
- 研究開発職: 長期的な成果を評価するため、短期的な成果主義よりも、能力や役割を重視した賃金体系
このように、職種の特性に合わせて複数の賃金制度を使い分けることで、社員全員が公平な評価を受けられるように工夫しています。
業績が低迷している企業には不向き
成果主義賃金制度は、成長している企業や業績が好調な企業により適した制度と言えます。これは、成果給の原資を確保しやすく、従業員の頑張りに報いることができるからです。
成果主義と企業の成長
成長・好調な企業の場合
- 成果給の原資が豊富: 業績が伸びているため、売上増分の利益を従業員へのインセンティブやボーナスとして還元できます。
- 従業員のモチベーション維持: 成果を上げた分だけ給与が増えるため、従業員のモチベーションは高く保たれます。これにより、さらなる業績向上という好循環が生まれます。
業績が停滞・縮小している企業の場合
- 原資の確保が困難: 業績が伸び悩む、または縮小している状況では、成果給を支払うための原資が乏しくなります。
- モチベーションの低下: 成果を出しても給与に反映されにくいため、従業員の不満がたまり、モチベーションが低下するリスクがあります。
- 人件費の硬直化: 成果主義を導入しても、基本給をなかなか下げられないため、固定費である人件費の削減が難しくなります。結果として、企業の財務状況をさらに圧迫する可能性があります。
停滞企業における成果主義の課題と対策
業績が停滞している企業が成果主義を導入する場合、以下のような課題に直面し、対策を講じる必要があります。
- 課題: 成果給の原資がないため、インセンティブが機能しない。
- 対策: 成果を上げた社員に対して、金銭報酬だけでなく、昇進・昇格、裁量権の拡大、表彰といった非金銭的な報酬を組み合わせることで、モチベーションを維持しようと試みます。
- 課題: 基本給の減額が難しい一方で、業績悪化による人件費削減が急務。
- 対策: ジョブ型雇用など、職務内容や役割に応じて賃金を決定する制度への移行を検討する企業もあります。これにより、社員の能力や成果をより厳密に評価し、人件費の適正化を図ります。
このように、成果主義は企業の成長段階や財務状況によって向き不向きがあります。ただ、どのような状況であれ、制度を導入する際には、評価の透明性や公平性を確保することが最も重要です。