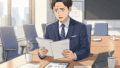全額払いの原則
労働基準法に次のような定めがあります。
労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
つまり、原則として賃金を支給するときは、何であっても差し引いて支給してはいけない、というのが原則です。これを賃金の「全額払いの原則」といいます。
全額払いの例外
賃金の全額払いには例外があります。先ほどの労働基準法24条には次のような定めもあります。
労働基準法第24条 (続き)法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
つまり、原則として差し引いて支給してはいけないとしつつ、法律にもとづく場合と労使協定にもとづく場合は例外的に控除してもよいと定めています。
法律にもとづく場合
所得税・地方住民税の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料が該当します。
労使協定にもとづく場合
労使協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定です。労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と協定します。
労使協定で控除できる項目
労使協定による控除は、従業員が負担することが明らかなもので、給与から控除することが従業員にとって便利なものが認められています。
具体的には、物品等の購買代金、社宅・寮その他福利厚生施設の費用、財形貯蓄金、労働組合費、貸付金の返済等があります。
給料の振込手数料は労使協定をしても控除することができません。
協定書の例
その他の注意点
労使協定書の扱い
賃金控除の労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。
労使協定の内容は従業員へ周知しなければなりません。協定締結後に入社した従業員に対しては協定内容を入社説明事項に加えるなどして周知を忘れないようにしましょう。
この労使協定を自動更新にしていると、労使協定の内容と実際に控除している項目が異なってきても気が付かないことがあります。時々チェックしましょう。
就業規則の変更
労使協定を結んだ場合でも、就業規則や給与規程にその旨を規定する必要があります。
労使協定の効力は、労働基準法第24条1項の賃金全額払い原則違反を免れさせるものにすぎないので、労働契約上適法に控除するためには、別途労働協約または就業規則に根拠規定を設けなければならないという判例があるからです。
したがって、賃金控除の労使協定は届け出は不要でも就業規則の変更を労働基準監督署に届け出する必要があります。
個別同意書
就業規則等への規定がなければ、労使協定があっても労働者の個別の同意が必要になります。
ただし、労働者との個別の同意については注意が必要です。使用者と労働者の力関係からして、後日争いになったときは、控除の同意が従業員の完全に自由な意思に基づくとはいえないと判断される可能性が大きいからです。
また、同意によって控除している場合は、自由意思での同意ですから、途中で合意を撤回されるとその後は控除できなくなります。
控除の限度額
民法及び民事執行法の規定により、賃金の4分の3(その額が33万円を超える場合は33万円)に相当する部分については、使用者側からは控除することはできません。つまり、控除額の上限は4分の1までです。貸付金の返済控除などについて注意が必要です。