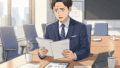引き継ぎ義務について
法的な義務について
労働基準法などの法律に「退職者は必ず引き継ぎをしなければならない」といった規定はありません。
ただし、労働契約法3条4項にある「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」という規定や、民法の信義誠実の原則から、退職時にも一定の範囲で誠実に対応する義務があると解されます。
実務上は、多くの会社が就業規則等に「業務の引き継ぎを行うこと」と定めています。
就業規則による拘束力
就業規則に「退職に際しては業務の引き継ぎを誠実に行うこと」と定められていれば、労働者はこれに従う義務があります。
ただし、退職は労働者の権利ですので、引き継ぎの不備を理由に退職を妨げることはできません。
引き継ぎを一切行わず、会社に大きな損害や混乱を与えた場合には「職務怠慢」等として懲戒処分を検討する余地はあります。
ただし、懲戒処分は退職日までにできることであり、退職後には処分できません。
また、そもそも、会社が社員の業務を把握していれば引き継ぎも簡単に終わるはずなので、一方的に従業員の責任にすることはできません。「引き継ぎが不十分だった」という程度で重い処分を科すのは裁判例上も難しいでしょう。
したがって「できる範囲で」ということが現実的な落としどころになります。
退職後に判明した引き継ぎもれ
退職後に業務上の引継ぎ義務は基本的にありません。退職日までの間は誠実に引き継ぐという一定の義務がありますが、退職後に呼び出されて追加対応をする義務まではありません。
引き継ぎ書について
引き継ぎ書の作成は、法的な義務ではありませんが、一般的に行われています。
引き継ぎ書の基本的な構成
引き継ぎ書に決まった書式はありませんが、一般的には以下の項目を含めると良いでしょう。
- 基本情報:書類のタイトル、作成日、作成者、引き継ぎ先(後任者)の名前など
- 業務一覧:担当している業務をリストアップします。
- 引き継ぎ内容:それぞれの業務について、具体的な進め方や注意点などを記載します。
- 資料・ファイル一覧:業務で使用している資料やファイルの保管場所、アクセス方法などを記載します。
- その他:引き継ぎに関する連絡先や、口頭での補足事項など
各項目の具体的な内容
1. 業務一覧
まずは、担当しているすべての業務を洗い出しましょう。年間、月間、週間のルーティン業務や、イレギュラーな業務、進行中のプロジェクトなども忘れずにリストアップします。
2. 詳細な引き継ぎ内容
このセクションが最も重要です。「誰が見ても分かるように」を意識して、具体的に記載しましょう。
- 業務の目的:なぜこの業務を行うのか、その意義や目的を伝えます。
- 業務フロー:業務の開始から完了までの流れを順を追って説明します。
- 使用ツール・システム:業務で使用するシステム名やソフト名、ログイン情報などを記載します。
- キーパーソン:業務に関わる社内外の連絡先や担当者名を記載します。
- 注意点・コツ:業務を進める上での注意点や、円滑に進めるためのコツなどを共有します。
3. 資料・ファイル一覧
業務で使用する資料やファイルの保管場所、アクセス方法を明確に示します。ファイル名やフォルダ名も具体的に記載すると後任者が探しやすいです。
引き継ぎ書を書かなかったらどうなるか?
法的な義務ではないため、引き継ぎ書を書かなかったからといって罰則はありません。
しかし、引き継ぎが不十分だったために会社に大きな損害が出た場合、会社側が「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」違反を主張し、損害賠償を求めるケースは考えられます。
ただし、実際に損害賠償が認められるケースは極めて稀で、相当な悪意や過失が認められない限り、会社が訴訟に踏み切ることはほとんどありません。
退職日までに間に合わない場合
引き継ぎは通常業務と並行して行うため、時間的に厳しいと感じる方も多いです。もし退職日までに引き継ぎが完了しそうにない場合は、早めに上司に相談しましょう。
相談することで、引き継ぎ内容の優先順位を決めたり、周囲の協力を得られたりするなど、解決策が見つかるかもしれません。