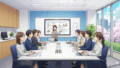会社内での政治活動について
就業規則に、会社で政治活動をしてはいけないという規定をつくるのは、問題があるでしょうか。会社というのは、会社の敷地内という意味でなく、仕事をしている場所すべてという意味ですが。
政治活動禁止の妥当性
原則として、就業規則で職場内の政治活動を禁止することは問題はありません。 ただし、その規定の内容や適用においては、合理性が求められ、行き過ぎた制限は無効となる可能性があるので注意してください。
企業秩序維持の観点
- 裁判例では、企業は企業秩序維持の見地から、就業規則によって職場内における政治活動を禁止する定めを設けることは合理的であると判断された例があります(最高裁昭和52年12月13日 目黒電報電話局事件など)。
- 会社には、施設管理権や経営秩序を保持する権利があり、業務遂行に支障をきたしたり、従業員間に不必要な対立を生じさせたりする可能性のある活動を制限することができます。
制限の範囲の注意点
- 問にあった「仕事をしている場所すべて」での政治活動禁止は、勤務時間中の活動や職務専念義務との関係で、特に合理性が認められやすいです。
- ただし、この制限は無制限ではありません。労働者の思想・信条の自由や政治活動の自由(憲法で保障)を過度に侵害するものであってはなりません。
規定・運用の際の留意点
特に問題となりやすいのは、勤務時間外(休憩時間や休日など)の活動への制限です。
| 項目 | 留意点と判断基準 |
| 制限が有効となる場合 | 会社の企業秩序を乱すおそれがある場合や、業務に具体的な支障が出る場合など、合理的な理由がある場合です。 |
| 制限が無効となる可能性 | 休憩時間など、業務に関連しない場所で、穏当な内容かつ受領を強制しない態様で行われる活動まで一律に禁止するなど、企業秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合。単に思想や信条を理由とする差別的取扱いと判断される場合。 |
| 懲戒処分 | 就業規則に違反した場合でも、懲戒処分を行う際は、違反行為の態様(強制性、業務への影響の程度、場所、時間など)を考慮し、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるものでなければなりません。 |
禁止できない活動
休憩時間など、業務に関連しない場所で、穏当な内容かつ受領を強制しない態様で行われる活動は、禁止できないという理解で良いでしょうか。線引が難しいとは思いますが。
休憩時間中や業務に関連しない場所における、穏当な内容かつ受領を強制しない態様の政治活動は、原則として会社は就業規則で一律に禁止することはできません。
これは、労働者には憲法で保障された思想・信条の自由や政治活動の自由があり、休憩時間等は労働から解放された自由な時間とみなされるためです。
制限が許される場合の「線引き」
しかし、この活動が以下のような状況に至ると、「企業秩序維持」の観点から会社の制限が有効になる可能性があります。ここが「線引き」の難しい部分です。
| 制限が無効となる可能性が高い活動 (原則自由) | 制限が有効となる可能性が高い活動 (禁止可能) |
| 休憩場所で同僚にビラを手渡す(受け取りを強制しない) | 執務場所や通路を占拠して大声で演説や集会を行う |
| 穏当で業務に無関係な政治主張を小声で話す | 他の従業員に威圧的な態度で署名や寄付を強要する |
| 業務時間外に、職務に影響がない範囲で個人的な主張をする | 活動により職場の人間関係が著しく悪化し、業務に具体的支障が出た場合 |
判例の示す基準
裁判所は、企業が休憩時間中の活動を禁止できるのは、「企業秩序を乱す具体的なおそれ」がある場合に限られる、という姿勢をとっています。
- 単に抽象的な危険があるというだけでは禁止できません。
- 活動の態様(強制的か否か、穏当か否か)、場所(休憩所か執務室か)、時間(休憩中か執務中か)、影響の程度(業務への支障の有無)などを総合的に判断されます。
したがって、「休憩時間など、業務に関連しない場所で、穏当な内容かつ受領を強制しない態様で行われる活動」は、企業秩序を乱す具体的な危険性が極めて低いため、会社が就業規則で禁止しても、その規定は無効と判断される可能性が高い、という結論になります。
宗教活動の禁止
宗教活動についても、政治活動に対するのと同じような対応で良いでしょうか。
はい、基本的な考え方と線引きの基準は、政治活動の場合と非常に似ています。
宗教活動に関する対応の原則
企業秩序維持の観点から、業務に支障をきたしたり、他の従業員に強制したりするような宗教活動は、就業規則で制限することができます。
ただし、労働者の信教の自由(憲法で保障)を尊重する必要があるため、企業が職場で宗教活動を制限できるのは、企業秩序維持のために必要な限度にとどまります。
| 活動のタイプ | 企業の制限の妥当性 |
| 制限が妥当な活動 | 業務時間中の熱心な祈祷、業務を妨げる布教活動、他の従業員への強要や執拗な勧誘、会社の施設・備品を無断で利用した集会など。 |
| 制限が難しい活動 | 休憩時間や業務に無関係な場所での個人的な祈り、穏当で受領を強制しない文書の配布、個人的な信仰に関する会話など。 |
特に注意すべき点
「強要・勧誘」の禁止
政治活動と同様、就業規則に定めるべきは、「特定の宗教を理由とした差別的取り扱い」の禁止と、「他の従業員に対する強要や執拗な勧誘」の禁止です。
- 単に個人的な信仰を持っていることや、穏当な会話をすることまでを禁止することは、信教の自由の侵害となる可能性が高いです。
就業場所・就業時間中の制限
「仕事をしている場所すべて」での宗教活動の禁止は、就業時間中については、職務専念義務との関係で一般的に合理性が認められます。
しかし、休憩時間や更衣室など業務から離れた場所で、他の従業員に迷惑をかけない範囲での個人的な行為(例:目立たない形での短時間の祈り)まで一律に禁止することは、合理性を欠くと判断される可能性があります。
中立性の維持
企業は、特定の宗教を優遇したり、差別したりすることなく、公平な立場で対応する必要があります。制限を設ける場合は、特定の宗教に狙いを定めたものではなく、あくまで職場秩序維持を目的としたものであることを明確にする必要があります。
したがって、就業規則の規定例としては、政治活動の規定例と同様に、「業務の遂行を妨げ、または企業秩序を乱すおそれのある行為」として宗教的な勧誘、布教、集会などを制限するのが妥当な方法となります。
物品販売等の禁止
同僚等に、物品やサービスの購入を勧誘する行為はどうでしょうか。
物品やサービスの購入勧誘行為(営業行為や営利行為)についても、基本的な考え方は政治活動や宗教活動と同様です。つまり、休憩時間等に穏当なやり方で行われる場合は、会社が一律に禁止することは難しいですが、制限の合理性が認められやすい側面もあります。
規制の線引き
政治活動や宗教活動が思想・信条の自由に関わるのに対し、物品やサービスの購入勧誘(いわゆる内部営業やマルチレベルマーケティングへの勧誘など)は、主に営利活動に関わります。
しかし、これも労働者の私的な活動の一環であるため、原則として自由ですが、企業秩序維持のために制限が加えられます。
規制できない可能性が高い活動
- 休憩時間中に、個人的な趣味や私的な売買に関する話を穏当な会話の範囲で行うこと。
- 強要性がなく、受領や購入を強制しない形で、個人的な物品を一度だけ紹介すること。
- 業務に全く影響がない私的なメッセージツール等で勧誘を行うこと(ただし、相手が同僚である以上、職場関係への影響は考慮されます)。
規制できる可能性が高い活動
「業務遂行の妨げ」や「企業秩序の乱れ」に繋がる場合は、会社はこれを就業規則で制限し、違反に対して懲戒処分を行う合理性があります。
- 執拗かつ頻繁な勧誘:繰り返しの勧誘により、勧誘された同僚が精神的な負担を感じ、業務に集中できなくなる場合。
- 勧誘の強要:地位や人間関係を利用し、断りにくい状況を作ったり、購入を強く迫ったりする場合。
- 金銭トラブルの発生:勧誘を通じて借金や金銭的な被害が発生し、職場の信頼関係が崩壊したり、業務に支障をきたしたりする場合。
- 業務時間中の活動:休憩時間外に勧誘を行うなど、職務専念義務に違反する場合。
制限の合理性
営利目的の活動は、政治活動や宗教活動と異なり、職場の人間関係を金銭トラブルに発展させるリスクが特に高いため、会社が「企業秩序を乱す具体的なおそれ」があると判断しやすい活動です。
したがって、就業規則に、「業務遂行を妨げ、または職場の人間関係及び企業秩序を乱すおそれのある、金銭または物品の売買や勧誘行為」を禁止する規定を設けることは、高い合理性が認められます。
就業規則規定例
「業務遂行の妨げ」や「企業秩序を乱すおそれ」を判断基準とし、私的な活動の自由を不当に侵害しないよう配慮した規定例です。
(職場秩序維持および禁止行為)
従業員は、会社の就業時間中および就業の場所(業務遂行中のすべての場所を含む)において、職務専念義務に反する行為、または業務の遂行を妨げ、企業秩序を乱すおそれのある以下の行為をしてはならない。
- 特定の政党・政治団体、宗教団体、物品やサービスを支持、反対、または販売・購入させることを目的として、他の従業員に対し、威圧的、強制的、あるいは執拗に次の行為を行うこと。
- 演説、集会、署名、文書やビラの配布。
- 金銭の寄付や物品・サービスの購入を勧誘、または強要すること。
- 個人的な主義・主張、信仰、営利活動に関し、他の従業員に精神的な負担を与えたり、職場の人間関係を著しく悪化させたり、金銭的なトラブルを引き起こしたりする行為。
- 会社または第三者の施設・備品・情報を、上記の活動に無断で利用する行為。
規定のポイント
この規定は、あらゆる私的活動を包括的に規制しつつ、制限が違法とならないよう、「業務・秩序を乱すおそれ」と「活動の強制性・執拗性」に焦点を当てたものです。
なお、この規定例は一般的なものであり、会社の業種や実情に合わせて調整が必要です。より具体的な内容や法的リスクの確認については、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。