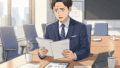ケーススタディ
課長の一人が、自分の部下について、使えない、程度が低い、異動させられないか、解雇できないかと、社内の他の部署で何度も発言しているとのことです。人事からも見ると、「使えない」など言われている部下よりも、その管理職(課長)の方に大きな問題があると思うのですが、上司(部長)の信頼が厚いので少し問題が複雑です。本人(課長)と上司である部長に、どのように対応すればよいでしょうか。
ご質問のケースは、組織の健全性に関わる重要な問題です。このケースでは上司(部長)の信頼が厚い課長であるため、対応が複雑になることは理解できますが、人事として、臆することなく慎重かつ毅然と対応してください。
人事として、この課長と部長にどのように対応していくべきか、段階を追ってご提案します。
初動(事実確認と状況把握)
感情的にならず、客観的な事実を確認することが重要です。
- 課長の発言の記録と影響の確認:
- 課長が「使えない」「程度が低い」などと言った具体的な発言内容、発言された状況(いつ、どこで、誰に対して、他の誰が聞いていたか)を記録します。
- これらの発言が、実際にパワハラに該当する可能性を検討します。(職場の優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えるまたは就業環境を悪化させる行為に当たるか。)
- 部下たちが実際に異動や解雇の対象になっているかではなく、その発言によって部下のモチベーションやメンタルヘルス、チームの雰囲気にどのような悪影響が出ているかを把握します。
- 部長への申し出内容の確認:
- 課長がどのような根拠で「異動・解雇」を求めているのか、その具体的な内容(例:〇〇という業務ができない、△△というミスが多いなど)を確認します。
- 人事としての方針の明確化:
- 部下を一方的に蔑むような言動はハラスメントにあたり、組織として許容できないという方針を明確にします。この方針が、後の対応の軸となります。
課長(本人)への対応
課長の行動の改善とハラスメント防止が主眼となります。
- 個別面談の実施(指導・注意):
- 人事担当者、または場合によっては部長と連携して面談を行います。
- 「部下に対する不適切な言動(〇〇という発言や、異動・解雇要求など)が、ハラスメントに該当する可能性があり、組織として許されない」ことを明確に伝えます。感情論ではなく、会社の方針とリスク(コンプライアンス、部下のメンタルヘルス不調、離職リスクなど)に基づいて伝えます。
- 課長が部下を評価する際に用いるべき客観的な基準(業務目標、行動評価など)を示し、指導方法を改善するよう求めます。
- 部下の能力が不足していると考える場合でも、管理職として取るべき行動は「異動・解雇の要求」ではなく、「能力開発」「適切な業務分担」「具体的な指導」であることを指導します。
- 発言内容によっては、懲戒規定に基づいた処分も検討対象となり得ることを示唆し、事態の重大性を認識させます。
- 管理職研修の受講:
- ハラスメント防止、部下育成、メンタルヘルスに関する研修を受講させる必要を検討します。特に個別指導の必要があれば、外部コーチングなども検討します。
部長(上司)への対応
部長の認識の是正と連携が重要です。課長への信頼があるからこそ、慎重に進める必要があります。
- リスクと会社の方針の説明:
- 部長に対して、課長の発言がハラスメントに該当し、放置すれば企業の信用、訴訟リスク、他の社員のモチベーション低下といった重大なリスクにつながることを具体的に説明します。
- 「課長への信頼は理解するが、今回は個人の能力評価を超えた組織運営上の重大な問題である」と伝えます。
- 協力を求める:
- 課長への指導・監督は部長の責務でもあるため、人事と部長が連携して課長への指導に当たるよう協力を求めます。
- 課長の発言を「部下への指導熱心さの裏返し」と捉えている場合があるため、指導とハラスメントの明確な線引きを共有します。
- 課長の業務監督の強化:
- 今後、課長が部下に対して行う評価や指導内容について、部長がより詳細にチェックする体制を構築するよう依頼します。
部下への配慮(沈静化と再発防止)
問題となっている部下たちへの配慮も不可欠です。
- 秘密厳守の配慮のもとでのヒアリング:
- 課長の発言内容が事実であれば、部下たちが既に不当な評価やハラスメントに苦しんでいる可能性があります。
- 部下たちに安心感を与えつつ、課長との関係について個別でヒアリングを実施し、心身の状況を確認します。
- 再発防止策の周知:
- ハラスメントの相談窓口の存在を再周知し、必要に応じて異動を含めた配置転換やメンタルヘルスサポートなどの措置を検討します。
- 今回の事案への具体的な対応は秘密にしながらも、「会社として不適切な言動には適切に対応する」というメッセージを社内に発信し、組織の信頼回復に努めます。
この問題のポイントは、人事として毅然と「ハラスメントは許されない」という一貫した対応を取ることです。