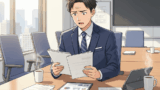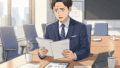マタハラとは
マタハラ(マタニティハラスメント)とは、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントのことです。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
男女雇用機会均等法第11条の3 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 第11条第2項の規定(Ⅱ-1参照)は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
育児介護休業法第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
マタハラの例
マタハラには、①制度等の利用への嫌がらせ型、②状態に対する嫌がらせ型の2つがあります。
制度等の利用への嫌がらせ型
妊娠・出産・育児に関する制度等の利用をしようとする労働者に対して、解雇等の不利益な取扱いの示唆、制度利用の妨害、嫌がらせなどを行うことで就業環境を害することを言います。
・上司に妊娠を報告したところ「妊娠したら辞めてもらうことになっている」などと言う
・産前の検診のため休業を申請した労働者に「会社が終わってからでも間に合うだろう」などと言う
・育児休業を申し出た男性労働者に「会社にいれば仕事があるが、お前が家にいて何をするのだ」などと言う
・育児のための短時間勤務している女性労働者に、「こっちは忙しい思いをしているのに甘えているのではないか」などと言う
状態に対する嫌がらせ型
労働者が妊娠・出産する、したという状態に対して、解雇等の不利益な取扱いの示唆、制度利用の妨害、嫌がらせなどを行うことで就業環境を害することを言います。
・産前産後休業や育児休業をとりたいと申し出た労働者に「休んでも良いが、代わりの人を採用するから戻る場所はないと思ってほしい」などと言う
・妊娠した労働者に「なぜ忙しい時期に妊娠するんだ」などと言う
・「こう休みが多いと責任ある仕事は任せられない」などと言う
・「妊娠しているからといって甘え過ぎではないか」などと言う
など
業務上の必要
不利益取扱いは禁止されていますが、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動はハラスメントには該当しません。
会社の義務
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
会社はマタハラ防止についての方針等を明確化するとともに、これに関する情報を、従業員に周知・啓発しなければなりません。
具体的には、マタハラの内容、妊娠・出産等、育児休業等に関する否定的な言動が職場におけるマタハラの原因や背景となり得ること、マタハラがあってはならない旨の方針、労働者は、妊娠・出産・育児に関する制度等の利用ができること、マタハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を周知します。
周知・啓発は、ポスターの掲示、パンフレットの配布、メールの送付、研修などにより行います。
相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
会社は社内に相談窓口を設置してマタハラに関する従業員からの相談や苦情に対応しなければなりません。窓口がハラスメントごとに分かれていると相談がしにくくなるため、厚生労働省の指針では、一元的な相談窓口を設置することが望ましいとしています。
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
マタハラが発生してしまったときは、事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害者に対する配慮の措置をとるとともに、行為者に対する是正措置を行い、再発防止に向けた措置も合わせて講ずる必要があります。
職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
マタハラは、業務量が多い職場や人員が不足している職場に生じやすいといわれています。産休や育休をとる人が出たときに、他の社員への負担が大幅に増加することがあるからです。
会社は、業務の負担の偏りを改善する、人員を補充するなどの対応を行い、マタハラの原因や背景となる要因を解消するための措置をとる必要があります。