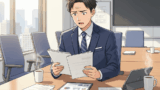セクハラとは
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、他の者を不快にさせる職場または職場外における性的な言動のことです。
「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものをいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。
セクハラは男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行われるものも対象になります。
場所・時間の限定はありません。
不快であるか否かの判断は、基本的には受け手が不快に感じるか否かによって判断されます。
セクハラの例
セクハラになり得る言動として、例えば、次のようなものがあります。
・ スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
・ 卑猥わいな冗談を話すこと。
・ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」などと言うこと。
・ 性的な質問をすること。
・ 性的な噂うわさを立てること
・ 性的なからかいの対象とすること。
・ 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと言うこと。
・ 「男の子、女の子」、「お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などの呼び方をすること。
・ 性的指向や性自認をからかったり、本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること。
・ ヌードポスター等を職場に貼ること。
・ 雑誌等の卑猥わいな記事等を見せたり、読んだりすること。
・ 身体を必要以上に眺めること。
・ 食事やデートにしつこく誘うこと。
・ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
・ 身体に不必要に接触すること。
・ 性的な関係を強要すること。
・ 更衣室等をのぞき見すること。
・ 女性であるという理由でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
・ カラオケで一緒に歌うことを強要すること。
・ 酒席で、上司のそばに座席を指定したり、お酌やダンス等を強要すること。
会社の義務
従業員からセクハラやパワハラ、職場いじめなどのいわゆる「ハラスメント」の被害にあっているとの申告があったときは、会社はそのハラスメント行為をやめさせる適切な対処をしなければなりません。
男女雇用機会均等法第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。