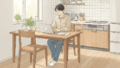社内公募制度とは
社内公募制度とは、人材を必要とする部署が社内に募集をかけ、それに対して従業員が自らの意思で応募し、異動を目指せる仕組みのことです。
通常の人事異動が会社や人事主導で決められるのに対し、社内公募制度は、従業員が自身のキャリア形成のために主体的に行動できる点が大きな特徴です。「社内転職」「ジョブ・ポスティング」と呼ばれることもあります。
制度の主な特徴
- 従業員の自主性: 従業員が「この部署で働きたい」「この新しいプロジェクトに挑戦したい」といった自分の希望に基づいて応募します。
- 人材の募集: 人材を補充したい部署や、新規プロジェクトの立ち上げなどで必要なポジションが社内に公開されます。
- 選考: 応募した従業員は、応募先の部署などで選考(面接など)を受け、合否が決定します。
- キャリアの選択肢: 会社を辞めることなく、職種や業務内容を大きく変えるキャリアチェンジの機会を得られます。
類似制度との違い
社内公募制度と混同されやすい他の人事制度との違いは以下の通りです。
| 制度名 | 仕組み | 従業員の異動希望 |
| 社内公募制度 | 部署が募集し、社員が応募する(求人型) | 応募先への異動が前提 |
| 自己申告制度 | 社員が、スキルや異動希望などを人事部に申告する | 異動が約束されるわけではなく、参考情報となる |
| 社内FA制度 | 社員が、一定条件のもと自分を売り込む(求職型) | 交渉が成立すれば異動 |
導入のメリット
| 対象 | メリット |
| 企業 | * モチベーションの高い人材を確保できる。 |
| * 採用コストや研修コストを抑えられる。 | |
| * 優秀な人材の社外流出防止につながる。 | |
| 従業員 | * 自らの意思でキャリアを形成できる。 |
| * 新たな職種や業務に挑戦できる。 | |
| * 転職せずに仕事環境を変えられる。 |
従業員のキャリア自律を促し、企業にとっても適切な人材配置を進める有効な手段として注目されています。
中小企業でも社内公募制度を導入することができます。限られた人材を最大限に活用し、企業の成長に結びつけるための有効な戦略となる可能性があります。
導入の注意点
社内公募制度は多くのメリットがある一方で、ご指摘の通り、導入・運用にあたってはいくつかの重要な問題点が生じる可能性があります。
ここでは、考えられる主な問題点と、それに対する具体的な対策を解説します。
社内公募制度の主な問題点と対策
異動元の上長・部署からの反感
優秀な人材が公募で引き抜かれることで、異動元の部署の士気が低下したり、上長が人事部に不満を持ったりする可能性があります。
上長に拒否権を与えないルールを徹底し、「人材育成は全社的な責任」という意識を浸透させます。上長を評価する際に、部下のキャリア自律支援や公募制度への協力を評価項目に加えることが有効です。
異動元の業務負担増加(人材不足)
異動元の部署は、穴埋めや業務引き継ぎで一時的に業務過多に陥る可能性があります。特に少数精鋭の中小企業では影響が大きくなります。
異動が決定した場合、後任の採用や配置、業務の見直し期間を設け、十分な引継ぎ期間を確保します。必要であれば、公募部署に対して異動元への一時的な人員サポートを義務付けることも検討します。
不採用者のモチベーション低下
応募したものの不採用となった社員が、「会社に必要とされていない」と感じ、モチベーションを失ったり、離職につながったりするリスクがあります。
応募者全員にフィードバック面談を実施し、不採用の理由と、そのポジションに必要なスキルを明確に伝えます。その上で、スキルアップのための研修機会や次の挑戦への支援を提供し、前向きなキャリア形成をサポートします。
人気部署への人材集中と不人気部署の固定化
人気のある部署や新規プロジェクトに優秀な人材が集中し、他の部署の人材が公募に応募できず、組織全体として最適化が難しくなることがあります。
応募が集まりにくい部署については、募集内容を具体的に魅力的に提示し、異動後の成長機会や待遇を明確に示します。また、キャリア面談を通じて、社員が知らなかった部署の魅力に気づけるように支援します。
応募の動機が不純なケース
「現在の仕事からの逃避」や「現職の上司との人間関係からの脱出」など、キャリアアップ以外の目的で応募する社員が出てくることがあります。
選考プロセスで動機を深く確認し、現在の部署で抱える問題が異動で解決できる性質のものなのかを見極めます。異動前にキャリアカウンセリングを行い、本人の真の目標と現状をすり合わせる機会を設けます。
制度定着のための総合的な対策
これらの個別対策に加え、制度を定着させるためには、以下の取り組みが不可欠です。
- 全社的なキャリア支援: 社員が自身のキャリアについて自律的に考えるためのキャリア研修や、人事部門によるキャリア相談窓口を整備します。公募に応募するかどうかにかかわらず、社員の成長をサポートする文化を作ります。
- 公平性と透明性の確保: 募集要項や選考基準を明確にし、選考過程の公平性を保つことが、制度への信頼につながります。選考結果は、不採用の場合も含め、速やかに本人に伝えます。
- 経営層の明確なメッセージ: 「この制度は、社員の成長と企業の成長を両立させるために重要である」というメッセージを、経営層が継続的に発信し続けることで、現場の管理職の協力も得やすくなります。
規程例
中堅企業を想定した、社内公募制度の社内規程サンプルを、主要な項目に絞って作成しました。
社内公募制度規程(サンプル)
第1条(目的)
本規程は、従業員に対し、自身の能力、適性及び意欲に基づき自発的に職務を選択する機会を提供し、従業員のキャリア形成の自律を促すとともに、組織の活性化と適材適所の人員配置を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本規程において「社内公募制度」とは、欠員または新規事業に伴う人材を必要とする部署が社内に募集を行い、これに対し従業員が応募し、選考を経て異動を決定する制度をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、正社員を対象とする。ただし、試用期間中の者、休職中の者、または別途定める特別契約社員は対象外とする。
第4条(募集部門の責務)
公募を行う部門(以下「募集部門」という)は、以下の事項を明確にし、人事部の承認を得て社内に公示しなければならない。
- 募集ポジション名、職務内容、必要な知識・スキル・経験
- 異動後の処遇(等級、職位、給与など)
- 応募資格、選考方法、スケジュール
第5条(応募資格)
公募に応募できる従業員は、原則として以下の資格要件を全て満たす者とする。
- 現所属部署における在籍期間が1年以上であること。
- 過去1年以内に懲戒処分を受けていないこと。
- 過去1年以内に本制度に応募し、不合格となっていないこと。(※安易な応募防止のため)
第6条(応募手続き)
- 応募を希望する従業員は、所定の期日までに、応募書類(職務経歴書、応募理由書など)を人事部に提出しなければならない。
- 応募に際し、現所属部署の上長への事前報告は不要とする。
第7条(選考プロセスと情報保護)
- 選考は、書類選考および募集部門による面接(1~2回)により行う。
- 選考結果は、人事部と募集部門が協議のうえ決定し、応募者に通知する。
- 応募者の情報(氏名、応募の事実)は、選考期間中、人事部及び募集部門の選考関係者以外に一切開示されないものとする。
第8条(異動の内定通知)
選考の結果、合格となった従業員に対し、人事部を通じて異動を内定する。
第9条(現所属部署への通知と調整)
- 異動内定後、人事部から現所属部署の上長へ、当該従業員の異動が決定した旨を通知する。
- 現所属部署の上長は、従業員の異動を理由なく拒否することはできない。
- 人事部は、異動に伴う業務の引継ぎ期間を考慮し、異動日を現所属部署と協議のうえ決定する。原則として、内定通知から1ヶ月~2ヶ月以内に異動するものとする。
第10条(不合格者への対応)
- 選考の結果、不合格となった従業員に対しては、人事部がその旨を通知する。
- 希望者には、不合格の理由と今後のキャリア形成に関するアドバイスを行うため、人事部によるフィードバック面談を実施する。
第11条(異動後の評価)
異動後の異動初年度の業績評価については、在籍期間を考慮し、異動元と異動先の部署における貢献度を按分して評価を行うものとする。
第12条(規定の改廃)
本規程の改廃は人事部が起案し取締役会の承認を得て決する。
【ポイント】
- 応募の秘密保持 (第6条、第7条):社員が安心して応募できるように、応募時の現上長への報告は不要とし、応募情報を厳重に非公開とする点を強調しています。
- 上長の拒否権の排除 (第9条):優秀な人材の異動を上長が妨げないよう、「拒否できない」ことを明記しています。
- 不合格者へのフォロー (第10条):不合格者のモチベーション低下を防ぐため、フィードバック面談を設ける仕組みを取り入れています。