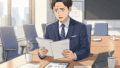カーナビを運転中に「じっと見る」行為は、道路交通法によって禁止されている「注視」にあたり、違反となります。この「注視」の加減について解説します。
運転中の「注視」とは?
道路交通法第71条第5号の5では、自動車等が停止しているときを除き、画像表示用装置(カーナビやスマホなど)に表示された画像を注視しないことが義務付けられています。
違反となる行為
「注視」とは、文字通り「注意して見ること」や「じっと見つめること」を指します。
- 具体的な時間: 法律には「何秒以上見たら違反」という厳密な規定はありません。
- ただし、一般的には、2秒以上継続して画面を見続けると「注視」と判断され、取り締まりの対象になる可能性が高いとされています。
- 時速60kmで走行している場合、2秒間目を離すと車は約33メートル進みます。この間に前方の状況が変化しても対応できず、非常に危険だからです。
- 「確認程度」は違反ではない: 地図をちらっと見て、すぐに前方に視線を戻すといった確認程度の短い視線移動は、通常、違反とはなりません。
- 操作も注意: カーナビの操作自体は直ちに違反とはなりませんが、操作に夢中になって画面を長時間注視してしまうと、結果として「注視」違反となります。
判断のポイント
最も重要なのは、「運転の安全を妨げるほど、画面に意識が集中しているかどうか」という点です。現場の警察官が、運転状況や視線の動きなどから危険だと判断すれば、検挙の対象となります。
安全な利用方法
カーナビを利用する際は、運転中の「注視」を避けるために、以下の点を徹底しましょう。
- 事前に設定を完了する: 目的地設定やルート確認など、複雑な操作は出発前に済ませておきましょう。
- 停車中に操作する: 走行中に操作や詳細な地図確認が必要になった場合は、安全な場所に停車してから行うか、信号待ちなどで車が完全に停止している間に行いましょう。
- 音声案内を活用する: 地図画面を見る時間を減らすために、音声案内を積極的に活用しましょう。
- 1秒以内に済ませる: 走行中に画面を見る際は、チラッと見てすぐに視線を前方に戻すことを意識し、1秒以内に留めるようにしましょう。
安全な運転を最優先し、画面への意識集中を避けることが、違反防止と事故防止につながります。
ハンズフリー通話は?
運転中のハンズフリー通話は「違反ではないが、注意が必要」というのが基本的な考え方になります。
詳しく解説します。
道路交通法上の規定
道路交通法では、運転中の携帯電話等の使用について、以下のように定めています。
| 違反となる行為 | 法律の条文(要約) |
| 手で持って通話 | 携帯電話等の全部または一部を手で保持しなければ通話ができないものを使用すること。 |
| 画面の注視 | 携帯電話やカーナビなどの画面を注視すること(停止中を除く)。 |
この規定に基づくと、
- ハンズフリー通話は、携帯電話等を「手で保持」しないため、原則として道路交通法上の通話禁止の対象にはなりません。
- カーナビや車載システム、Bluetoothイヤホン/スピーカーなどを使って、手を使わずに通話することは可能です。
安全運転義務違反になることがある
ハンズフリー通話自体は違反でなくても、通話に集中するあまり、運転がおろそかになった場合は、「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。
| 違反の名称 | 該当するケース | 罰則等(普通車の場合) |
| 安全運転義務違反 | ハンズフリー通話に熱中し、 ・前方不注意になった。 ・ハンドル操作がおろそかになった。 ・他の車両や歩行者への注意が散漫になった。 | 反則金:9,000円 違反点数:2点 |
特に、議論が白熱したり、感情的になったりするような通話は、注意力が散漫になりやすく、安全運転義務違反として取り締まられるリスクが高まります。
都道府県ごとの条例にも注意が必要
一部の都道府県では、条例(道路交通規則など)によって、自動車の運転中にイヤホンやヘッドホンを使用して、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえない状態で運転することを禁止している場合があります。
- 例えば、「片耳イヤホンはOKだが、両耳イヤホンはNG」といった規定がある地域もあります。
- お住まいの地域や運転する地域の条例を一度確認することをおすすめします。