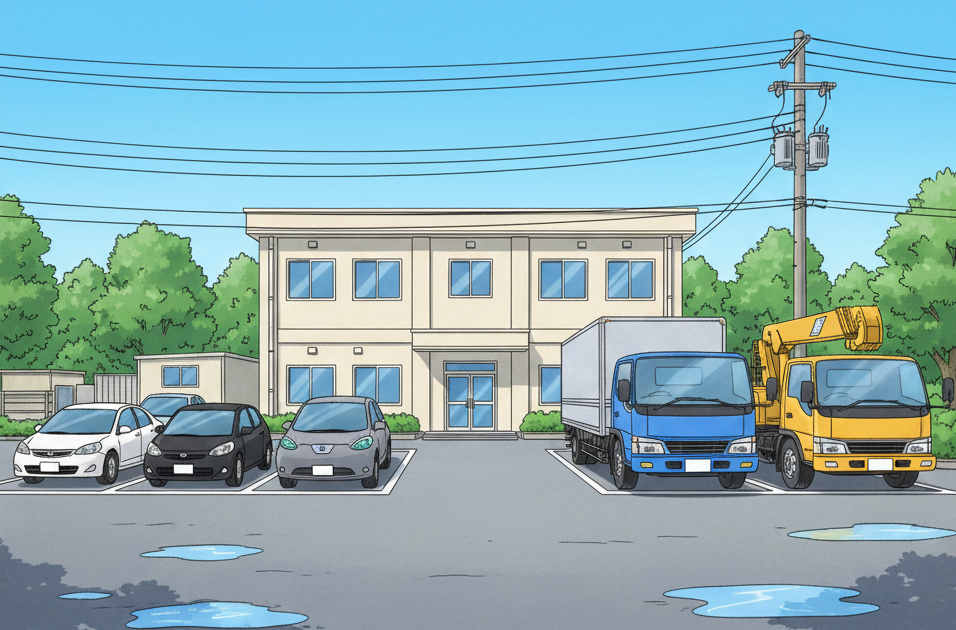ケーススタディ
小規模な運送会社の社長です。運転職の従業員が心臓の手術をして会社に復帰してきました。本人はまったく元通りなのですぐに運転職に復帰したいと希望しています。運転に差し支えないという診断書も持ってきました。私には医学的知識がありませんが、常識的に考えて、心臓の手術をしたものが全く不安がないというのが信じられません。倉庫係を打診しましたが、本人は、そういう仕事は退屈で却って体を悪くすると言って断りました。どうしても倉庫係をやれと言うなら、会社を辞めて他所の会社で運転手になるとも言いました。こういう場合、会社はどうすればよいでしょうか。
病気を克服した従業員の復帰は歓迎すべきことですが、同時に会社には、安全配慮義務いう責任があります。
このような心臓疾患からの復職の場合、特に運転職という安全性が非常に重要視される職種では、医学的な判断を客観的に得ることが最も重要になります。
会社として取るべき具体的な手順と、現在の状況への対応策を説明します。
復職判断と安全配慮のためのステップ
まず、主治医の診断書に加えて、会社の責任において客観的な意見を求めることが重要です。
産業医等による意見聴取の検討
従業員数50人未満の事業場であれば産業医の選任義務はありませんが、安全配慮義務を果たすために、外部の医師(産業医や地域産業保健センターの医師など)の意見を求めることを強くお勧めします。
- 主治医の診断書:
- 従業員の方が提出した「運転に差し支えない」という診断書は、日常生活や一般的な業務が可能であることを示している可能性があります。
- しかし、運送業の長時間・長距離運転や緊急時の対応など、業務の具体的内容を踏まえた意見であるかを確認する必要があります。
- 会社側からの依頼:
- 主治医に対して、具体的な運転業務の内容(例:運転時間、休憩、積荷の重労働の有無、緊急時の対応など)を伝え、「当該業務に復帰させることの是非」について、より詳細な意見書を改めて依頼することを検討してください。
- この際、「復職に際し、会社として配慮すべき事項(業務量や時間、配置転換の必要性など)があるか」という点も明確に尋ねましょう。
- 産業医や専門医の意見:
- 主治医の診断書だけで判断せず、会社の安全配慮義務の観点から、産業医などの職場復帰支援の専門家の意見を聴くのが最善です。地域の産業保健総合支援センターなどに相談窓口があることが多いです。
「試し出勤制度」の検討
従業員の方はすぐに運転職への復帰を強く希望されていますが、会社として、いきなり元の運転業務に戻すことに不安がある場合は、「慣らし運転」の期間を設けることを提案しましょう。
- リハビリ出勤(試し出勤):
- 最初は短時間の倉庫業務や軽作業から始め、段階的に体力や集中力の回復を確認していく期間を設ける。
- これは、従業員の方の体調を慣らすためだけでなく、会社が安全性を客観的に判断するための期間でもあります。
- 「倉庫係」として恒久的に配置転換するのではなく、「運転職復帰に向けたリハビリ期間」として位置づけることで、従業員の方の抵抗感を和らげられる可能性があります。
配置転換の必要性と法的な視点
従業員の方の「会社を辞めて他所で運転手になる」という発言は、本人の強い希望と不安の裏返しだと思います。しかし、会社には従業員の健康と安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。
- 医学的意見の尊重:
- 産業医や主治医の詳細な意見によって、現在の運転業務が健康上不適当であると判断された場合、会社は安全配慮義務に基づき、配置転換(職種の変更)を命じることができます。
- この場合、「安全のために必要である」という客観的な根拠(医師の意見書)が重要になります。
- 就業規則の確認:
- 会社の就業規則に配置転換に関する規定があるかを確認してください。通常、業務上の必要性や従業員の健康維持のために配置転換を命じることが可能とされている場合が多いです。
- ただし、職種を「運転職限定」として採用している場合は、配置転換には本人の同意が必要となる可能性があります。
従業員の方とのコミュニケーション
最も大切なのは、従業員の方の意向を尊重しつつ、会社の懸念を誠実に伝えることです。
- 懸念の共有:「あなたの体調を心配している」「復帰を歓迎しているが、万が一運転中に何かあった場合、あなた自身だけでなく、相手の運転手や通行人にも影響が出てしまう。これは会社の責任問題であり、あなたの人生に関わる問題でもある」と、会社があなたを守りたいという姿勢で伝えましょう。
- 根拠の説明:上記の医師の客観的な意見や、リハビリ期間の必要性など、医学的・安全上の根拠に基づいて説明すれば、本人の理解を得やすくなります。
- 運転職復帰への道筋を示す:「リハビリ期間を設け、主治医や産業医が『問題なし』と判断すれば、すぐに運転職に戻ってほしい」と、運転職復帰を完全に否定するものではないというメッセージを明確にしてください。
従業員の希望をかなえてやりたい気持ちがあると思いますが、心臓疾患からの復職で無理をさせて事故が起こった場合、会社としての責任は非常に重くなります。
まずは、医学的な根拠を補強すること、そして運転職復帰に向けた一時的な措置(リハビリ出勤など)として提案することで、従業員の方の納得を得られるよう努めてください。
この件について、より詳細な法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することもご検討ください。
病気差別との関係
病気を理由に、希望する職種に復帰させないことになった場合、病気に対する差別にはならないでしょうか。
会社が心臓手術後の従業員に対して復職や配置転換について慎重な判断をすることは、病気を理由とした不当な差別にはあたりません。これは、「職場の安全配慮義務」に基づく正当な措置だからです。
安全配慮義務の履行であると伝える
会社には、労働契約法に基づき、従業員が安全で健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。
運送業の運転職の場合、心臓疾患が原因で運転中に意識を失うなど、万が一の事態が発生すれば、従業員本人の生命に関わるだけでなく、同乗者、相手の運転手、そして一般の通行人にも甚大な被害を及ぼす可能性があります。
【従業員への伝え方】
- 「これはあなたの病気に対する差別ではない。あなたの体調を心配しているからこその安全性の確認だ。」
- 「私たちには、あなた自身と、あなたが運転するトラックの周りのすべての人々の安全を守る社会的・法的な責任がある。その責任を果たすために、医学的な確認が必要不可欠だ。」
客観的かつ公平な判断プロセスを提示する
感情論や「常識的な不安」だけで判断するのではなく、客観的な専門家の意見に基づいて判断することが、差別ではないことの最も強力な証拠になります。
「主治医の診断書」だけでなく、「産業医(または外部の専門医)の意見」を聴取するプロセスこそが、公平性を確保するための重要なステップです。
- 「診断書は尊重するが、運送業務という特殊な業務の安全性を、会社の責任として確認する必要がある」と伝えます。
- このプロセスは、会社が「安全に運転職に復帰してもらうための支援」の一環として行っていることを強調してください。
配置転換は「恒久的な差別」ではなく「一時的な配慮」であると説明する
従業員の方が拒否された「倉庫係」の打診についても、それが「運転職への差別的な降格」ではないことを明確に説明します。
- 倉庫係の打診は、運転職復帰に向けた「慣らし運転」や「リハビリ」期間として提案したと明確に伝え、短期間で体力を回復させ、運転職にスムーズに戻るための準備期間であると位置づけ直しましょう。
- 「いきなり過度な負荷がかかる運転業務に戻るよりも、まずは体調を万全に戻すための一時的な措置であり、あなたの早期の運転職復帰を支援するための配慮だ」と伝えます。
退職の申し出への対応
「会社を辞めて他所で運転手になる」という発言に対しては、「それはあなたの自由な選択だが、健康と安全に関する懸念はどの会社でも同様に重要視されるべき問題だ」と、冷静に伝えましょう。
- 会社の安全配慮義務の観点から、運転業務に支障があると客観的に判断される限りは、会社として運転職への復帰を命じることはできません。
- 人材を失うのは痛手ですが、安全配慮義務を怠って重大な事故が発生した場合の社会的・法的なリスクの方がはるかに大きいことを念頭に置いてください。
この問題は、常識的な「不安」を、医学的な「根拠」に置き換えることで解決に向かいます。感情的にならず、従業員の気持ちに寄り添いつつ、一貫して安全と健康の客観的な確認を求める姿勢を維持することが大事です。