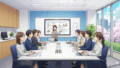社内研修の講師育成は、企業の持続的な成長と人材育成において非常に重要です。人事課に所属する専任講師を育てる場合と、各部門から出てもらう兼務講師を育てる場合では、アプローチや育成のポイントが異なります。それぞれについて詳しく解説します。
社内研修講師の育成の基本
まず、共通して講師に求められる能力と、育成の基本的な考え方について述べます。
講師に求められる能力
専門知識・スキル:担当する研修テーマに関する深い知識と実践的なスキル。
伝える力(コミュニケーション能力):
論理的思考力:情報を体系立てて整理し、わかりやすく説明する能力。
表現力:声のトーン、表情、ジェスチャーなどを効果的に使い、受講者を引き込む能力。
質問力・傾聴力:受講者の疑問を引き出し、理解度を確認し、適切にフィードバックする能力。
場をコントロールする力(ファシリテーション能力):
受講者の参加を促し、議論を活性化させる能力。
時間管理、トラブル対応など、スムーズな研修運営を行う能力。
受講者へのエンゲージメント力:
受講者の興味を引きつけ、学習意欲を高める能力。
受講者の成長を支援する熱意と姿勢。
育成の基本的な考え方
体系的な育成プログラム:OJT(On-the-Job Training)だけでなく、Off-JT(Off-the-Job Training)も組み合わせた体系的なプログラムが必要です。
段階的アプローチ:最初から完璧を求めず、小さな成功体験を積み重ねながら徐々にステップアップさせていきます。
フィードバックと実践の繰り返し:研修実施後の丁寧なフィードバックと、それを踏まえた実践の機会を確保することが不可欠です。
専任講師を養成する場合
人事課の講師は、企業全体の人材育成戦略に基づいた研修の企画・実施を担う、いわば「プロの講師」としての役割が期待されます。育成のポイントは次のとおりです。
講師としての基礎力向上(インプット)
ロジカルシンキング、プレゼンテーションスキル:自身の思考を整理し、的確に伝えるための基礎スキル研修。
ファシリテーションスキル:グループワークや議論を効果的に導くためのスキル研修。
教材作成スキル:魅力的なスライドや演習問題を作成するためのスキル研修(デザイン、構成、コピーライティングなど)。
インストラクショナルデザイン:学習効果を最大化するための研修設計の考え方(目標設定、コンテンツ構成、評価方法など)。
成人への教育に関する心理学:成人の学習特性を理解し、飽きさせずに学びを深めるための知識。
外部研修への参加:講師育成を専門とする外部機関の研修に積極的に参加させ、最新の知見や多様な手法を学ぶ機会を提供します。
実践と経験の積み重ね(アウトプット)
OJT(共同登壇):まずは経験豊富な講師のアシスタントとして参加し、運営の流れや講師の振る舞いを間近で学びます。その後、一部のセッションを担当させ、徐々に担当範囲を広げていきます。
模擬研修(ドライラン):本番前に、人事課内や少数の関係者を相手に研修を実践し、フィードバックを得ます。
本番登壇とフィードバック:実際に研修に登壇させ、終了後には受講者アンケートや上長・育成担当者からの具体的なフィードバックを丁寧に行います。特に「良かった点」と「改善点(具体的な行動レベルで)」を明確に伝えます。
研修動画の活用:自身の研修風景を動画で撮影し、客観的に自己分析する機会を提供します。
専門分野の深化
人事課講師は、会社の理念、人事制度、コンプライアンス、新入社員研修など、企業全体のベースとなる研修を担当することが多いため、これらの分野に関する専門知識を深く掘り下げることが必要です。
法改正や最新動向に関する学習機会も必要です。
マインドセットの醸成
「人材育成を通じて会社の成長に貢献する」という強い使命感と情熱を持たせることが重要です。
常に学び続ける姿勢、受講者の成長を喜ぶ気持ちを育みます。
兼務講師を養成する場合
社内の各部門から兼務の形でカリキュラムの一部を担当してもらう講師に、講師としての力をつけさせる場合について解説します。
各部門の兼務講師は、自身の業務知識や経験を活かし、より実践的で専門性の高い内容を伝える役割が期待されます。彼らは「普段の業務遂行者+講師」であるため、育成アプローチはより効率的かつ実務に即したものにする必要があります。育成のポイントは次のとおりです。
講師としての最低限の基礎スキル習得
ショートプレゼンテーション研修:短時間で効果的に情報を伝えるための基礎スキルに特化します。具体的な構成(結論から話す、具体例、要点まとめなど)を教えます。
質疑応答対応:受講者からの質問に的確に答えるための準備と心構え、知らない場合の対処法などを指導します。
スライド作成の基本:情報を詰め込みすぎず、視覚的に分かりやすいスライド作成のポイントを伝えます。
時間管理の重要性:持ち時間を厳守し、効率的に研修を進めるための意識付けと具体的なコツを伝えます。
業務知識と講師スキルの橋渡し
自身の業務経験を「研修コンテンツ」として再構築するサポート:
講師候補者に「この知識を誰に、何を、どう伝えたいか」を明確にするワークショップで学習してもらいます。
自身の成功事例や失敗談を、受講者が「自分ごと」として捉えられるように話す工夫を指導します。
専門用語を避け、平易な言葉で説明する練習してもらいます。
実務的なノウハウ共有会:経験豊富な兼務講師から、自身の登壇経験や工夫点を共有してもらう場を設けます。
実践機会と具体的なフィードバック
「お試し」登壇の機会:まずは短い時間(15分~30分程度)で、特定のテーマについて登壇する機会を設けます。
ロールプレイング:実際に研修を想定したロールプレイングを行い、講師役、受講者役に分かれて実践練習をします。
個別フィードバック:人事課の育成担当者が、個別に研修の様子を観察し、具体的な改善点を丁寧にフィードバックします。改善点だけでなく、良かった点も具体的に伝えることでモチベーションを維持します。
受講者アンケートの活用:受講者からの具体的なコメントや評価を講師本人にフィードバックし、次回の改善に繋げます。
OJT(共同登壇):最初はアシスタントや一部のパートを担当させ、徐々に慣れさせます。
動機付けと負荷管理
講師としての役割の重要性を伝える: 自身の知識や経験が、後進の育成や組織力向上に貢献することを強調し、やりがいを持たせます。
業務とのバランスを考慮: 兼務であるため、本業に支障が出ないよう、講師としての準備時間や登壇頻度を無理のない範囲で調整します。
適切な評価: 講師としての貢献を人事評価に反映させるなど、モチベーションを高める仕組みも検討します。
まとめ
人事課に所属する専門講師は、より高度な教育スキル(インストラクショナルデザイン、ファシリテーション、心理学など)を習得し、研修全体の設計・実施を担うプロフェッショナルとしての育成を目指します。
各部門の兼務講師は、自身の専門知識を「分かりやすく伝える」ことに特化させ、効率的かつ実践的なスキルアップを支援します。個別のフィードバックと実践の機会を重視し、本業とのバランスを考慮することが重要です。
どちらの場合も、講師自身の「教えたい」「貢献したい」という意欲を引き出し、継続的にサポートしていく体制が成功の鍵となります。