 賃金・賃金制度
賃金・賃金制度 年末調整手続きの電子化とは?わかりやすく解説
「年末調整手続きの電子化」は、従業員での年末調整の負担を減らし、手続きを簡単にするための取り組みです。年末調整書類のデジタル化と提出、そして、マイナポータル連携による控除証明書等の自動取得の二つのポイントに分けて説明します。年末調整書類のデ...
 賃金・賃金制度
賃金・賃金制度  賃金・賃金制度
賃金・賃金制度  日常業務
日常業務  採用
採用 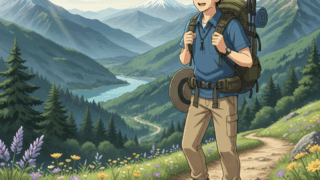 労働時間
労働時間  ハラスメント
ハラスメント  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  採用
採用 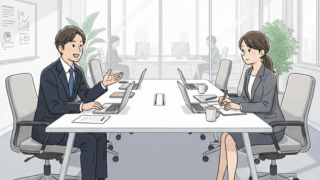 採用
採用