 賃金・賃金制度
賃金・賃金制度 成果主義賃金制度はなぜ敬遠されるのか?
今の若者は安定志向が強い傾向にあります。これは、日本の経済状況や社会の変化を背景とした、彼らの合理的な選択であると捉えられます。そして、その安定志向の強さから、従来の「ハイリスク・ハイリターン型」の成果主義賃金制度は敬遠される傾向があります...
 賃金・賃金制度
賃金・賃金制度  採用
採用  採用
採用 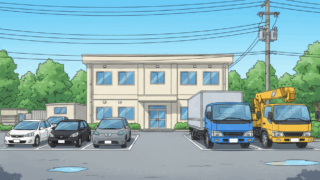 安全衛生管理
安全衛生管理  日常業務
日常業務 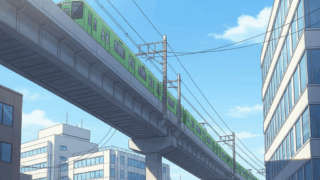 会社の運営
会社の運営  防火・防災
防火・防災  IT
IT  IT
IT  IT
IT