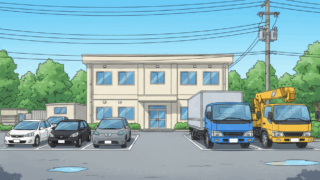 労働時間
労働時間 シフト制とは?運用の注意点を解説
シフト制とはシフト制とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどによって、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。「シフト制」と...
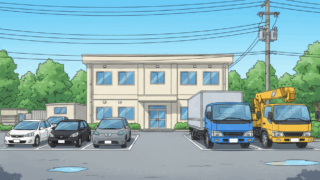 労働時間
労働時間  経理の事務
経理の事務  経理の事務
経理の事務  経理の事務
経理の事務  採用
採用  採用
採用  採用
採用  採用
採用  個人情報保護
個人情報保護  個人情報保護
個人情報保護