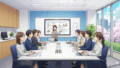従業員の社会保険料控除は、当月控除または翌月控除の方式がありますが、一般的には翌月徴収が行われています。当月控除と翌月控除の違いについて、少し詳しく解説します。また、退職する日によって控除が違う点についてもあわせて解説します。
入社するときの社会保険料控除
社会保険の資格取得日と保険料の発生
例えば、10月1日入社、会社の給料が20日締、月末払の場合、最初に受け取る10月末日の給料から社会保険料が引かれるか検討してみます。
- 資格取得日: 入社日である10月1日です。
- 保険料の発生: 社会保険の加入資格を取得した月(10月)から保険料が発生します。つまり、入社と同時に10月分の保険料の支払い義務が生じます。
保険料の控除タイミング
この10月分の社会保険料がいつの給料から引かれるかは、その会社の就業規則(給与規程)によります。社会保険料の控除を「当月控除」と定めていれば、10月末の最初の給料から差し引かれます。「翌月控除」と定めていれば、10月末の給料からは引かれないで、翌11月末の2回めの給料から差し引かれます。
| 控除パターン | 控除の対象月 | 10月給料(10月末払)から引かれるか |
| 当月控除 | 当月分の保険料を当月の給料から控除 | 引かれます(10月分保険料を10月給料から控除) |
| 翌月控除 | 前月分の保険料を当月の給料から控除 | 引かれません(10月分保険料は11月給料から控除) |
退職するときの社会保険料控除
退職月の社会保険料の控除は、退職日と会社の控除ルール(当月控除か翌月控除か)によって変わるため、複雑に感じやすい部分です。
結論から言うと、退職月の控除額は主に以下の3パターンになります。
- 控除なし(0ヶ月分)
- 1ヶ月分の控除あり
- 2ヶ月分の控除あり
退職日による違い
退職日によって社会保険料の控除額が違う背景には、次の2つのルールが関係しています。
ルール1:保険料は「月単位」で計算される
社会保険料は、日割りではなく月単位で計算されます。
- 資格取得日(入社日)の月から発生します。
- 資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月まで保険料がかかります。
ルール2:月末退職は「翌月1日喪失」になる
月末に退職した場合、資格喪失日(保険をやめる日)は翌月1日になります。
- 例えば、10月31日退職であれば11月1日が資格喪失日です。
- 11月1日に資格を喪失したということは、10月31日までは加入していたことになり、10月分の保険料まで発生します。
月末以外(例えば月末の前日)に退職した場合次のようになります。
- 例えば、10月30日退職すると、資格喪失日は10月31日です。
- 10月31日に資格を喪失したということは、10月分の保険料は発生しません(前月分までで終了)。
控除パターンによる違い
次に、「当月控除」と「翌月控除」の違いで退職時の社会保険控除がどうなるか解説します。(ここでは退職月を10月として説明します)
翌月控除の会社の場合
翌月控除は、前月分の保険料を当月の給与から控除するルールです。
ケースA:10月30日など「月末以外」に退職する場合の控除は1ヶ月分
| 項目 | 9月分保険料 | 10月分保険料 | 10月支給の給与からの控除 |
| 発生 | 発生 | 発生しない (10月31日資格喪失のため) | 9月分を1ヶ月分控除 |
| 説明 | 10月分の保険料は発生しないため、退職月の給与からは、前月(9月)分の保険料のみが控除されます。 |
ケースB:10月31日など「月末」に退職する場合の控除は2ヶ月分
| 項目 | 9月分保険料 | 10月分保険料 | 10月支給の給与からの控除 |
| 発生 | 発生 | 発生する (11月1日資格喪失のため) | 9月分+10月分の2ヶ月分を控除 |
| 説明 | 10月分の保険料が発生します。翌月控除の会社は、退職月(10月)の給与で、まだ控除していない前月分(9月)と当月分(10月)をまとめて控除します。 |
当月控除の会社の場合
当月控除は、当月分の保険料を当月の給与から控除するルールです。
ケースC:10月30日など「月末以外」に退職する場合の控除は0ヶ月分
| 項目 | 9月分保険料 | 10月分保険料 | 10月支給の給与からの控除 |
| 発生 | 発生 | 発生しない (10月31日資格喪失のため) | 9月分の清算になるが0ヶ月分 |
| 説明 | 10月分の保険料は発生しません。また、9月分の給与で9月分がすでに控除されているため、控除額は0ヶ月分となることが一般的です。 |
ケースD:10月31日など「月末」に退職する場合の控除は1ヶ月分
| 項目 | 9月分保険料 | 10月分保険料 | 10月支給の給与からの控除 |
| 発生 | 発生 | 発生する (11月1日資格喪失のため) | 10月分を1ヶ月分控除 |
| 説明 | 10月分の保険料が発生し、当月控除のルールに従い、10月支給の給与から10月分が控除されます。 |
このように、会社の「いつの給与からいつの分の保険料を引くか」という控除月のルールと、退職日が月末かどうかで、退職月の控除額が大きく変わります。
一般的には翌月控除
社会保険料の控除は翌月控除(保険料が発生した月の翌月の給与から控除)としている企業が一般的です。
しかし、少数派ではありますが当月控除(保険料が発生した月の給与から控除)を選択する企業も存在し、それには主に以下のような理由があります。
当月控除を選択する主な理由
給与と保険料の発生月の同期
当月控除の最大の目的は、給与と社会保険料の発生月を一致させることです。
- 「○月分の給与」から「○月分の保険料」を控除するという構造になるため、経理や従業員にとって、保険料が何の月の分であるかが分かりやすく、給与計算の処理がシンプルになると考える企業があります。
退職時の処理の簡略さ
翌月控除の場合、従業員が月末に退職すると、最後の給与から2ヶ月分の社会保険料(退職月の前月分+退職月分)をまとめて控除する必要が生じることが一般的です。
- 当月控除を採用していると、退職月にはすでに当月分の保険料が控除済みになっているため、最後の給与から控除する保険料は発生せず、清算の手間が少なくなります。特に、給与が少ないパート・アルバイトの場合、最後の給与が2ヶ月分の保険料を賄いきれず、不足分を別途徴収する手間を避ける目的もあります。
当月払い企業との相性
給与の締め日・支払い日が「当月締め・当月払い」という企業は、給与の発生と支払いのタイミングが早いため、社会保険料も「当月の給与から控除する」という流れに統一しやすいという面があります。
翌月控除が一般的な理由
当月控除にもメリットはありますが、翌月控除が一般的なのは、給与計算の事務処理上の利便性と資金的な理由からです。
- 社会保険料は、原則として翌月に納付します。翌月控除にすることで、保険料の納付月と徴収月を合わせることができ、企業側の資金繰りや会計処理が分かりやすくなります。
「当月控除」か「翌月控除」かは、法律で厳密に定められているわけではなく、企業が給与規程などで自由に定めることができます。ご自身の会社がどちらのルールを採用しているかは、就業規則や給与明細を確認するか、総務・経理部門にご確認ください。
当月控除が問題になることはないか
健康保険法の次の規定を根拠に、社会保険料は翌月控除が妥当で、当月控除は法の主旨にそぐわないという意見があります。
健康保険法第167条第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
ここでは、「前月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除できると規定されているため、「翌月控除」が法の原則であり、法の主旨に最も忠実な方法であると解釈できます。
しかし、現実として「当月控除」が存在するのは、この法律の規定が「翌月控除を義務付けるものではない」と解釈されているためです。給与計算ソフトが「当月控除」にも対応しているのは、それが法律上許容される実務の一つとなっているためです。
法定されているのは「控除の時期の上限」
健康保険法第167条第1項は、以下の2点を定めています。
- 原則: 被保険者の負担すべき前月の保険料を控除できる。
- 例外(退職時): 従業員が退職した月は、前月およびその月(退職月)の保険料を控除できる。
健康保険法第167条第1項は、「前月の保険料を控除できる」と定めています。これは翌月控除を認める規定であり、「当月控除をしてはならない」という禁止規定ではありません。
つまり、「前月分」と定めることで、少なくとも翌月(前月分)以降の給与で控除すべきという、控除時期の上限的なガイドラインを示していると解釈されています。
当月控除が許容される背景
当月控除を選択している企業は、この法律の規定を「前月分までを控除できる」という上限規定と捉えており、「当月分の保険料を当月の給与から控除すること」は、従業員との合意(給与規程や就業規則など)があれば、法律の制限を超えないため許容される、と考えられています。
当月控除は、最終的な総支払保険料額が変わるわけではありません。また、入社時に多少手取りが少なくなることはあっても、退職時は逆に控除が少なくなる(もしくはゼロになる)ため、金銭的な不利益が相殺されます。したがって、従業員側に大きな金銭的損害がありません。