傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んで、給与の一部または全部が支給されないときに支給される手当金です。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までが対象です。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間があった場合は、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能です。
支給額
標準報酬月額の3分の2
金額は、よく給与の3分の2と言われますが、協会けんぽの場合は以下の計算式で求められます。
支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額 ÷ 30日 × 3分の2
標準報酬月額とは、従業員の月々の給与を1~50の等級に分けてあてはめたものです。例えば、月額給与(手当込み)が25万円から27万円までの人の標準報酬月額は26万円です。社会保険(厚生年金保険料・健康保険料)では実際の給料ではなく、標準報酬月額で計算します。標準報酬月額が給料明細書に記載されていない場合があります。知りたい場合は給与担当者に聞けばすぐに分かります。
給与が支払われると減額や支給停止
傷病手当金は療養のために仕事ができず(労務不能)、賃金を受けられない時の生活費補填のために支給されるものです。
仕事をして報酬を得れば、労務可能とみなされ支給できなくなります。労務の提供がない状態で事業主から生活支援の金銭が支払われるのであれば、減額や支給停止となります。
社会保険料が差し引かれる
病気やケガで休職中に「傷病手当金」を受け取っている場合でも、社会保険料の免除はありません。傷病手当金は非課税ですが、そこから社会保険料(自己負担分)を支払う必要があります。
支給期間
仕事ができず休業している期間が4日以上あるときに支給されます。最初の連続3日間は傷病手当金は支給されません。この3日間を「待期期間」といいます。
最初の3日間は「連続」していなければなりません。例えば、2日目にいったん出社すれば、3日目から改めて連続3日をカウントします。4日目からは連続した休みである必要はありません。
なお、最初の3日間は有給休暇や休日、祝日に該当する日であっても対象としてカウントされます。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月までです。途中で給与を受け取ったなどの理由で傷病手当金が支給されない期間があれば、その期間は1年6か月の期間に含まれません。
言いかえれば、傷病手当金の支給開始日から、同一の病気やケガにより会社を休んだ日数の合計が1年6ヶ月に達するまで、傷病手当金を受給することができます。
暦日の1年6か月ではないのでご注意ください(令和4年1月1日から施行)。
これは、同じ病気であればという説明です。違う病気であれば、すでに受給していても新たに傷病手当金を受給することができます。
病名が同じでも、新たな傷病手当金を受給できる場合があります。次の記事を参照してください。
受給手続き
確認する事項
基本的には従業員が自ら申請する手続きですが、申請書に会社記入欄もあることから、会社が手続きをサポートするのが一般的です。
従業員から病気やケガで休むという連絡を受けたときは次の点を確認します。
□ その傷病は仕事に関係あるか
仕事に関係があれば労災の可能性があります。労災であれば傷病手当金の手続きはできません。
□ 何日休む予定か
4日以上であれば傷病手当金の支給を受けることができることを伝えます。待期期間の3日間、あるいはそれ以降に有給休暇を使用するかも確認します。
手続きの流れ
申請手続きは、主に「本人」「会社」「医師」の三者の連携が必要となります。
以下に、傷病手当金申請の一般的な流れを手順を追って解説します。
ステップ1:申請書の入手
- 従業員: 会社の人事・総務担当部署から「健康保険 傷病手当金 支給申請書」(以下、「申請書」)を受け取るか、加入している健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)のウェブサイトからダウンロードします。
- 申請書は、通常「被保険者記入用(2枚)」「事業主記入用(1枚)」「療養担当者(医師)記入用(1枚)」の合計4枚綴りになっています。
ステップ2:【本人記入】「被保険者記入用」の作成
- 従業員: 申請書の「被保険者記入用」の欄に、以下の情報を記入します。
- 氏名、生年月日、被保険者証の記号番号
- 休業した期間(申請期間)
- 傷病名、発病・負傷年月日、傷病の原因
- 振込先口座(原則、被保険者本人の名義の口座)
ステップ3:【医師記入】「療養担当者記入用」の依頼
- 従業員: 通院先の医療機関(医師)に申請書を渡し、「療養担当者記入用」の記入を依頼します。
- 重要: 医師には、休業期間中に「労務不能であった」ことを診断し、証明してもらう必要があります。この証明がなければ支給は受けられません。
- 医療機関での書類作成には時間がかかることがあるため、早めに依頼することが推奨されます。
ステップ4:【会社記入】「事業主記入用」の作成と証明
- 会社: 従業員から受け取った申請書の「事業主記入用」の欄に、以下の情報を記入し、事業主証明(押印または署名)を行います。
- 休業期間中の従業員の出勤状況(出勤簿などの確認)
- 休業期間中の賃金(給与)の支払いの有無と、その金額(賃金台帳などの確認)
ステップ5:保険者への提出(申請)
- 会社または従業員: 4枚一組の申請書がすべて揃ったら、加入している健康保険の窓口に提出します。
- 提出先:
- 協会けんぽの場合:事業所の所在地を管轄する協会けんぽの支部
- 健康保険組合の場合:当該健康保険組合
- 提出方法: 会社経由で提出することが一般的ですが、従業員本人が直接郵送または窓口に持参することも可能です。
- 提出先:
ステップ6:審査と支給
- 保険者: 提出された申請書に基づき、支給要件を満たしているか審査を行います。
- 支給: 審査に問題がなければ、通常、申請から2週間~1ヶ月半程度で、申請書に記載された金融機関口座に傷病手当金が振り込まれます。
- 不備があった場合は、書類が差し戻されるため、支給が遅れる原因となります。
【請求期限の注意点】
傷病手当金には時効があり、療養のために仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で請求権が消滅します。長期休業の場合は、給与の締め日ごとに分けて定期的に申請することが推奨されます。
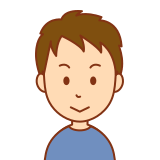
従業員から思っていたより少ないと言われることがあります。多くの場合は支給対象の認識違いによるものです。医師が労務不能と認定した期間に出勤した場合。逆に、医師が労務不能と認定しない日に、本人が大事をとって仕事を欠勤した場合などは傷病手当金の支給対象期間になりません。本人が申し出た申請期間にこうした期間が入っていることがあります。
別の傷病が生じた場合
傷病手当金を受給中に、新たな傷病が生じた場合、1つ目の傷病と同様の受給手続きをすることができますが、二重に支給されることはありません。最初の傷病による支給期間が満了したり支給停止されたときは別の傷病に対する傷病手当金を受給できます。
退職後の継続給付
傷病手当金は条件が適合すれば退職して被保険者でなくなってからも支給される場合があります。




