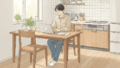健康保険の資格喪失後の給付
退職後の傷病手当金
一定の条件を満たしていれば、会社を退職した後の期間についても引き続き傷病手当金を受給することができます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
継続して受給するための主な条件は以下の通りです。
- 被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(健康保険の資格を喪失した日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続被保険者期間や国民健康保険の加入期間は含まれません。)
- 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
- 退職日(資格喪失日の前日)に、傷病手当金の支給を受けているか、または支給を受けるための条件(待期期間3日間の完成、労務不能であることなど)を満たしていること。
- 特に重要な点として、退職日に出勤していないことが必要です。
- 退職後も引き続き同じ傷病で労務不能の状態であること
- 退職した後の期間も、引き続き同じ病気やケガの療養のために仕事ができない状態が続いていること。
- 一度でも仕事に就くことができる状態(労務可能日)と判断された場合、それ以降は継続給付を受けることはできなくなります。
【支給期間について】
支給期間は、最初に傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヶ月が限度です。退職前に受給していた期間があれば、その期間を差し引いた残りの期間が退職後も支給されます。
退職後の出産手当金
出産手当金も、傷病手当金と同様に「資格喪失後の継続給付」の制度がありますが、受給できるための条件が少し異なります。
傷病手当金と同じく、退職後も引き続き受給するためには以下の条件を満たす必要があります。
退職後の出産手当金(継続給付)の主な条件
- 被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(健康保険の資格を喪失した日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
- 退職日が支給対象期間に含まれていること
- 退職日が、出産手当金の支給対象期間(出産予定日以前42日[多胎は98日]から出産日後56日)に含まれていること。
- 退職日に出勤していないこと
- 退職日に労働に従事していないこと。
傷病手当金との主な違い
| 項目 | 傷病手当金(継続給付) | 出産手当金(継続給付) |
| 被保険者期間 | 継続して1年以上が必要 | 継続して1年以上が必要 |
| 資格喪失時の要件 | 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること | 退職日が支給対象期間(産前42日~産後56日)に含まれていること |
| 継続性の要件 | 退職後も引き続き労務不能の状態であること(一度でも回復すると打ち切り) | 支給期間(産後56日まで)の満了まで給付される |
特に注意すべき点は、「退職日」と「出産手当金の支給対象期間」の関係です。出産手当金は、退職日が出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)の期間に含まれていないと、退職後の継続給付を受けることができません。
資格喪失後の出産育児一時金
出産育児一時金についても、退職後の支給を受けるための制度があります。
傷病手当金や出産手当金と同様に「資格喪失後の継続給付」の一つですが、退職時に支給を受けている必要がない点が、他の二つの手当と大きく異なります。
退職後の出産育児一時金 受給の主な条件
出産育児一時金は、退職日時点で以下の2つの条件をすべて満たしていれば支給されます。
- 被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(健康保険の資格を喪失した日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。(任意継続被保険者期間は含まれません。)
- 資格喪失後6ヶ月以内の出産であること
- 健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から6ヶ月以内に本人が出産していること。
【ポイント】
- 「継続給付」の扱いが異なる:
- 傷病手当金や出産手当金と異なり、退職時に支給を受けている必要はありません。
- 対象は「本人」のみ:
- 退職後に支給されるのは、被保険者であった本人の出産が対象です。退職後に被扶養者(配偶者など)が出産した場合は、この制度の対象にはなりません。
- 他の保険との選択:
- 退職後に他の健康保険(国民健康保険や配偶者の健康保険の被扶養者)に加入し、そこから出産育児一時金を受けられる場合は、以前加入していた健康保険から受け取るか、現在加入している健康保険から受け取るかを選択することになり、両方から重複して受け取ることはできません。
資格喪失後の埋葬料
埋葬料についても、「資格喪失後の継続給付」として、退職後に支給される制度があります。
傷病手当金や出産手当金と比べて、被保険者期間が1年未満でも支給されるケースがあるなど、要件が異なります。
退職後の埋葬料(費)受給の主な条件
被保険者であった人が亡くなったとき、以下のいずれかの条件を満たしていれば、埋葬を行った人に対して埋葬料(または埋葬費)が支給されます。
- 資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
- 健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から3ヶ月以内に亡くなった場合。
- この場合、退職前の被保険者期間が1年未満でも支給対象となります。
- 継続給付を受けている間に死亡したとき
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなった場合。
- 継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けなくなった日から3ヶ月以内に亡くなった場合。
【ポイント】
- 支給対象者:
- 通常、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人(遺族など)に「埋葬料」(一律5万円)が支給されます。
- 生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」(埋葬にかかった費用の実費、上限5万円)が支給されます。
- 家族の死亡(家族埋葬料):
- 退職後に、被保険者であった人の被扶養者(家族)が亡くなった場合、家族埋葬料は支給されません。
この埋葬料の制度は、他の継続給付(傷病手当金・出産手当金)と密接に関連しているのが特徴です。
手続きや詳細な条件については、ご加入されていた健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)にご確認ください。