 労働基準法
労働基準法 妊産婦が請求できる労働時間の制限
変形労働時間制の適用女性が「妊産婦」(妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性)である場合に請求したときは、変形労働時間制の適用に制限があります。労働基準法に基づき、妊産婦が請求した場合は、使用者は以下の制限を守る必要があります。法定労働...
 労働基準法
労働基準法  経理の事務
経理の事務  経理の事務
経理の事務  経理の事務
経理の事務 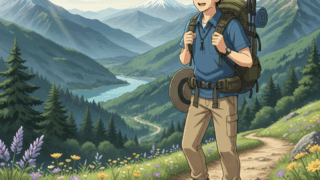 労働時間
労働時間  労働時間
労働時間  ハラスメント
ハラスメント  労働時間
労働時間  日常業務
日常業務  採用
採用