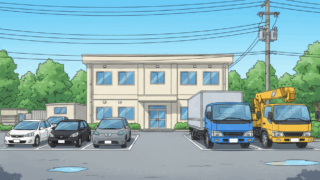 安全運転
安全運転 安全が懸念される状況での復職にどう対応するべきか?
ケーススタディ小規模な運送会社の社長です。運転職の従業員が心臓の手術をして会社に復帰してきました。本人はまったく元通りなのですぐに運転職に復帰したいと希望しています。運転に差し支えないという診断書も持ってきました。私には医学的知識がありませ...
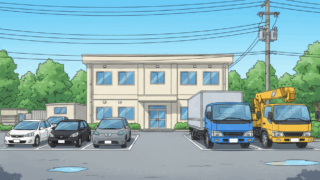 安全運転
安全運転  安全運転
安全運転 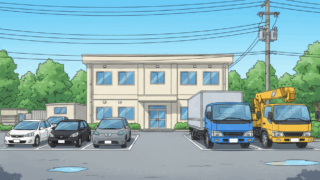 安全運転
安全運転  安全運転
安全運転 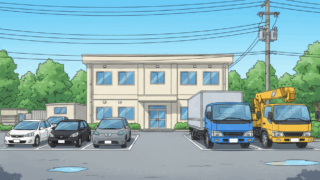 安全運転
安全運転  安全運転
安全運転 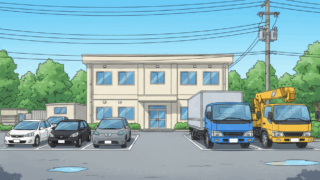 安全運転
安全運転 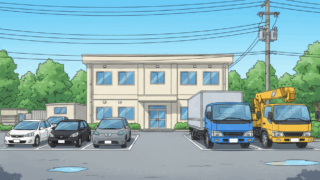 マニュアル
マニュアル 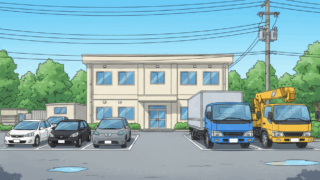 安全運転
安全運転  安全運転
安全運転