 社会保険
社会保険 育児休業等終了時の報酬月額改定
標準報酬月額とは標準報酬月額とは、毎月の給与から引かれる健康保険料や厚生年金保険料の計算の元になる金額のことで、標準報酬月額が低くなればこれらの社会保険料は安くなります。ただし、すぐに連動するのではなく、随時改定では「固定的賃金の変更があっ...
 社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険  社会保険
社会保険 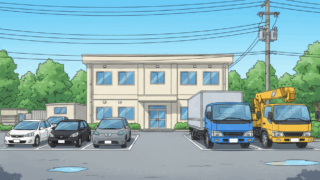 社会保険
社会保険 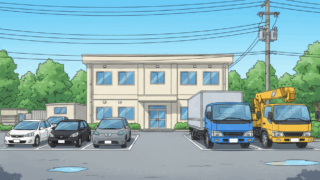 社会保険
社会保険