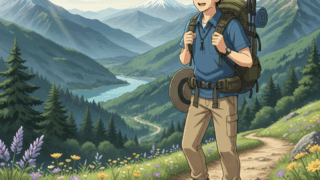 労働時間
労働時間 有給休暇の取得理由を聞いてはいけないの?
有給休暇の申請があったときに、上司が理由を聞くのが良くないと聞きましたが、普通の人間関係であれば、どうしたの?どこかへ行くの?とか会話するのが自然だと思うのですが、やはり、聞いてはいけないのですか?法律上は「理由」を言わなくてもよい法律上の...
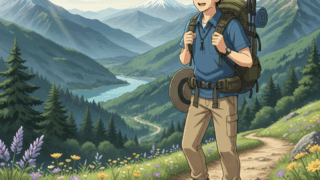 労働時間
労働時間 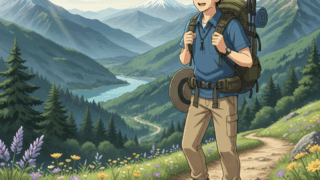 労働時間
労働時間 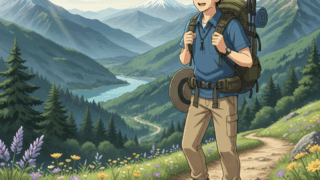 労働時間
労働時間 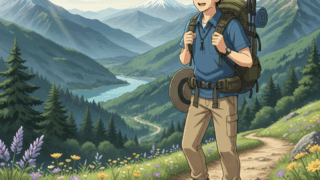 労働基準法
労働基準法  労働基準法
労働基準法  労働基準法
労働基準法 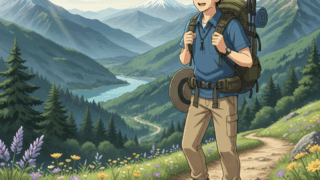 労働基準法
労働基準法  労働時間
労働時間  労働時間
労働時間