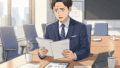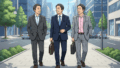年次有給休暇の基準日統一について、入社日が異なることによる管理の不便さを解消する方法として、基準日を統一することのメリットとデメリットを、人事課長と新人人事担当者の会話形式で解説します。
有給休暇の基準日統一ってどうですか?
新人人事(以下、新): 課長、年次有給休暇の管理についてご相談があります。従業員によって入社日がバラバラなので、有給の付与日もそれぞれ違って、残日数の管理がすごく複雑で…。これをもう少しシンプルにする方法はないでしょうか? 基準日を統一する、という話を聞いたことがあるのですが、どうなんでしょう?
課長: そうだね。入社日ごとに管理するのは、確かに手間がかかるし、ミスも起きやすい。「基準日の統一」は、有給休暇管理を効率化する有効な手段の一つだよ。
新: そうなんですね!具体的にどういうことなんでしょうか?
基準日を統一するとは?
課長: 基準日を統一するというのは、文字通り、全従業員の年次有給休暇の付与日を、特定の日に合わせるということだ。例えば、毎年4月1日や1月1日といった、会社の会計年度の始まりやキリの良い日を「有給休暇の基準日」と定めるんだ。
新: なるほど!そうすれば、全員一斉に有給が付与されるので、管理はすごく楽になりそうですね!
基準日を統一するメリット
課長: その通り。基準日を統一するメリットはいくつかあるよ。
管理業務の効率化:これが一番大きいね。付与日が一斉になることで、年に一度、まとめて付与処理ができるようになる。残日数の確認や、年5日取得義務の管理も格段に楽になるよ。
従業員への説明のしやすさ:全員が同じ日に有給が付与されるので、「あなたの有給は〇月〇日に付与されます」と個別に説明する必要がなくなり、従業員も自分の有給付与日を覚えやすくなる。
計画的付与の導入が容易に:年5日を超える部分について、会社が計画的に有給休暇を取得させる「計画的付与」を導入する場合、基準日が統一されていると、全社的な計画が立てやすくなる。
新: メリットはたくさんありそうですね!ぜひ導入したいです!
基準日を統一するときの注意点
課長: ただ、良いことばかりではない。基準日を統一する際には、いくつか注意すべき点や、不都合が生じる可能性もあるんだ。
労働者にとって不利益にならないこと: これが最も重要だ。労働基準法では、有給休暇の付与は、労働者が不利にならないように行わなければならないとされている。基準日を統一することで、本来付与されるはずだった有給休暇の日数が減ったり、付与されるまでの期間が不当に長くなったりしてはならないんだ。
新: 不利益にならないように、ですか…。具体的にはどういうことでしょうか?
課長: 例えば、入社から6ヶ月後に最初の有給が付与されるのが原則だよね。基準日を統一する場合、入社日から最初の基準日までの期間が6ヶ月未満の従業員には、その期間に応じて「前倒しで」有給を付与する必要がある。そして、その付与日数が、本来6ヶ月後に付与される日数(例えば10日)を下回らないように配慮しなければならないんだ。
また、付与される日数が減ってしまうような場合は、減った分を補填するなどの措置が必要になることもある。
また、次の点にも注意を払ってほしい。
労使協定の締結と就業規則の変更: 基準日を統一するには、労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結し、就業規則も変更して労働基準監督署に届け出る必要がある。勝手に変更することはできないから、従業員への説明や合意形成に時間と手間がかかる可能性があるんだ。
導入時の計算が複雑になる可能性: 統一する初年度は、従業員それぞれの入社日と統一後の基準日との兼ね合いで、最初の付与日数を計算するのが一時的に複雑になる場合がある。特に、入社して間もない従業員や、既に多くの有給を消化している従業員など、個別の状況に応じた調整が必要になることがあるよ。
従業員への丁寧な説明: 制度が変わることで、従業員から「なぜ変わるのか」「自分にとって不利にならないか」といった疑問や不安の声が出る可能性がある。変更の目的(管理の効率化など)や、従業員に不利益が生じないように配慮している点を、丁寧に説明し、理解を得ることが不可欠だ。
新: なるほど、管理は楽になるけど、導入するまでが大変そうですね。特に、従業員に不利益を与えないように、最初の付与日数の計算や調整が重要だということですね。
課長: その通りだ。基準日の統一は、長期的に見れば管理コストの削減や効率化に繋がる良い方法だけど、導入する際には、労働者の権利を侵害しないよう、細心の注意を払う必要がある。
わが社もだいぶ人数が増えたので、そろそろ基準日を統一したほうが良いかもしれない。まずは現状の有給付与状況を詳しく分析したうえで、一人ひとりに不利益が生じないような案と実施スケジュールを作成してください。
新: はい! ありがとうございます、慎重に進めていきたいと思います!