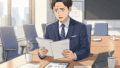労働基準法に定められている「軽易な業務への転換」の規定は、働く女性の母性保護において非常に重要な制度です。これについて、根拠となる法令と、事業主(会社)が負う義務の詳細を説明します。
法的根拠と義務の性質
この規定は、労働基準法第65条第3項に定められています。
「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」
義務の性質は「絶対的」
この規定は「〜させなければならない」と定められており、妊娠中の女性労働者から請求があった場合、事業主は原則としてこれを拒否することはできません。これは母性保護のための絶対的な義務です。
適用される期間
軽易な業務への転換が認められるのは、妊娠中の女性に限られます。産後(産後休業終了後)の女性はこの条文の対象外ですが、別の法律(男女雇用機会均等法)に基づく健康管理上の措置の対象にはなり得ます。
「軽易な業務」の範囲と企業の対応
「軽易な業務」の具体的な内容は法令で明確に定義されていませんが、一般的に現在の業務よりも身体的・精神的な負担が少ない業務を指します。
転換が必要な業務の例
妊娠中の女性にとって負担が大きいとされる業務の例としては、以下のようなものがあります。
- 肉体的負担:長時間の立ち仕事、前かがみの姿勢を続ける作業、頻繁な階段の昇降、重量物の取扱い(重い荷物の運搬など)。
- 環境的負担:有害ガスや放射線など有害物質を取り扱う業務、高温・多湿または寒冷な場所での作業、著しい振動を伴う機械を扱う業務。
- 勤務態様:通勤ラッシュ時の勤務、頻繁な夜勤や時間外労働(これらは別途、労働基準法第66条で制限されます)。
請求と不利益取扱いの禁止
転換請求の要件
この制度は、女性労働者からの請求(申出)があって初めて効力が発生します。会社が一方的に転換させることはできません(本人の同意が必要です)。
また、請求の際、医師等から出された「母性健康管理指導事項連絡カード」など、医師の指導内容を示す書面を提出すると、具体的な転換の必要性が明確になり、会社側も対応しやすくなります。
不利益取扱いの禁止
妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求し、またはその措置を受けたことを契機として、降格、減給、不当な配置転換、解雇などの不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法により禁止されています。企業は、制度の利用を理由として、労働者に不利益を与えてはなりません。
企業が負う義務の限界(業務の新設義務は無い)
事業主には軽易な業務への転換義務がありますが、厚生労働省の通達(行政解釈)により、転換させるべき軽易な業務が社内に存在しない場合、そのために新たな業務を創設して与える義務までは課されていないとされています(昭61.3.20 基発第151号など)。
しかし、条文の「絶対的義務」としての側面と、他の法令(男女雇用機会均等法)に基づく「母性健康管理措置の義務」とを組み合わせることで、企業には実質的な対応が強く求められています。
軽易業務転換の「実効性」が制限されている
実効性が低下する主な原因は、「新たな業務の創設義務はない」という通達(行政解釈)にあります。
- 業務の新設義務なし:企業がもともと軽易な業務を一切持たない場合、または妊婦の請求内容に応じた軽易な業務を新たに生み出す必要がないため、形式的には「義務を果たしている」とみなされる可能性があります。
- 中小企業・専門職での課題:特に業務が固定化されやすい中小企業や、専門性の高い職種(例:プログラマー、特定の技能職)では、「他の軽易な業務」が存在しないことが多く、結果として制度を利用できないケースが生じます。
軽易業務転換の「実効性」を担保するために
「やむを得ない」という解釈がある中でも、実効性を担保するために以下の点が重要となります。
「軽易な業務がない」と判断するのは企業側ですが、従業員が請求した場合、企業には転換に「応じなければならない」という絶対的な義務があります。
- 拒否は違法:請求を安易に拒否した場合、労働基準法違反となります。
- 業務内容の調整:既存の業務をすべて変える必要はなくても、作業時間、作業量、作業姿勢、持ち運び重量などを調整することで「軽易な業務」とすることは可能です。極端な肉体労働や危険有害業務からの解放は必須です。
労働基準法だけでなく、男女雇用機会均等法第13条が定める母性健康管理措置が実効性を高めています。
- 医師の指導事項への対応義務:妊婦が健康診査等を受け、医師から「○○(例:長時間の立ち仕事)を避けるように」と指導を受けた場合、事業主は均等法に基づき、その指導事項を守れるように勤務時間の変更、勤務の軽減等、必要な措置を講じる義務を負います。
- 拒否は均等法違反:医師の指導があるにもかかわらず、企業が適切な措置(勤務の軽減)を講じなければ、均等法違反となり、行政指導の対象になります。
この均等法の措置義務は、労基法の「軽易な業務転換義務」よりも広く、既存の業務であっても負担軽減策を講じることを実質的に強制しています。