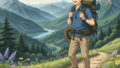3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置を実施しなければなりません。(2025年10月改正施行)事業主が、「柔軟な働き方を実現するための措置」を選択・導入する際に注意すべき点は多岐にわたります。主な注意点を以下に整理します。
この義務は、企業規模の大小に関わらず全ての事業主に課され、対象となるのは3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者です。
会社が講ずべき措置の選択と整備
会社は、国が示す以下の5つの措置の中から2つ以上を選択し、制度として導入することが義務となります。
| No. | 措置の具体的な内容 | ポイント |
| ① 始業時刻等の変更 | フレックスタイム制 または 時差出勤制度(始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げ)を導入。 | 1日の所定労働時間は変更しないことが基本です。 |
| ② テレワーク等 | 自宅やサテライトオフィス等で働く制度を導入。 | 月に10労働日以上、原則として時間単位での利用ができる制度である必要があります。 |
| ③ 保育施設の設置運営等 | 自社で保育施設を設置・運営する、またはこれに準ずる便宜(ベビーシッターの手配や費用負担など)を供与する制度。 | 福利厚生制度(カフェテリアプラン等)での費用補助も含まれます。 |
| ④ 養育両立支援休暇 | 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を付与。 | 年に10日以上、原則時間単位での取得も可とし、取得理由は限定しない制度。 |
| ⑤ 短時間勤務制度 | 3歳以上の短時間勤務制度を導入。 | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むものとする必要があります。 |
各措置の詳細と運用に関する注意点
テレワーク等
「在宅勤務等の措置」は、1日の所定労働時間を変更することなく利用できるものでなければなりません。
利用できる日数は、1か月につき、週5日勤務の労働者については10労働日以上が求められます。週5日以外の労働者については、週の所定労働日数や平均所定労働日数に応じて日数を調整します。
利用は、1日の所定労働時間数に満たない「時間」を単位とし、始業から連続、または終業まで連続して利用できるものとします 。
この「10労働日以上」という日数は、措置を講じていると認められる最低限の日数であり、より高い頻度で利用できる措置とすることが望ましいとされています。
「テレワーク等」には、情報通信技術を利用しない業務も含まれます。
実施場所は自宅が基本ですが、事業主が認めるサテライトオフィス等も含まれます。
利用日数は、1週間の所定労働日数が5日の労働者については1か月につき10労働日以上が基準となります。複数月で平均して10労働日以上となるような仕組みは認められません。
テレワーク等の措置を講じる際には、夜間勤務や長時間労働により心身の不調が生じないよう、労働者の健康への配慮が望ましいとされています。面談による健康状況の把握や勤務間インターバル導入も考慮すべきです。
養育両立支援休暇
子の養育に資する目的であれば、利用目的は労働者に委ねられます。
取得期間中は無給でも問題ありませんが、企業独自に有給とすることも可能です。
1年につき10労働日以上の付与が求められます。付与単位を半年ごとや月ごとに設定し、年間で合計10労働日以上確保する仕組みは問題ありません。
保育施設の設置運営等
「設置運営等」にはベビーシッターサービスの手配と費用の一部負担が含まれます。費用負担の程度に基準はありません。
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の割引券のみの提供では、費用負担に該当しないため、措置を講じたことにはなりません。
福利厚生サービス会社と法人契約し、会費を支払うことでベビーシッターサービス料金の一部を負担している場合は、措置を講じたことになります。
原則として事業所ごとに設置が必要ですが、近くの事業所の労働者が利用できる場合はその事業所についても措置を講じたとみなされます。事業所内にある必要はなく、通勤途上など合理的に利用できる範囲であれば認められます。
制度導入のための具体的な手順
義務化に対応するために、会社は主に以下の手順を踏む必要があります。
制度設計と意見聴取
2つ以上の措置を選択
会社の業務特性や労働者のニーズを考慮し、上記5つの選択肢から利用しやすい措置を2つ以上選定します。
既に社内で導入している制度(例: 始業時刻等の変更と短時間勤務制度)がある場合、それが新たな措置義務を履行したとみなされることがあります。
ただし、「始業時刻等の変更」にはフレックスタイム制と時差出勤が含まれますが、これら2つを導入しても1つの措置とみなされ、2つの措置を講じたことにはなりません。
労働者の意見聴取
制度導入(就業規則等に規定)にあたっては、労働者の過半数を代表する労働組合(または労働者の過半数代表者)から意見を聴取する機会を設けなければなりません。
育児当事者からの意見聴取や労働者へのアンケート調査も並行して行うことが望ましいとされています。
意見聴取の結果、労働組合の意見に沿えない場合でも、丁寧にコミュニケーションを取り、判断に至った事情を説明することが重要です。
就業規則等の整備
- 選択した2つ以上の措置の内容を、育児・介護休業規程や就業規則に具体的に規定します。
個別周知と意向確認の実施
- 対象となる労働者(3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者)に対して、以下の事項を個別に周知し、意向を確認することが義務づけられます。
- 講ずることとした柔軟な働き方を実現するための措置の内容(2つ以上の措置)
- 措置の申出先
- 所定外労働、時間外労働、深夜業の制限に関する制度
- 周知・意向確認のタイミング: 原則として、対象となる子(例えば、子が3歳に達する日)の情報を把握した適切な時期に行います。
個別の周知・意向確認に関する注意点
対象者と時期
子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に実施する必要があります。
施行日において既に子が3歳以上小学校就学前である労働者に対しては、個別の周知・意向確認は義務ではありませんが、利用意向が示された場合には対応が必要であり、個別の周知を行うことが望ましいとされています。
将来的に措置の利用が可能になる可能性がある労働者(例:継続雇用期間が1年未満で現在は対象外だが更新により対象となる可能性のある者)についても、3歳になるまでの間に個別の周知・意向確認を実施する必要があります。
日々雇用の労働者など、今後利用する可能性がない場合は実施不要です。
実施方法
面談(オンライン面談も可、ただし音声のみは不可)、書面の交付、FAXの送信(労働者が希望する場合のみ)、電子メール等の送信(労働者が希望し、記録出力が可能なものに限る)のいずれかで行う必要があります。
対象者を一堂に集めて行うことも可能ですが、その場合でも上記の方法に従い、個別の書面交付を伴うなど、各対象者の事情を踏まえた配慮が望ましいです。労働者が意向を表明しにくい状況にならないよう配慮が必要です。
実施者
事業主の委任を受けて権限を行使する者であれば、人事部でなくても所属長や直属の上司が実施しても差し支えありません。
ただし、実施者となる所属長や直属の上司に対し、制度の趣旨や適切な実施方法を十分に周知し、労働者が意向を表明しにくい状況にならないようにすることが重要です.
記録
面談による意向確認の記録は義務ではありませんが、記録が残らないため、必要に応じて作成することが望ましいとされています。
不利益取扱いの禁止
個別の周知・意向確認は、措置の利用申出が円滑に行われるようにすることが目的です。
利用を控えさせるような抑制的な言動や、不利益をほのめかすような行為は禁止されています。過去に前例がないことを強調することも含まれます。
実施と運用の準備
労働者は、事業主が講じた制度の中から1つ選択して利用することができます。
- 労働者が選択した措置を確実に利用できる体制を整えます。
- 労働者から申し出があった場合、選択した措置の中から労働者が1つを選択して利用できるように運用します。
- 制度の利用によって業務に支障が出る場合は、代替要員の確保や業務の調整など、業務運営体制の見直しも必要になります。
その他の注意点
多様な働き方への対応
措置は企業単位だけでなく、事業所単位、事業所内のライン単位、職種ごとに組み合わせを変えて講じても差し支えありません。職場の実情を適切に反映させることが望ましいです。
労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定される措置を講じても、措置義務を果たしたことにはなりません。
シフト制を含む交替制勤務を行う労働者も措置の対象です。テレワーク等が困難な業務の場合は、それ以外の選択肢から2つ以上を措置する必要があります。
正規・非正規雇用労働者間の措置
正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択することは可能ですが、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、不合理な待遇差とならないよう配慮が必要です。
職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情を考慮し、待遇の性質と目的に照らして適切であると認められるようにする必要があります。
差異の理由を労働者に対して合理的に説明できなければなりません。
短時間労働者で既に1日の所定労働時間が6時間以下の場合でも、それをもって直ちに「短時間勤務制度」を措置したことにはならず、他の選択肢と合わせて2つ以上を講じる必要があります。
ハラスメント防止
「柔軟な働き方を実現するための措置」の申出や利用を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
制度の利用を阻害する言動(例:取得を諦めさせるような発言)や、人格を否定するような言動はハラスメントに該当する可能性があります。
事業主は、ハラスメント防止のための方針を明確化し、労働者に周知・啓発し、相談体制を整備するなどの措置を講じなければなりません。
配置転換時の配慮
就業の場所の変更を伴う配置転換を行う場合、労働者の子の養育や家族の介護の状況に配慮が必要です. 労働者の意向を尊重し、代替手段の有無を確認することが求められます。
以上の点を踏まえ、事業主は、労働者の仕事と育児・介護の両立を支援するため、法改正の趣旨を理解し、実情に応じた柔軟な働き方を導入・運用することが求められます。
三歳に満たない子の場合のテレワークとの違い
「柔軟な働き方を実現するための措置」におけるテレワークと、「三歳に満たない子」を養育する労働者に対するテレワークの扱いは、義務の内容と具体的な要件において異なる点があります。
「三歳に満たない子」を養育する労働者の場合
3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務制度は、業務の性質や実施体制により措置を講じることが困難な場合、労使協定により対象外とすることができます。
この場合、事業主は代替措置を講じる義務があり、その代替措置の一つとしてテレワーク等(在宅勤務等)があります。現行制度における他の代替措置は、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営等です。
したがって、テレワークは短時間勤務制度の代替的な選択肢として提供されるものです。
「三歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者の場合
「三歳以上小学校就学前の子」を養育する労働者の場合にでてくるテレワークは、事業主が示す5つの選択肢の一つです。短時間勤務制度の代替措置ではありません。
ご注意
以上は主要な点について整理したものです。詳細は、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」で検索して原文を参照してください。なお、2つの組み合わせとして最も多いのは、始業時刻等の変更と短時間勤務制度が最多のようです。