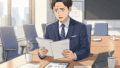ケース
新入社員をつかまえて、「よくこんな会社に来たな、ここはとんでもないブラックだぞ」とか「この会社はそのうちつぶれる、次を考えたほうがよいぞ」などと言う古参の社員がいるそうです。その言葉を真に受けて辞めてしまった新人が何人もいるそうです。私は役員として、そのような噂を聞いて本人に直接注意したのですが「誓ってそんなことは言っていない。それを言ったのは誰ですか、これは名誉毀損だから対決させてください」と興奮して反論してくるありさまです。感触としては、実際に会社を悪く言っていると思うのですが、証拠がありません。どのように対処するべきでしょうか。
会社の未来を担う新入社員が、心ない言葉でモチベーションを下げられ、退職してしまうのは残念です。ご相談の件、まずは証拠がなく本人も認めない状況での対処法について、いくつかのステップをご提案します。
証拠の収集と事実確認
直接的な証言が得られない場合でも、間接的な証拠を探ることはできます。
まだ会社にいる新入社員がいれば、匿名性を保つことを約束したうえで、具体的な状況をヒアリングします。「誰に、いつ、どこで、何を言われたか」をできるだけ詳しく聞き出してください。
他のにもヒアリングしましょう。「そのような発言があるらしい」と、特定の人物を名指しせず、広く聞き込み調査を行うことも考えられます。「最近、新入社員の定着率が悪いことについて、何か心当たりのあることはないか?」など、当たり障りのない聞き方でもよいでしょう。
組織全体へのメッセージ発信
特定の個人を名指しせず、会社全体に向けて再発防止と注意喚起を促します。
「ハラスメント防止」 や 「エンゲージメント向上」 などをテーマにした研修を企画します。研修の中で「根拠のないネガティブな発言が、新入社員の会社への信頼を損ね、退職につながる深刻な問題である」と伝え、安易な発言がもたらす影響を認識させます。
社内報やイントラネット、全体朝礼などを利用して、役員から全社員に向けて「新入社員の成長を支え、組織全体で温かく迎えることの重要性」 を訴えかけます。新入社員の成長を阻害する言動に対しては、会社として看過しない姿勢を明確に示しましょう。
当該社員への指導
証拠はなくても、疑わしい社員への指導は継続する必要があります。再度面談を試みてみましょう。
面談の目的を「非難」ではなく、「会社への貢献」という観点に切り替えるのも一策です。「あなたの長年の経験は評価している。しかし、その貴重な経験や知識が、若い社員にうまく伝わっていないようだ」と伝えてみましょう。
最終的な判断
上記のような対応を続けても改善が見られない場合、最終的には就業規則に基づいた処分を検討することになります。
しかし、それはあくまで最終手段です。まずは「事実の確認」「組織全体への働きかけ」「行動変容を促す面談」を地道に行っていくことが、今回の問題解決の糸口になるかと思います。
このような状況は、個人だけの問題ではなく、組織として改善するべき課題が背景にあることも少なくありません。これを機に、会社にも反省すべき事項があれば謙虚に受け入れ、社員が安心して働ける環境づくりを推進していくことも重要です。