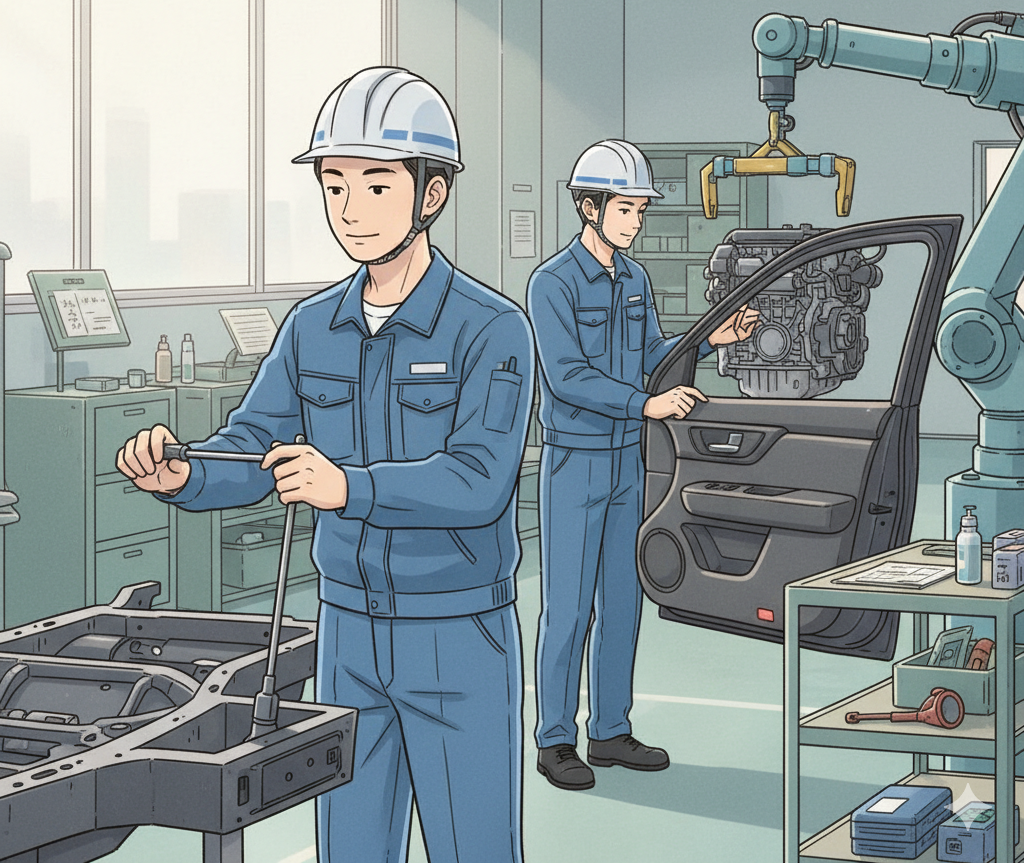法律の規制
化学物質による健康障害防止の基本となる法律は、労働安全衛生法(安衛法)です。
化学物質については、リスクアセスメントの実施義務(第57条の3)、表示・SDS(安全データシート)の交付義務(第57条、第57条の2)などが定められています。
安衛法に基づき、特定の有害性の高い化学物質については、さらに詳細で具体的な規制を定めた特別規則があります。
- 特定化学物質障害予防規則(特化則):ベンゼン、アスベストなど、特に有害性の高い物質を規制します。
- 有機溶剤中毒予防規則(有機則):トルエン、キシレンなどの有機溶剤を規制します。
- 鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則なども含まれます。
健康障害防止対策の主な内容
化学物質による健康障害を防止するための対策は、一般的に「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」の3つが基本とされ、これに加えてリスクアセスメントと化学物質管理体制の整備が重要となります。
| 分類 | 主な対策(措置) | 詳細 |
| リスクアセスメント | 危険性・有害性の特定と評価 | 使用する化学物質の危険性・有害性を特定し、労働者のばく露による健康障害発生の可能性と影響の大きさを評価します。その結果に基づき、必要なリスク低減対策を検討・実施します。 |
| 作業環境管理 | 工学的対策の実施 | 発生源を密閉化・隔離したり、局所排気装置や全体換気装置を設置したりするなど、有害物質の空気中への発散を抑制し、労働者のいる作業場の環境を改善します。 |
| 作業管理 | 作業方法・手順の改善 | 作業方法の改善、作業時間の短縮、適切な保護具(防毒マスク、保護手袋など)の使用、定期的な作業環境測定の実施と評価などを行います。 |
| 健康管理 | 特殊健康診断の実施 | 特定の化学物質を取り扱う労働者に対して、法令に基づき特殊健康診断を定期的に実施し、健康状態を把握します。また、その結果に基づく事後措置(医師の意見聴取、作業転換など)を行います。 |
| 管理体制の整備 | 情報伝達と教育 | SDS(安全データシート)により化学物質の情報を労働者に周知徹底します。また、化学物質管理者を選任し、労働者に対し安全衛生教育を徹底します。 |
化学物質規制が関係する主な業種
化学物質による健康障害防止対策は、化学工業や製造業だけでなく、多岐にわたる業種に関係します。
労働安全衛生法に基づく化学物質規制(リスクアセスメント、SDS交付、化学物質管理者選任など)は、特定の化学物質を製造、取り扱い、または譲渡・提供するすべての事業場が対象となり、業種や規模の要件はありません。
これは、日常生活で使う製品の多くに有害性が存在する化学物質が含まれており、多くの職場でそれらが使用されているためです。
化学物質による労働災害は、製造業だけでなく、建設業やサービス業など第三次産業でも多く発生しており、幅広い業種で対策が必要です。
特に化学物質規制との関わりが深い業種を、使用する物質や作業内容とともに具体的に解説します。
1. 製造業全般
化学物質の規制の中心となる業種です。化学物質を原料として使用したり、製品そのものを製造したり、洗浄や塗装などに使用します。
- 化学工業: 医薬品、農薬、化粧品、合成樹脂、塗料、接着剤、洗剤などの製造。
- 関連物質: 有機溶剤、特定化学物質(ベンゼン、エチレンオキシドなど)、各種反応性化学品。
- 機械系製造業: 自動車、電気機械、精密機械、金属製品などの製造。
- 関連物質: 部品の脱脂・洗浄に使われる有機溶剤(トリクロロエチレン、トルエンなど)、潤滑油、切削油、塗料。
- 食料品製造業: 食品の殺菌・洗浄、添加物の調合など。
- 関連物質: アルカリ性・酸性の洗浄剤、殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)。
2. 建設業
現場での様々な工程で化学物質を含んだ材料を使用します。
- 関連物質: 塗装作業の有機溶剤、接着作業の接着剤、防水工事のアスファルト、内装工事のホルムアルデヒド、解体作業時のアスベスト(特定化学物質)。
3. サービス業・その他
製品の製造工程に関わらなくても、清掃や施設の維持管理のために使用する薬剤が規制の対象となります。
- 清掃業/ビルメンテナンス業:
- 関連物質: 強力な洗浄剤、剥離剤、カビ取り剤(酸性・アルカリ性物質、次亜塩素酸塩など)。
- 医療・福祉業:
- 関連物質: 消毒液、殺菌剤、病院内で使用する医薬品や試薬。
- 教育・研究機関:
- 関連物質: 大学や企業の研究所で使用する各種試薬。少量でも多品種を扱うため、厳格な管理が求められます。
- 印刷業:
- 関連物質: インク、洗浄溶剤など。
4. 卸売・小売業
化学物質を含む製品を製造していなくても、プロ向けの製品を在庫・管理・販売する場合や、自社の倉庫などで小分けする作業を行う場合に規制対象となります。
- 関連物質: 販売する塗料、農薬、業務用洗剤など。
このように、化学物質規制は「化学メーカー」だけではなく、製品の製造、加工、洗浄、メンテナンスなどを行うあらゆる事業場に関係します。自社の事業場で使用している洗剤や潤滑油、接着剤などがリスクアセスメント対象物質を含んでいないかを確認することが、健康障害防止対策の第一歩となります。
労働安全衛生法改正(2025年5月8日)
化学物質による健康障害を防止するための仕組みが整備され、特に情報伝達の徹底と測定の適正化が図られます。
- SDS通知義務への罰則適用: 化学物質の譲渡・提供を行う事業者による、危険性・有害性情報(SDS:安全データシート)の通知義務違反に対し、新たに罰則が設けられます。(2025年5月8日施行)
- 通知事項変更時の再通知の義務化: 通知事項に変更が生じた場合の再通知が、努力義務から義務になります。(2026年4月1日施行)
- 個人ばく露測定の適正化: 労働者が実際にどの程度の化学物質にばく露したかを測定する個人ばく露測定が、作業環境測定の一つとして位置づけられ、作業環境測定士などによる適切な実施が担保されます。(2026年10月1日施行)