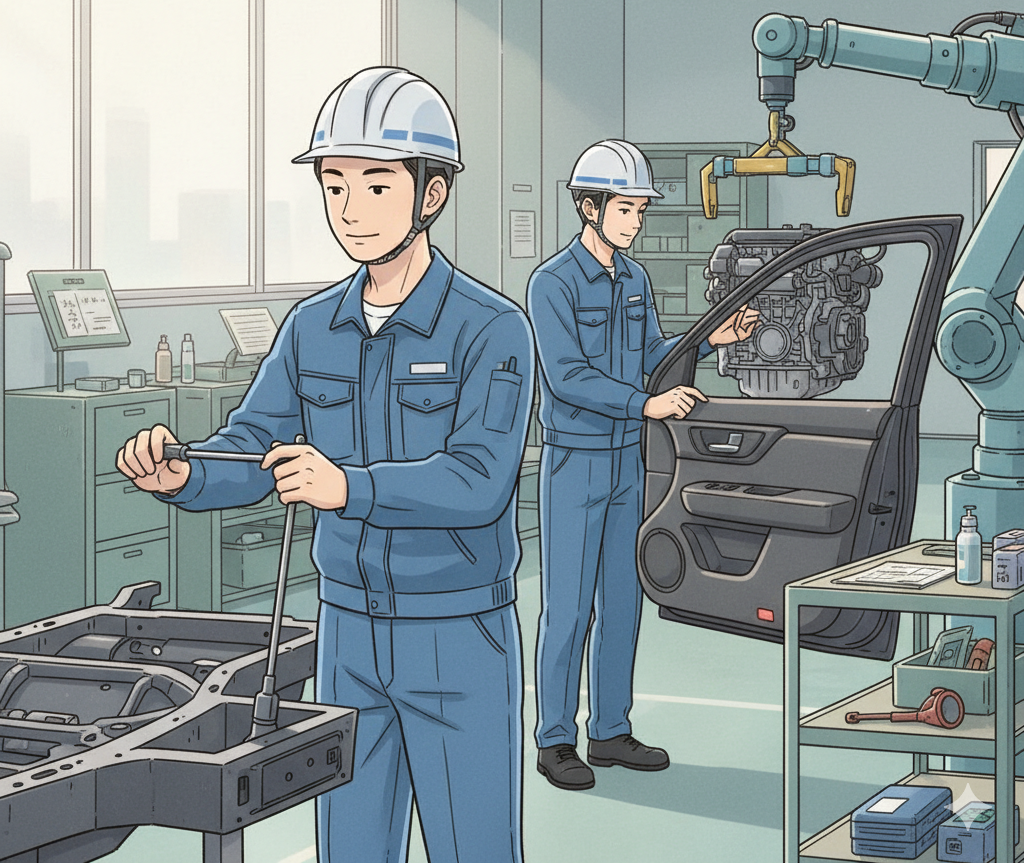労働安全衛生法による機械等による労働災害の防止は、主に事業者に対して、機械の設計、製造、設置、使用、点検といった各段階で、労働者が危険源に触れたり、危険な動作に巻き込まれたりしないよう、具体的な措置を講じることを義務付けるものです。
機械等による労働災害防止の3原則
労働安全衛生法による機械等による労働災害の防止は、具体的には、以下の3つの原則に基づくリスク低減措置が求められます。
1. 本質安全の原則(危険源の除去・低減)
機械自体の危険な箇所(危険源)を、設計段階で除去したり、人に危害を与えない程度に低減したりすることを目指します。
- 具体的な対策例:
- 鋭利な部分や突出部をなくし、角を丸くする。
- 機械の駆動力を小さくしたり、運動エネルギーを下げたりする。
- はさまれる危険のある隙間を、人が進入できないほど狭くするか、はさまれないほど広く設計する。
- 危険な物質を使わない、または最小限にする。
2. 隔離の原則(人と危険源の隔離)
人が機械の危険源に接近・接触できないように隔離することを目指します。
- 具体的な対策例:
- 原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルトなどの危険な部分に、覆い(ガード)や囲い、柵を設ける(安衛則第101条)。
- 産業用ロボットなどの稼働範囲に、人が立ち入れないように柵を設置する。
- 加工物の供給・取り出し作業などを自動化し、人の手が入らないようにする。
3. 停止の原則(危険時の機械停止)
人が機械の動作範囲に入る場合や、危険が差し迫った場合に、機械を確実に停止させることを目指します。
- 具体的な対策例:
- 機械の稼働中に身体の一部が危険区域に入った場合に、自動的に機械を停止させるインターロック付き可動式ガードや光線式安全装置(エリアセンサー)を設置する。
- 掃除、点検、修理などの作業を行う際は、機械の運転を停止し、他の人が誤って起動しないようにロックアウト(鍵かけ)やタグアウト(標識付け)などの措置を講じる(安衛則第107条)。
- 機械の運転を開始する際は、関係労働者に対して一定の合図を定め、合図を行わせる(安衛則第104条)。
その他の重要な措置
上記3原則に加え、労働安全衛生法や関連法令では、以下の措置も義務付けています。
- 特定機械等への規制: クレーン、ボイラー、プレス機械など特に危険性の高い機械(特定機械等)については、製造許可、検査、構造規格への適合などが義務付けられています。
- 作業主任者の選任: プレス機械作業や木材加工用機械作業など、危険な作業を行う場合は、作業主任者を選任し、作業の指揮や機械・安全装置の点検を行わせる必要があります。
- リスクアセスメント: 事業者は、すべての機械設備に対し、危険性や有害性を特定・評価し、その結果に基づきリスクを低減するための措置を講じることが推奨されています(安衛法第28条の2)。
- 安全衛生教育: 労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときなどに、機械の安全な操作方法や緊急時の措置を含む安全衛生教育を実施する必要があります。
法令における根拠と関連条文
労働安全衛生法やその関連法令には、「機械等による労働災害防止の3原則」として明文化された条文や定義はありません。
しかし、この「3原則(本質安全、隔離、停止)」は、安衛法や労働安全衛生規則(安衛則)に定められている具体的な規制や措置の根底にある、安全思想・設計思想として広く認識され、行政や専門機関が労働災害防止の指針として活用しています。
「3原則」の考え方は、以下の安衛法の条文や規制に具体的に反映されています。
1. 本質安全の原則(危険源の除去・低減)
- 安全な設計・製造の要求:
- 安衛法 第20条(事業者の講ずべき措置):事業者は、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない、と定めています。
- 安衛法 第42条(特定機械等の構造規格):特定の危険な機械(ボイラー、クレーン、プレスなど)について、国が定める安全基準(構造規格)に適合しなければならないとしており、これは安全性の設計を要求するものです。
- 安衛法 第28条の2(リスクアセスメント):事業者が危険性を特定し、そのリスクを低減するための措置を講じることを推奨しており、設計段階での危険性除去が最も効果的な低減策とされています。
2. 隔離の原則(人と危険源の隔離)
- ガード・囲いの設置義務:
- 安衛則 第101条:原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の危険な部分には、覆い(ガード)、囲い等を設けなければならないと具体的に義務付けています。
- 安衛則 第150条の2:産業用ロボットについて、立入禁止措置(柵などによる隔離)を講じ、その旨を見やすい箇所に表示することを義務付けています。
3. 停止の原則(危険時の機械停止)
- 緊急停止と起動防止の義務:
- 安衛則 第107条(運転停止後の措置):掃除、点検、修理等の作業を行う際には、機械の運転を停止し、誤って起動するのを防止するための措置(ロックアウトや標識の設置)を講じなければならないと義務付けています。
- 安衛則 第133条(プレス機械):プレス機械には、スライド(動く部分)を操作中に急停止させるための装置を設けなければならないとしています。
このように、「3原則」は法令の直接的な条文ではありませんが、労働安全衛生法の安全対策の考え方を集約したものであり、実際の安全対策はこの原則の優先順位(1.本質安全 2.隔離 3.停止)に従って実施することが、最も効果的で確実な労働災害防止策とされています。
関連する主な業種
労働安全衛生法による機械等による労働災害の防止に関する規定は、機械設備を使用するほぼ全ての業種に関係しますが、特に製造業が最も深く関わります。
主要な関連業種と、その中で具体的にどのような機械が対象となるかをご説明します。
1. 製造業(最も関係が深い)
製品を製造・加工するために、多種多様な機械を使用するため、関連規定の核となります。
- 具体的な機械・設備:
- 加工機械: プレス機械、シャー(切断機)、旋盤、フライス盤、研削盤、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤など)。
- 運搬・昇降設備: クレーン、フォークリフト、コンベヤ、エレベーター、ゴンドラ。
- 生産設備: 産業用ロボット、射出成形機、印刷機械、包装機械、攪拌機(ミキサー)。
- 圧力容器: ボイラー、圧力容器。
2. 建設業
建設現場では、大型の機械や建設用仮設設備を多用するため、労働災害防止が非常に重要です。
- 具体的な機械・設備:
- 建設機械: ショベルカー(油圧ショベル)、ブルドーザー、クレーン(移動式クレーン)、高所作業車。
- 揚重設備: 揚貨装置、デリック、リフト。
- 仮設設備: 足場、型枠支保工(これらは機械ではないが、機械等による災害防止と同様に安衛法の規制対象)。
3. 運輸業・物流業
物の積み下ろしや運搬、倉庫内作業で機械を使用します。
- 具体的な機械・設備:
- フォークリフト、コンベヤ、クレーン、エレベーター、トラック(荷台の昇降装置など)。
4. 農業・林業
トラクターやチェーンソーなどの機械類を安全に使用するための規定が適用されます。
- 具体的な機械・設備:
- トラクター、コンバイン、田植え機、チェーンソー、集材機。
5. その他の業種
製造・建設以外でも、以下の業種は特定の機械を使用するため関係します。
- 医療業・福祉業: 医療機器、リフト、昇降設備。
- サービス業: 食品加工機械、厨房機器(調理器具)、業務用洗浄機、エレベーター、エスカレーター。
- 清掃業: 高圧洗浄機、業務用清掃機械。
規制のポイント
労働安全衛生法は、機械を「使用する」ことによる危険だけでなく、機械の「設計、製造、輸入、設置、貸与」に関わる全ての事業者に対しても規制をかけています。
したがって、機械を作るメーカー(製造業者)や、機械をリース・レンタルする貸与業者も、労働災害防止の責任を負うことになります。
労働安全衛生法改正(2026年4月1日施行)
ボイラー、クレーンなどの特定の機械に係る検査・登録制度の適正な運用を図るための改正が行われました。
- 民間の登録機関の業務範囲拡大: ボイラーやクレーンなどの製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大します。
- 不正防止対策の強化: 登録機関や検査業者の適正な業務実施を確保するため、不正行為への対処や欠格要件が強化されます。