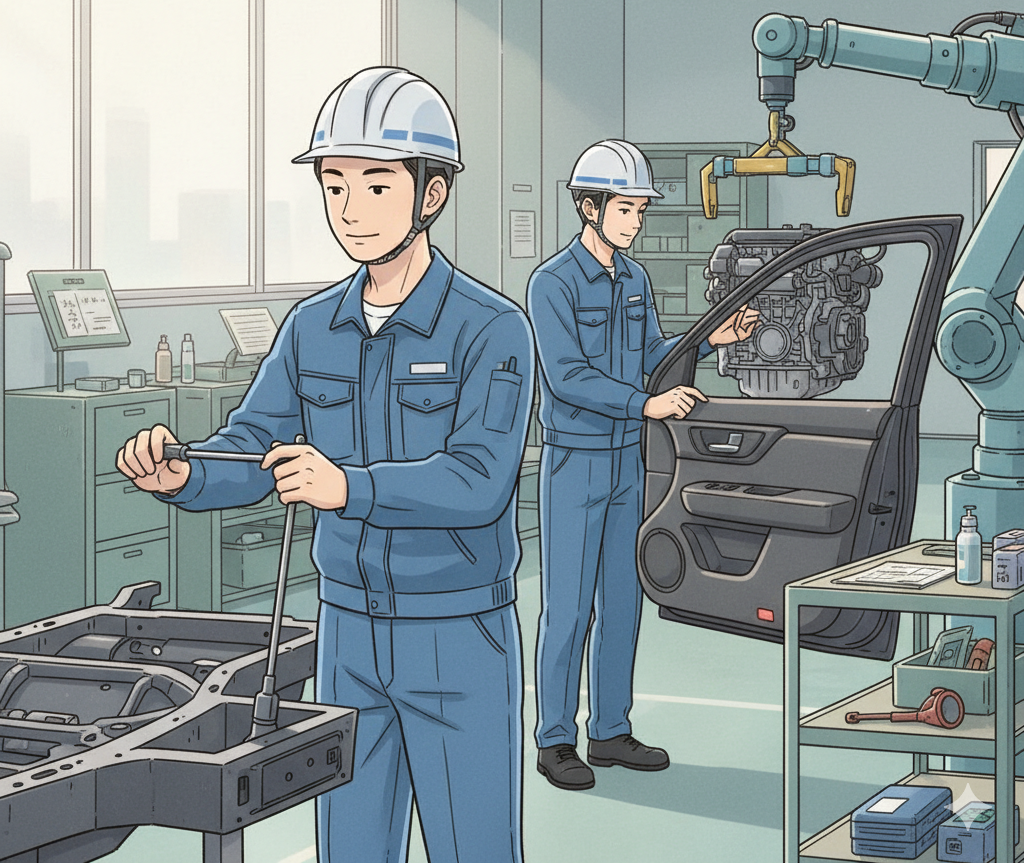安全管理者は労働安全衛生法に定められています
一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければなりません。
労働安全衛生法第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
「政令で定める業種及び規模の事業場ごとに」とあります。次の通りです。
| 業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
| 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
該当する業種
安全管理者を選任すべき業種は、主に工業系の業種と、工業系ではなくても人が多く出入りする業種です。上記の表をみて、自身の事業場がどの業種に該当するかご不明なときは、所轄の労働基準監督署に問い合わせた方がよいでしょう。
該当する規模
安全管理者を選任すべき労働者数は50人以上です。選任すべき業種に該当し、かつ、常時使用する労働者数が50人以上の場合に安全管理者を選任しなければなりません。
事業場とは
事業場」とは、同一の住所で、独立して業務を行っている場所を指します。つまり、「会社」という単位ではなく「支店、営業所、工場などの一つ一つが事業場です。
製造業で、工場が何か所かに設置されていれば、本社に一人ということではなく、50人以上の工場ごとに安全管理者が必要になります。
なお、安全管理者は、原則として「専属」であることが求められています。専属というのは、その事業場に属している(勤務している)人という意味です。同じ会社であっても、本社にいる人が別の工場の安全管理者になったり、一つの工場に勤務している人が別の工場の安全管理者になることはできません。
カッコ書きの意味
労働安全衛生法第11条に、カッコ書きの部分があります。「第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。」
つまり、第25条の2により技術的事項を管理する者を選任した場合は、安全管理者の業務はその範囲が除かれます。
第25条の2は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者の「救護」についての規定です。
その第2項では、「前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。」と定めています。救護に関する技術的事項を管理する者の資格は、労働安全衛生規則第24条の8に定められています。
専任の安全管理者を選任すべき場合
安全管理者は通常他の仕事を兼任することができます。ただし、300人以上の大人数の事業場になれば安全管理者は「専任」であることが求められます。業種別に次の規模が該当します。
| 業 種 | 事業場の規模(常時使用する労働者数) |
| 建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 | 300人 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人 |
| 上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) | 2,000人 |
安全管理者については、一定の規模になれば「専任」を求める規定がありますが、事業場の規模が何人になったら安全管理者を増やしなさいという規定がありません。衛生管理者と違うところです。ただし、事業規模や作業内容等の実態において必要に応じて複数の安全管理者を選任するが一般的です。
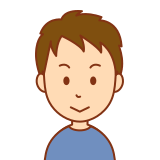
ここで用語の意味を確認しておきます。
選任というのは「ある人を選んでその役割を任せる」という用語です。つまり従業員の中から安全管理者を選ぶという意味です。
専属というのは、「その場所に専(もっぱ)ら属している」という用語です。つまり、該当する事業場にのみ勤務しているという意味です。
専任というのは、「専ら任(まか)せられている」という用語ですが、この用語には一つの仕事のみを受け持つという意味があります。勤務時間の全部を安全管理者として働く場合に専任となります。
安全管理者の業務
安全管理者の業務は「前条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項の管理」と定められています。
前条第一項各号の業務とは、総括安全衛生管理者が行う業務で、次のようになっています。
(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
安全管理者は、上のうち、安全に係る技術的事項を管理します。
安全に関する技術的事項
安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。
1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
3. 作業の安全についての教育および訓練
4. 発生した災害原因の調査および対策の検討
5. 消防および避難の訓練
6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置
作業場の巡視
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
安全管理者の巡視頻度は法律上に示されていませんが、一般的には衛生管理者の週1回に準じて行うべきだとされています。
安全管理者の権限
労働安全衛生規則第6条2に「事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない」という定めがあります。
権限を与えられない名ばかり管理者では職場の安全を保つことができないからです。
安全管理者の資格
安全管理者は、安全管理者になる資格を持つもののなかから任命しなければなりません。資格は実務経験と研修で取得します。
厚生労働大臣の定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
1.大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
2.高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
3.その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
研修は、各地の労働基準協会等が随時開催しています。
労働安全コンサルタントの資格を持つものは上記の要件は不要です。
(労働安全衛生規則第5条)
選任の手続き
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。選任後は、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
選任してから14日以内ではありません。選任すべき事由、例えば、常時使用する労働者数が50人になったときから14日以内に選任が必要です。労働基準監督署への届け出は選任後に「遅滞なく」です。
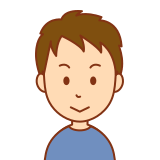
「遅滞なく」というのは、文字通り「遅れないで」という意味ですが、法律で用いられるときは、一番スピードが求められるのが「直ちに」、次が「速やかに」、その次が「遅滞なく」です。「遅滞なく」は、合理的な理由があれば遅れてもいいけれどなるべく早く、と解されていますが、当然ながら制限なく遅れてよいものではありません。可能であれば「直ちに」提出するのが無難です。
安全管理者の選任報告は、令和7年1月1日より電子申請による提出が義務づけられています。
なお、増員や解任について労働基準監督署長から命じられることもあります。
労働安全衛生法第11条2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。