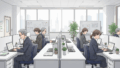日本とアメリカの違い
日本のインターンシップとアメリカのインターンシップには、主に以下の3つの違いがあります。
1. インターンシップの目的
- 日本: 学生が就職活動を始める前の「企業や業界理解」「自己分析」「就職の予行練習」を目的としたものが主流です。特に短期インターンは、採用選考の練習や企業との接点を作る場と位置づけられることが多く、必ずしも実務経験を積むことが目的ではありません。
- アメリカ: 学生が専門的なスキルを身につけ、実務経験を積むことを目的としています。インターンシップでの実績や経験は、卒業後の就職活動において重要な評価項目となり、そのまま本採用につながるケースも珍しくありません。
2. インターンシップの期間
- 日本: 1日から数日間の「短期インターンシップ」が主流です。特に1日完結型のものは「1dayインターンシップ」と呼ばれ、企業説明会やグループワークが中心となります。長期インターンシップも存在しますが、アメリカに比べると一般的ではありません。
- アメリカ: 数ヶ月から1年間にわたる「長期インターンシップ」が一般的です。夏休み期間などを利用して、実務に深く関わるプログラムが多く、社員と同様の業務を任されることもあります。
3. 給与
- 日本: 短期インターンシップは無給であることがほとんどです。交通費や昼食代が支給されることはありますが、業務に対する給与は発生しないケースが多いです。長期インターンシップでは、有給のものが増えています。
- アメリカ: 有給のインターンシップが主流です。特に専門的な分野や長期のインターンシップでは、給与が支払われることが一般的で、学生は収入を得ながらキャリアを形成することができます。
映画「マイ・インターン」の世界
映画「マイ・インターン」で描かれた高齢者インターンシップは、フィクションの世界だけでなく、現実にも存在します。特に、近年では「シニアインターン」という形で、高齢者を対象としたインターンシップが実施されるケースが増えています。
シニアインターンシップが広がる背景
高齢者インターンシップは、主に以下の理由から注目されています。
- 高齢化時代の働き方: 寿命が延び、定年後も長く働きたいと考える人が増えています。シニアインターンは、そうした人々が再就職やキャリアチェンジを検討する上で、実際の業務内容や職場の雰囲気を知るための重要な機会となります。
- 労働力不足の解消: 少子高齢化が進み、特に専門的なスキルを持つ人材が不足している企業にとって、シニアインターンは、経験豊富な人材を確保するための有効な手段となります。
- 多様性の確保: 企業側にとっては、長年の社会経験や専門知識を持つ高齢者を受け入れることで、若手にはない視点やアイデアを取り入れ、組織の活性化を図るというメリットがあります。
高齢者インターンシップの事例
「マイ・インターン」のように、退職したシニア層を対象にしたインターンシップは、特にアメリカや日本の一部の企業で見られます。
- アメリカ
- テック企業などでは、シニア向けの再教育プログラムの一環としてインターンシップが提供されることがあります。これは、高齢者が最新のスキルやテクノロジーを習得し、再び労働市場に戻ることを支援する目的があります。
- 映画「マイ・インターン」のモデルになったと言われる企業でも、同様のプログラムが存在すると言われています。
- 日本
- 介護や福祉業界など、深刻な人材不足を抱える業界でシニア向けインターンシップが導入されています。
- 地方自治体が主体となり、高齢者の就労を促進するためのインターンシッププログラムを実施するケースもあります。
ただし、学生向けの一般的なインターンシップに比べると、高齢者向けのプログラムはまだ数が限られており、特定の企業や業界に限定されているのが現状です。それでも、働く意欲のある高齢者が増えているため、今後もシニアインターンシップの機会は増えていくと考えられます。
映画「The Internship」の世界
映画「The Internship」で描かれたように、学生ではない人がインターンとして企業に入るケースは、アメリカでは現実にも見られ、近年ではその種類が増えています。ただし、学生向けインターンシップとは目的やプログラム内容が異なります。
1. リターンシップ(Returnship)
映画の主人公たちのように、一度キャリアを中断した人が職場復帰を目指すためのインターンシップです。
企業は、このプログラムを通じて、豊富な社会経験や専門スキルを持つ優秀な人材を発掘し、正社員としての採用につなげることを目的としています。
2. キャリアチェンジ・インターンシップ
全く異なる業界や職種への転職を希望する人を対象としたインターンシップです。映画の主人公たちは時計の営業マンでしたが、IT企業へのキャリアチェンジを目指しました。こうしたプログラムは、転職希望者が未経験の分野で実務経験を積み、その適性を見極めるために利用されます。
3. ポストグラデュエート・インターンシップ(Post-graduate Internship)
大学を卒業したばかりの学生を対象としたインターンシップです。これは、卒業後の就職活動を有利に進めるため、あるいは特定の職種での経験を積むために利用されます。日本の「第二新卒」に近い位置づけですが、アメリカではよりインターンシップという形式が一般的です。
4.なぜ学生ではない人がインターンをするのか?
これは、アメリカのインターンシップが単なる「就職活動の予行練習」ではなく、「実際のスキルと経験を積むための場」という明確な目的を持っているからです。
企業側も、学生だけでなく、多様なバックグラウンドを持つ人材をインターンとして受け入れることで、組織の活性化や新たなアイデアの創出を期待しています。
したがって、映画で描かれたケースは、現実にも存在する「特定の目的を持ったインターンシップ」の一例と言えます。通常の学生向けインターンシップほど一般的ではないものの、キャリアの多様化が進む現代アメリカでは、このようなインターンシップの機会は増加傾向にあります。