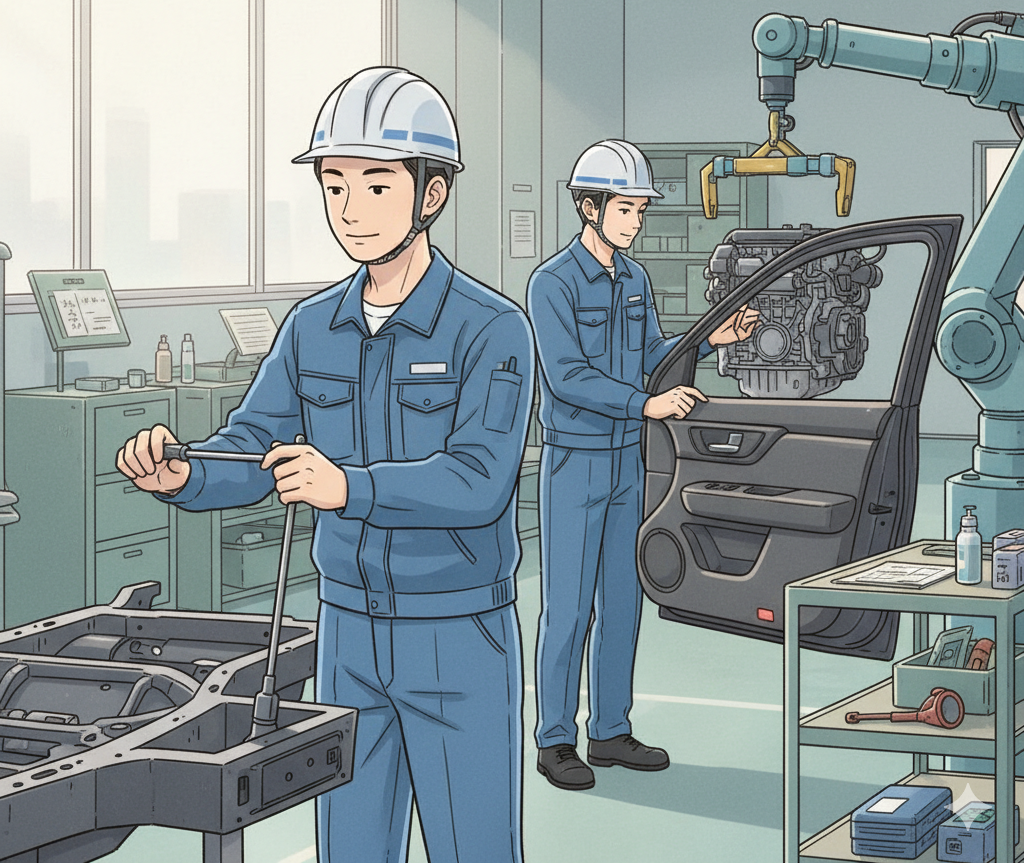事前準備
安全衛生計画の作成にあたっては、まず職場の「危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)」を行い、その結果に基づいて対策を盛り込むことが重要です。
厚生労働省の指針に基いたリスクアセスメントの進め方を紹介します。
実施体制の確立
- 経営トップの決意表明: 経営層が率先して取り組む姿勢を示す。
- 実施責任者・推進メンバーの選任: 現場をよく知る職長や作業者を必ず含め、知識を持つ者(安全管理者、衛生管理者など)でチームを編成します。
- 対象範囲の決定: 最初に全作業を対象とするのが理想ですが、困難な場合は、死亡災害や重大災害につながるリスクの高い作業や、新規・変更作業から優先的に実施します。
情報の入手
リスクを特定するための情報を集めます。
- 作業手順書・マニュアル
- 機械設備の仕様書・取扱説明書
- 過去の労働災害、ヒヤリ・ハット事例
- 化学物質等安全データシート(SDS)
- 作業環境測定結果
リスクアセスメントの4ステップ
ステップ1:危険性又は有害性の特定(ハザードの特定)
職場にある「負傷や疾病の原因となり得るもの(危険源・ハザード)」を洗い出します。
- 着眼点:
- 機械・設備: 挟まれ、巻き込まれ、感電、爆発の危険はないか。
- 作業: 転倒、墜落、無理な姿勢(腰痛)、熱中症、騒音、有害化学物質のばく露はないか。
- 環境: 整理整頓はされているか、非常時の避難経路は確保されているか。
- 特定方法:
- 作業の観察: 実際に作業している様子を観察し、危険な動きや状態を記録します。
- チェックリスト: あらかじめ用意されたチェックリストを使用して、漏れなく確認します。
- 危険性又は有害性から災害に至るプロセスを記述: 「〇〇(危険源)があるので、〇〇(現象)して、〇〇(災害)になるおそれがある」という形で明確にします。
- 例: 「プレス機に防護柵がない(危険源)ので、作業中に手が可動部に接触(現象)し、手指を切断(災害)するおそれがある。」
ステップ2:リスクの見積もりと評価
特定したハザードについて、リスクの大きさを見積もり、対策の優先度を決定します。
リスクの見積もり
リスクの大きさは、次の2つの要素を組み合わせて数値化します。
- 負傷又は疾病の重篤度(重さ): 発生した場合の被害の程度(例:死亡、休業1か月以上、軽傷)
- 発生の可能性の度合い(頻度): 災害が発生する確率や、危険な状態に人が近づく頻度(例:ほとんど起こらない、年に数回、毎日)
これらの組み合わせを「マトリックス表」や「加算式」で数値化し、リスクレベルを決定します。高い数値ほどリスクが大きいと評価します。
- (例:重篤度 3 × 発生可能性 3 = リスク点数 9)
リスクの評価
見積もったリスクレベルが、事業場で「許容できるレベル」にあるかどうかを判断し、リスク低減措置が必要なもの(優先度が高いもの)を決定します。
ステップ3:リスク低減措置の検討と決定
評価の結果、リスクが高いと判断されたものについて、リスクを減らすための具体的な対策を検討し、決定します。対策には優先順位があります。
1位 本質的対策(除去・変更):
危険な作業を廃止する、有害性の低い物質に代替する、より安全な機械に変更する。
2位 工学的対策(設備による対策):
機械に安全カバーやインターロック(安全装置)を設置する、局所排気装置を設置する。
3位 管理的対策(ルール・教育による対策):
安全作業手順書の作成・徹底、立入禁止措置、作業主任者の選任、安全教育の実施。
4位 個人用保護具の使用:
安全帯、保護メガネ、防塵マスク、安全靴を着用させる。
- 重要: 必ず1位から順番に検討し、1位でリスクを許容レベルまで下げられない場合に、2位、3位…と進めます。安易に個人用保護具(4位)で終わらせてはいけません。
ステップ4:リスク低減措置の実施と記録
決定したリスク低減措置を安全衛生計画に盛り込み、実行します。
- 実施と記録: 対策を実施したら、その実施日、責任者、効果を記録します。
- 残留リスクの評価: 対策実施後、残されたリスク(残留リスク)が許容できるレベルになっているか再度見積もり、問題がなければ作業者に周知し、作業を開始します。
- 見直し: 設備や作業方法が変更されたときや、労働災害やヒヤリ・ハットが発生したときは、その都度リスクアセスメントを見直します。また、定期的な見直しも重要です。
人材の養成
社内にリスクアセスメントを主導できる専門人材がいない場合、外部の専門家を活用しつつ、並行して、社内人材の育成を進めます。
外部専門家の活用
リスクアセスメントの仕組みを導入し、軌道に乗せるために、初期段階では外部の専門家の力を借りるのが最も確実な方法です。
専門家の種類と活用方法
労働安全コンサルタント / 労働衛生コンサルタント:
労働安全衛生法に基づく国家資格者で、職場診断や改善指導のプロです。リスクアセスメントの全体設計、具体的な実施指導、低減措置の技術的な助言を得ます。
中小企業等安全衛生対策支援事業:
独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)が実施している、中小企業向けの支援事業です。コンサルタントの費用の一部助成や、無料の専門家派遣を受けられる場合があります。
業界団体のサポート:
所属する業界団体が、リスクアセスメント導入のための研修会やひな形を提供している場合があります。
外部専門家に依頼する際は、単に作業を代行してもらうだけでなく、「自社の社員が将来的に自力でできるようになるための指導」をお願いすることが重要です。
社内人材の育成
外部の支援を受けつつ、将来的に自社で継続的にリスクアセスメントを実施できるよう、社員のスキルアップを進める必要があります。
研修と教育の実施
- リスクアセスメント研修の受講:
- 独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)の各センターや、民間の安全衛生関連団体が実施している、リスクアセスメントの実務研修に、現場の管理者(職長など)や推進メンバーを参加させます。
- eラーニングや動画教材を活用し、基礎知識を習得させます。
- 安全衛生推進者等の選任:
- 安全衛生推進者(常時10人以上50人未満の事業場)、安全管理者(業種・規模による)などを法令に基づき選任し、その方に重点的にリスクアセスメントの知識を習得させます。
職場の「安全衛生委員会」の活用
- 委員会メンバーの知識強化: 委員会のメンバー(特に安全管理者や衛生管理者)が、リスクアセスメントの基本的な考え方を理解し、調査審議ができるよう教育します。
- 専門家との連携窓口: 外部専門家が指導に入った際、委員会メンバーが中心となって連携し、知識やノウハウを吸収します。
実施方法の工夫
経験が浅いメンバーでも実行しやすいよう、リスクアセスメントの方法を工夫することも有効です。
- 簡便な手法の採用: 最初から複雑な評価手法を用いるのではなく、「はい/いいえ」で答えられるチェックリスト方式や、ハザードマップの作成など、特定に重点を置いた簡便な手法から始めます。
- 特定作業の絞り込み: 過去に事故が発生した作業や、新規導入した機械設備など、危険性が明確な特定の作業にまず対象を絞り込み、小規模な成功体験を積ませます。
- 記録のテンプレート化: 実施様式や記録のひな形(テンプレート)を用意し、担当者が迷わず記入できるようにすることで、スムーズな運用を促します。
これらのステップを踏むことで、専門人材がいない状況からでも、着実にリスクアセスメントを導入し、継続的に安全衛生活動を推進できる体制を構築できます。