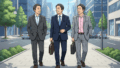従業員の方が70歳に到達した際の社会保険(厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険)の手続きについて解説します。主に厚生年金保険で特別な手続きが必要となります。健康保険と労働保険(雇用保険・労災保険)は、75歳になるまでは大きな変更なく継続します。
厚生年金保険の手続き(70歳到達日)
資格喪失
従業員が70歳に達すると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、「70歳以上被用者」となります。厚生年金保険料の徴収は70歳到達日を含む月から不要となりますが、在職老齢年金の調整対象となるため、届出が必要です。
| 届出が必要なケース | 必要な届出書類 | 提出先・期限 |
| 【原則として届出不要】 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合。 | 日本年金機構が資格喪失と70歳以上被用者該当処理を行うため、事業主からの届出は不要。 | – |
| 【届出が必要】 70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる場合(例:再雇用に伴い報酬が変動した場合)。 | 「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 / 70歳以上被用者該当届」(一体の様式) | 管轄の年金事務所 資格喪失日(70歳の誕生日の前日)から5日以内 |
- 届出用紙:届出が必要な従業員については、70歳に到達する月の前月に日本年金機構から事業所宛てに事前送付されます。
- 留意事項:
- 70歳到達日以降も、標準報酬月額の算定(定時決定、随時改定、賞与支払届)は引き続き行い、「70歳以上被用者算定基礎届」や「70歳以上被用者月額変更届」などを提出する必要があります。
高齢任意加入
上述したように70歳になれば厚生年金保険の加入資格を失いますが、その時点で老齢の年金を受けられる加入期間(10年以上)を満たしていない人については、70歳を過ぎても会社に勤めていて、厚生年金保険への加入について事業主の同意があり(同意がなければ全額負担)、厚生労働大臣の認可を得た場合に、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
条件を満たした場合は、従業員本人が実施機関(年金事務所)に「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出し、その申し出が受理された日に資格を取得します。
健康保険の手続き(70歳〜75歳未満)
健康保険は、原則として75歳になるまで被保険者資格が継続します。
70歳になったときは、高齢受給者証が交付されます。高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」は、原則として2割または3割のいずれかです。この割合は、主に所得や収入の状況によって判定されます。
70歳の誕生月の下旬、健康保険高齢受給者証が交付されます。事業主宛に送付されてくるので該当する従業員に渡します。会社がする手続きはありません。
対象者
- 70歳から74歳までの健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)の加入者(被保険者および被扶養者)。
- 75歳になると、後期高齢者医療制度へ移行するため、高齢受給者証は使えなくなります。
交付時期と有効期限
- 交付時期:70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が月の初日、つまり1日の場合はその月1日)から使用開始となるため、その前に交付されます。
- 有効期限:原則として毎年7月31日までです。毎年8月に前年中の所得に基づいて負担割合が見直され、新しい証が交付されます。ただし、75歳になる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなります。
使い方(医療機関での提示)
- 医療機関の窓口で、通常の健康保険証(または資格確認書)と合わせて提示する必要があります。
- この証を提示しないと、たとえ負担割合が2割であっても、原則の3割負担を求められる場合があるため注意が必要です。
注: マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)している場合は、この証の情報も一体化されるため、原則として高齢受給者証の提示は不要です。
労働保険の手続き(雇用保険・労災保険)
雇用保険
- 2017年1月1日以降、雇用保険の適用に年齢の上限が事実上撤廃されており、70歳以降も引き続き高年齢被保険者として加入が継続します。
- 継続して雇用している場合は、特別な手続きは不要です。
労災保険
- 労災保険には年齢制限がないため、特別な手続きは不要です。
手続きは法改正により変更になることがあります。提出書類の様式や提出方法の詳細は、必ず管轄の日本年金機構またはハローワークにご確認ください。