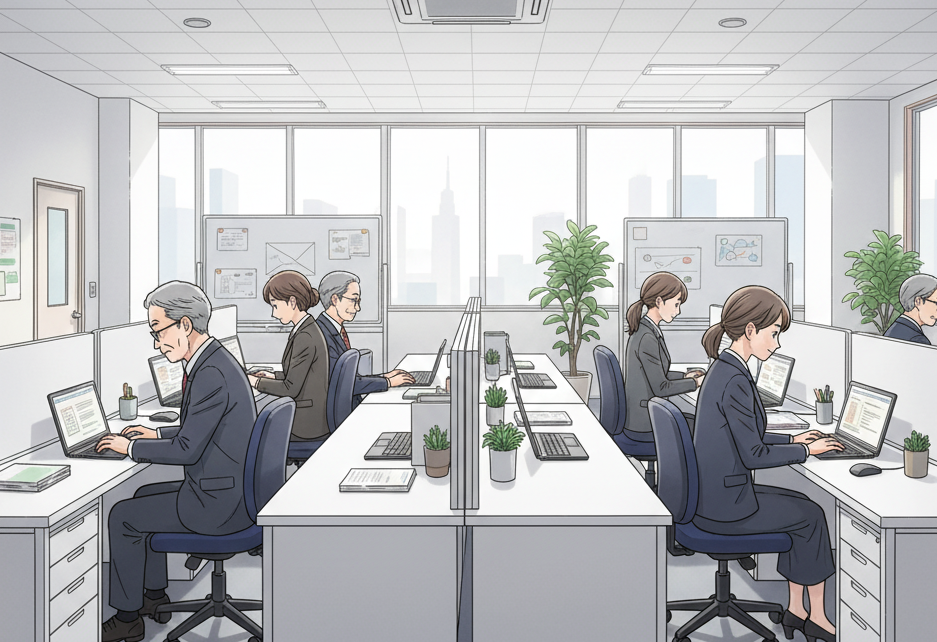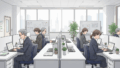「障害者雇用推進者」と「障害者職業生活相談員」は、どちらも企業内で障害者の雇用をサポートする役割ですが、担う職務と選任の義務・努力義務の点で違いがあります。
障害者雇用推進者
障害者雇用推進者は、主に企業の経営や雇用管理の視点から、障害者雇用に関する社内の体制づくりや計画の推進を担う人です。
| 項目 | 詳細 |
| 選任の義務 | 努力義務(義務ではないが、努めることが求められる) |
| 選任の対象 | 常用労働者数が40人以上の事業主(努力義務の対象) |
| 主な役割 | 障害者の雇用の促進及び継続を図るための体制整備や計画推進が中心です。具体的な業務は以下の通りです。 1. 施設・設備の設置、改善、環境整備に関すること。 2. 障害者の雇用状況の報告や解雇の届出などの各種届出に関すること。 3. 国からの雇入れ計画作成の命令・勧告を受けた際の連絡・対応に関すること。 4. 合理的配慮を提供するための環境整備に関すること。 |
| 位置づけ | 障害者雇用を進めるための窓口・責任者としての役割が期待されます。 |
障害者職業生活相談員
障害者職業生活相談員は、主に現場で働く障害者の職業生活全般に関する具体的な相談・指導を担う専門的な役割です。
| 項目 | 詳細 |
| 選任の義務 | 義務(法律により選任が義務付けられている) |
| 選任の対象 | 障害者である常用労働者を5人以上雇用する事業所 |
| 資格要件 | 厚生労働大臣が定める資格認定講習を修了した者、またはそれに相当する実務経験や学歴を有する者から選任しなければなりません。 |
| 主な役割 | 職業生活全般の相談・指導が中心です。 1. 職務内容:適性・能力に応じた職務の選定、職業能力の向上に関すること。 2. 作業環境:障害に応じた施設・設備の改善など、作業環境の整備に関すること 3. 職場生活:労働条件、職場の人間関係、生活面(余暇活動など)に関する相談・指導。 |
| 位置づけ | 現場の障害者に寄り添い、定着を支援する専門家としての役割が期待されます。 |
役割の主な違い(まとめ)
| 項目 | 障害者雇用推進者 | 障害者職業生活相談員 |
| 法的義務 | 努力義務 | 義務(障害者5人以上雇用で) |
| 主な職務 | 体制・計画の整備、行政への届出、合理的配慮の環境整備など経営・管理面 | 個別の相談・指導、職務内容の選定、職場・生活環境のサポートなど現場・専門面 |
| 資格 | 特段の資格要件なし | 厚生労働大臣が定める資格認定講習の修了などが必要 |
まとめて言えば、障害者雇用推進者は「会社として障害者雇用をどう進めるか」という体制と計画の責任者であり、障害者職業生活相談員は「雇用した障害者一人ひとりがどう働けるか」を現場でサポートする専門家といえます。
選任の届け出
「障害者雇用推進者」と「障害者職業生活相談員」の届け出先は、いずれも基本的に事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)になりますが、手続きの方法が異なります。
障害者雇用推進者
障害者雇用推進者については、個別の選任届を提出する義務はありません。
選任状況の報告は、毎年企業に提出が義務付けられている「障害者雇用状況報告書」(通称:ロクイチ報告)の中で行います。
- 届け出のタイミングと方法:
- 毎年6月1日現在の状況を報告する「障害者雇用状況報告書」の様式内に、選任している推進者の氏名や役職を記入することで報告が完了します。
- この報告書は、毎年7月15日までに、本社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
障害者職業生活相談員
障害者職業生活相談員については、選任した場合に個別の「選任報告書」を提出する義務があります。
- 提出する書類:
- 「障害者職業生活相談員選任報告書」
- 届け出のタイミング:
- 選任すべき理由が発生した日から3か月以内に選任し、速やかに報告書を提出します。
- 届け出先(民間企業の場合):
- 当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
補足
- どちらの届け出・報告も、現在は電子申請(e-Govなど)を利用して行うことができます。
- 手続きや様式の詳細について不明点がある場合は、事業所の所在地を管轄するハローワークに問い合わせてください。