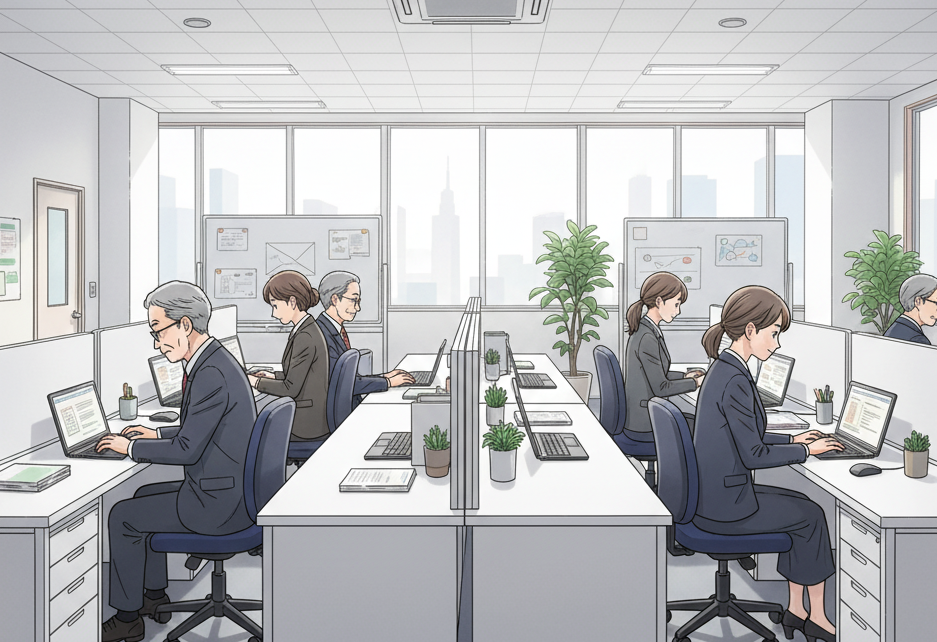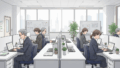障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務は、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」の柱となる考え方です。これらは、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を実現するために、行政機関や事業者(民間企業など)に求められる基本的な対応です。
不当な差別的取扱いの禁止
これは、障害者に対して「正当な理由なく」、障害を理由として、健常者と異なる不利益な取り扱いをすることを一律に禁止するものです。
具体的な禁止行為の例
- 拒否・排除:
- 障害があることを理由に、店舗や施設の利用を拒否すること。
- 雇用において、障害があることのみを理由に採用を拒否すること(雇用分野は「障害者雇用促進法」でも禁止)。
- 制限・条件の付与:
- サービス提供の際に、障害のない人には求めない介助者の同伴を必須の条件とすること。
- 窓口対応の順番を、障害者であることのみを理由に後回しにすること。
- 例外として禁止されない場合:
- 合理的な配慮を提供した結果として、異なる取り扱いとなる場合(例:障害の特性に合わせて別の職務に配置すること)。
- 正当な理由(例えば、施設の構造上、安全確保が不可能であるなど)がある場合。
合理的配慮の提供義務
これは、障害のある人から、社会の「障壁」(バリア)を取り除くために何らかの対応を必要としている旨の「意思の表明」があった際に、「過重な負担にならない範囲で」対応を行うことを義務付けるものです。
合理的配慮の考え方
- 目的: 障害のある人が、障害のない人と同等の機会を得て、活動できるように環境を調整することです。「特別扱い」ではなく、公平な機会の提供を目的とします。
- プロセス: 配慮の提供は、障害者本人からの「申出」をきっかけに、事業者と障害者との間で「建設的な対話」を通じて、個別の状況に応じた最適な解決策を一緒に見つけることが重要です。
- 範囲の限界: 事業者にとって「過重な負担」となる場合は、配慮の提供義務は及びません。ただし、その場合は、理由を説明し、代替案となる他の可能な配慮を提案する必要があります。
合理的配慮の具体例
| 種類 | 障害の例 | 具体的な配慮の例 |
| 物理的環境 | 肢体不自由(車いす) | 段差に携帯スロープを渡す、通路の障害物を除去する。 |
| 意思疎通 | 聴覚障害、言語障害 | 筆談、手話通訳者の手配、分かりやすい資料や図の活用。 |
| ルール・慣行の変更 | 精神障害、発達障害 | 休憩時間の回数を増やす、通院のための勤務時間や休暇を柔軟に調整する。 |
| 情報提供 | 視覚障害 | 書類を読み上げる、点字や拡大文字で情報を提供する。 |
差別禁止と合理的配慮の関係
この二つは、車の両輪のような関係にあります。
- 不当な差別的取扱いの禁止(ネガティブ・アプローチ): 障害を理由としたマイナスの行為(不利益な扱い)をしてはいけないというルールです。
- 合理的配慮の提供義務(ポジティブ・アプローチ): 障害を理由としたバリアを解消するために、必要な行為(環境調整)をしなければならないというルールです。
事業者は、この二つの義務を果たすことによって、障害のある人々の社会参加を促進することが求められています。