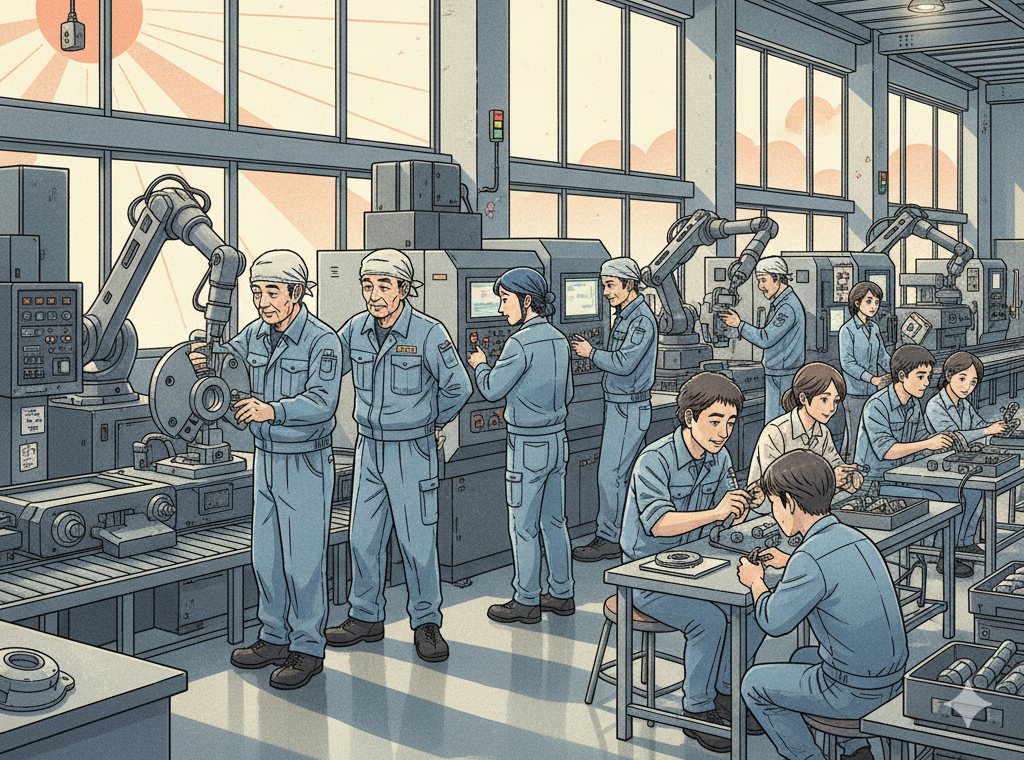雇用保険に関するよくある質問
退職者の皆様へ
このFAQは、ご退職される皆様が、雇用保険の基本や失業給付(基本手当)の受給についてご理解を深めていただくためのものです。ご不明な点がございましたら、ハローワーク、または会社の人事担当者までお気軽にお問い合わせください。
Q1. 雇用保険とは何ですか?
A1. 雇用保険は、働く皆さんが失業した場合や育児・介護などで休業した場合に、生活の安定と就職促進のために必要な給付を行う国の社会保険制度です。会社に勤めている間は、原則として給与から雇用保険料が天引きされています。
Q2. 雇用保険に加入していたか、どうすれば確認できますか?
A2. 給与明細をご確認ください。「雇用保険料」の項目で保険料が天引きされていれば加入しています。また、会社から交付される「雇用保険被保険者証」でも確認できます。もしご不明な場合は、人事担当者にお問い合わせください。
Q3. 失業給付(基本手当)とは何ですか?
A3. 失業給付(基本手当)は、雇用保険の被保険者であった方が、離職後に働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事が見つからない場合に、生活の安定を図りながら再就職活動ができるよう支給される手当です。
【基本手当の計算方法(概算)】
基本手当の1日あたりの金額(基本手当日額)は、原則として離職前の賃金に基づいて計算されます。
賃金日額の算出: 原則として、離職前6ヶ月間の賃金(賞与等を除く)の合計額を180で割った金額が「賃金日額」となります。
賃金に含まれるもの: 基本給、各種手当(通勤手当、残業手当、扶養手当など、毎月支払われるもの)
賃金に含まれないもの: 賞与(ボーナス)、退職金、結婚祝い金などの臨時に支払われるもの
基本手当日額の算出: 賃金日額に一定の給付率をかけたものが基本手当日額となります。給付率は離職時の年齢や賃金日額によって異なり、約50%~80%です。賃金が低い方ほど給付率は高く、賃金が高い方ほど給付率は低くなります。 また、基本手当日額には上限額と下限額が定められています。
計算式(概算):
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50%~80%)
具体的な金額は、ハローワークで受給資格の決定を受ける際に示されます。
Q4. 失業給付(基本手当)を受給するための条件は何ですか?
A4. 主な条件は以下の通りです。
雇用保険の加入期間(被保険者期間):
自己都合退職など(一般受給資格者)の場合: 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
会社都合退職など(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合: 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。 ※「被保険者期間」とは、雇用保険の加入期間のうち、賃金の支払いがあった日数が11日以上または労働時間が80時間以上の月を1ヶ月とカウントします。
働く意思と能力があること: 病気や怪我で働けない状態ではないこと。
積極的に求職活動を行っていること: ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、再就職のための活動をしていること。
離職していること: 現在、仕事をしていないこと。
Q5. 自己都合退職と会社都合退職で、失業給付の条件や受給期間は変わりますか?
A5. はい、大きく変わります。
自己都合退職の場合:
受給要件が厳しくなることがあります(Q4参照)。
2025年4月1日以降の離職の場合、原則として給付制限期間は1ヶ月となります。 ただし、過去5年間に正当な理由なく自己都合退職により失業給付の受給資格決定を2回以上受けている場合は、給付制限期間が3ヶ月となる場合があります。
また、離職期間中や離職日以前1年以内に、ご自身で雇用保険の教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した場合は、給付制限が解除されます(2025年4月1日施行)。
会社都合退職(特定受給資格者)の場合:
受給要件が緩和されることがあります(Q4参照)。
給付制限期間がありません。
所定給付日数(失業給付がもらえる日数)が、自己都合退職の場合よりも長くなる傾向があります。
「会社都合」とされるのは、倒産、解雇、事業所の移転による通勤困難など、ご自身の意思に反して離職せざるを得なかった場合が該当します。具体的な判断はハローワークが行います。
Q6. 会社からどんな書類をもらえますか?
A6. 雇用保険の手続きに必要な書類として、主に以下のものが交付されます。
雇用保険離職票-1: 雇用保険の資格喪失を証明する書類です。
雇用保険離職票-2: 離職理由や賃金などが記載された書類です。
雇用保険被保険者証: 雇用保険に加入していたことを証明するものです。
源泉徴収票: 退職後の確定申告や年末調整で必要になります。 これらの書類は、退職後10日~2週間程度で郵送されます。ハローワークでの手続きに必要ですので、大切に保管してください。
Q7. 失業給付の申請はどこで、いつまでにすればいいですか?
A7.
申請場所: ご自身の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
申請期限: 離職日の翌日から1年以内です。この期間を過ぎると、原則として失業給付は受けられなくなります。
病気や怪我、妊娠・出産、育児など、やむを得ない理由で30日以上引き続き求職活動ができない場合は、受給期間の延長が認められる場合があります。この場合は、離職日の翌日から1ヶ月以内に延長手続きが必要です。
Q8. 失業給付の受給までの流れを教えてください。
A8. 主な流れは以下の通りです。
会社からの書類受け取り: 雇用保険離職票などを受け取ります。
ハローワークでの求職申込み・受給資格の決定: 離職票などを持参し、ハローワークで求職の申込みと失業給付の申請を行います。
待期期間: 求職の申込みをした日(または受給資格決定日)から7日間は、失業給付が支給されない「待期期間」となります。
給付制限期間(自己都合の場合のみ): 待期期間満了後、自己都合退職の場合は給付制限期間があります。(2025年4月1日以降の離職者は原則1ヶ月。教育訓練受講による解除あり。 詳細はQ5を参照ください。)
雇用保険説明会への参加: ハローワークが指定する説明会に参加します。
失業の認定: 4週間に一度、ハローワークに行き、求職活動の実績を報告し、「失業の認定」を受けます。
失業給付の支給: 失業認定後、指定口座に失業給付が振り込まれます。
Q9. 失業給付を受けている間にアルバイトはできますか?
A9. はい、可能です。ただし、アルバイトの内容や収入によっては、失業給付が減額されたり、支給されなくなったりする場合があります。
週の労働時間が20時間未満であること
1日の労働時間が4時間未満であること
一定以上の収入がある場合は、失業給付額から収入が控除されます。 アルバイトを行う場合は、必ずハローワークに申し出て、指示に従ってください。申告を怠ると不正受給となり、厳しい罰則が科せられます。
Q10. 雇用保険に関する問い合わせ先は?
A10. 雇用保険の具体的な手続きや受給資格に関するご質問は、ご自身の住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)が窓口となります。 ハローワークの連絡先は、厚生労働省のウェブサイトなどでご確認いただけます。
【補足】
このFAQは一般的な情報提供を目的としています。個別の状況によって、手続きや条件が異なる場合がありますので、必ずハローワークにご確認ください。
本FAQの内容は、2025年4月1日施行の雇用保険法改正内容(給付制限期間に関する事項)を反映しています。 今後の法改正等により内容が変更される可能性もあります。