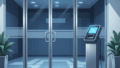メンタルヘルスケアのステップ3「復職後のフォローアップ」について、詳細に解説します。
復職後のフォローアップは、従業員が再発なく、安定して働き続けられるようにするための最終段階です。焦らず、段階的に元の働き方に戻していくことが成功の鍵となります。
定期的な面談と担当者
復職後も、従業員の体調や業務状況を確認するため、定期的な面談を継続します。
面談の担当者:
- 直属の上司(ラインケアの継続): 従業員の日常的な変化に最も早く気づく立場であり、業務状況の確認や日々の体調変化に配慮します。
- 人事担当者: 勤務時間や給与、休職制度などの事務的なサポートに加え、客観的な視点から従業員の復職状況を把握します。
- 産業医または保健師(専門家によるケア): 医学的な専門家として、心身の状態を継続的にチェックし、就業継続が可能かどうかを判断します。
面談の頻度:
復職直後は週1回、慣れてきたら2週間に1回、月に1回と、従業員の状況に合わせて頻度を徐々に減らしていきます。
面談での注意事項と会話シナリオ
面談では、従業員に安心感を与え、本音を引き出すことが重要です。
面談の注意事項:
- 個室で行う: 他の従業員に聞かれないよう、プライバシーが確保された場所で行います。
- 責めない・励まさない: 「頑張って」「早く元に戻って」といった言葉はプレッシャーになるため避けます。
- 具体的な質問をする: 「体調はどうですか?」のような漠然とした質問ではなく、「昨日はぐっすり眠れましたか?」など、答えやすい具体的な質問を心がけます。
会話シナリオの例(上司が面談する場合):
- 上司: 「〇〇さん、おはよう。今日はこの前の続きだけど、最近の体調や仕事の状況について話を聞かせてくれるかな。」(導入:安心して話せる雰囲気づくり)
- 従業員: 「はい、ありがとうございます。体調はだいぶ安定してきました。ただ、まだ少し疲れやすさを感じることがあります。」
- 上司: 「そうなんだね。何か困っていることはない?タスクの量や難易度はどうかな?」
- 従業員: 「タスクは問題ないのですが、以前より集中力が続かないと感じる時があります。休憩時間をこまめにとるようにしています。」
- 上司: 「休憩をしっかり取るのは素晴らしいことだね。何かあったら一人で抱え込まず、いつでも声をかけてほしい。必要であれば、業務量を調整することもできるからね。」(寄り添いと具体的な提案)
- 上司: 「もし、私以外に相談したいことがあれば、人事の△△さんや産業医の先生にもいつでも相談してね。私も連携してサポートしていくから。」(専門家への連携を促す)
業務内容や部署変更のプロセス
再発防止のためには、元の職場環境が不調の原因となった場合は、業務内容や部署を見直すことも必要です。
プロセス:
- 本人の意向確認: まずは、従業員本人がどのような働き方を希望しているかを丁寧にヒアリングします。
- 産業医の意見聴取: 産業医が「就業上の配慮が必要」と判断した場合、具体的な配慮内容について意見を聴取します。
- 上司・人事で検討: 産業医の意見と本人の意向を踏まえ、業務内容の変更(例:営業職から内勤職へ)、または部署異動の可能性を検討します。
- 決定と実行: 変更内容を本人に提示し、合意が得られれば実行します。
重要事項:
- 復職プランへの明記: 復職前に作成する「復職プラン」に、業務内容や勤務時間、部署変更の可能性について明記し、関係者間で共有します。
- 無理のない変更: 変更は一時的なものではなく、本人の回復と安定就労を目的としたものとします。急な変更ではなく、段階的に進めていくことが大切です。
面談窓口について
一つの窓口に絞ることは、従業員の負担を軽減する一方で、いくつかのデメリットも生じうるため、慎重な検討が必要です。複数の窓口を設置することは、役割の重複ではなく、むしろ多角的なサポート体制を築くための有効な手段となります。
一つの窓口に絞る場合のメリットとデメリット
メリット
- 従業員の迷いをなくす: 相談先が明確になり、「誰に相談すればいいのか分からない」という迷いをなくせます。
- 情報の一元管理: 相談内容が1つの窓口に集約されるため、情報共有や連携がスムーズになります。
デメリット
- 専門性の偏り: 担当者が1人(または1部署)に限定されると、対応できる専門分野が偏る可能性があります。例えば、人事担当者だけでは、医学的な判断や専門的なカウンセリングには対応できません。
- 心理的抵抗感の増加: 相談内容によっては、会社の人事担当者には話しにくいと感じる従業員もいます。プライバシーへの懸念から、相談そのものをためらってしまう可能性があります。
- 担当者への負担集中: すべての相談を1人で受け持つことになり、担当者自身の精神的・業務的負担が大きくなります。
複数の窓口を設けることの重要性
複数の窓口を設けることは、上記デメリットを補い、従業員に「選択肢」と「安心感」を提供します。
- 専門性の確保: 産業医や保健師といった専門家を窓口に加えることで、医学的な知識に基づいた的確なアドバイスが可能になります。
- 相談内容に応じた選択肢:
- 上司: 日常的な業務の悩み。
- 人事担当者: 人事評価や配置、休職に関する相談。
- 産業医・保健師: 心身の不調や健康問題に関する専門的な相談。
- プライバシー保護: 会社の人事部とは独立した、社外のEAP(従業員支援プログラム)サービスを窓口に加えることで、従業員はより安心して相談できます。
負担を軽減するためには、窓口を絞るよりも、各窓口の役割と相談内容を明確に区分けし、従業員に周知することの方が効果的です。これにより、従業員は自分の悩みに合わせて最適な相談先を迷わず選べるようになります。