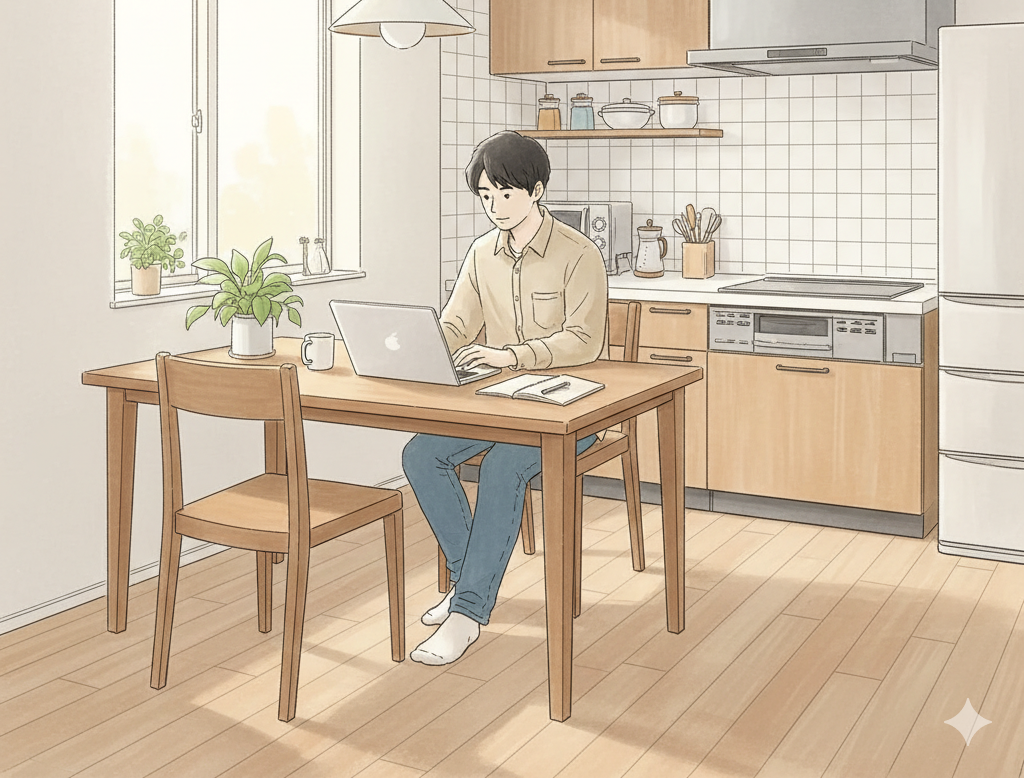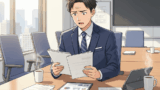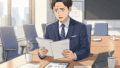「年末調整手続きの電子化」は、従業員での年末調整の負担を減らし、手続きを簡単にするための取り組みです。年末調整書類のデジタル化と提出、そして、マイナポータル連携による控除証明書等の自動取得の二つのポイントに分けて説明します。
年末調整書類のデジタル化と提出
これまで、年末調整のために「扶養控除等申告書」などの書類を手書きで書いて、それを会社に紙で提出していました。
電子化後の変化
- データで作成: 手書きではなく、パソコンやスマートフォンで必要な情報を入力してデータ(ファイル)として書類を作成できるようになります。
- データで提出: 作成したデータを、メールや会社のシステムなどを通じて会社にデータとして提出できるようになります。
これにより、記入ミスが減り、会社側も紙の管理が不要になるため、手続きがスムーズになります。
具体的な流れ
「扶養控除等申告書」などの年末調整書類をパソコンなどから入力してデータで作成する主な方法は、次の2つです。
国税庁提供の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を利用する
これは、国税庁が電子化のために無償で提供している公式ツールです。
- ソフトの種類: パソコン用(Windows/Mac)のソフトウェアと、スマートフォン用のアプリがあります。
- 入手先: 国税庁のホームページからダウンロードするか、スマートフォンの場合はApp StoreやGoogle Playストアからインストールします。
- 入力方法: ソフトを起動し、案内に従って氏名や住所、扶養家族の情報などを入力します。
- このソフト内で、先にご説明したマイナポータル連携を利用して控除証明書等のデータを自動で取り込むことができます。
- すべての入力とデータの取り込みが終わると、提出用のデータファイル(XML形式)が作成されます。
- 提出先: 作成したデータファイルを、勤務先が指定する方法で会社に提出します。
勤務先が導入している民間の年末調整システムを利用する
勤務先が、市販されている給与計算ソフトや年末調整手続きのクラウドサービスを導入している場合、そちらのシステムを利用することになります。
- 入力方法: 勤務先から提供される専用のWebサイト(URL)やアプリにアクセスし、ログインして入力します。入力画面はシステムによって異なりますが、アンケート形式で答えやすいよう工夫されているものが多いです。
- 提出先: システム内で入力・確定すれば、データがそのまま会社の人事・経理担当者に連携されます。
ポイント
- まずは勤務先に確認: あなたがどの方法(国税庁の年調ソフトか、会社の独自システムか)を利用してデータを作成・提出すればよいかは、勤務先の指示に従う必要があります。
- 対応しているか確認: そもそもあなたの勤務先が「年末調整の電子化」に対応していなければ、従来通り紙で提出することになります。
電子化に対応しているかどうか、どのソフト・サイトを使うべきかについては、必ず勤務先の人事や給与計算の担当部署にご確認ください。
給与計算ソフトの機能を利用する場合の流れ
国税庁が無料で提供する「年調ソフト」を従業員に使用させる方法もありますが、多くの企業は市販の給与計算・労務管理ソフトの機能を利用しています。給与計算ソフトが提供する機能を利用して、扶養控除等申告書等を従業員から電子申請(Web提出)で提出してもらう手順のその基本的な流れと、従業員・企業側の手順を分けて説明します。
給与担当者側
扶養控除等申告書を電子化するには、企業側で専用のソフトやシステムを導入し、環境を整える必要があります。
ステップ 1: システムの導入と設定
- 年末調整ソフト/給与計算ソフトの選定: 扶養控除等申告書の電子提出機能(Web申告機能)があるソフトを導入します。
- 従業員情報の登録: 従業員の氏名、住所、前年までの給与情報などをソフトに登録します。
- 提出環境の設定: 従業員がアクセスするためのURLやログインID、パスワードなどを設定します。
ステップ 2: 従業員への依頼と周知
- 提出依頼: 従業員に対し、電子申請を行うためのマニュアル、ログイン情報、提出期限などを通知します。
- 電子データ取得の推奨: 控除証明書(生命保険料控除、地震保険料控除など)も電子データ(XML形式など)で取得できることを周知し、取得方法(マイナポータル連携、保険会社等のWebサイト)を案内します。
ステップ 3: 提出データの回収・確認
- データ受領: 従業員からWeb上で提出された申告書データ(多くの場合、XMLファイルまたはソフト内でデータとして)を回収します。
- 内容の確認: 申告内容に不備や不明点がないか、ソフトのチェック機能などを利用して確認します。
- データ反映: 受領したデータを給与計算システムにインポートし、年末調整の計算に利用します。
従業員側
従業員は、会社の指定するソフトまたは国税庁の年調ソフトを使って申告書を作成し、提出します。
ステップ 1: システムへのログインと基本情報の確認
- アクセス: 会社から指定されたURLにアクセスし、IDとパスワードでログインします。
- 基本情報の確認: 画面に表示された氏名、住所、扶養親族などの前年の情報や会社の情報に誤りがないか確認します。
- (メリット: 前年の情報が自動表示されるため、従業員は変更点だけを入力すれば済みます。)
ステップ 2: 扶養親族等の情報の入力・修正
- 申告書の選択: 画面の案内に従って「扶養控除等申告書」を選択します。
- 変更点の入力: 前年から扶養家族に変更があった場合や、新たに扶養親族を追加する場合、その情報を入力・修正します。
- (ポイント: 画面の質問に答えていくだけで、必要な控除の判定や金額の入力が完了するように設計されていることが多いです。)
ステップ 3: 控除証明書データの取り込み(必要な場合)
- 控除証明書の準備: 生命保険料や地震保険料などの控除証明書の電子データ(XMLファイル)をPCやスマートフォンに準備します。
- データ連携/アップロード: ソフトの機能を利用して、証明書データをシステムに取り込みます(マイナポータル連携を利用すれば一括で自動取得できる場合もあります)。
ステップ 4: 申告データの提出
- 最終確認: 入力した内容の最終確認画面で、間違いがないかチェックします。
- データ送信: 「提出」ボタンなどをクリック(タップ)して、申告書データ(XMLファイルなど)を会社に送信します。
【重要事項】
- 税務署への承認申請: 企業が扶養控除等申告書を電子データで保存・提出を受けるためには、原則として所轄の税務署へ事前に「源泉徴収に関する申請書」などを提出し、承認を得る必要があります。
- ソフト依存: 従業員に依頼する具体的な画面操作や提出方法は、導入した給与計算ソフト(例:SmartHR、マネーフォワードクラウド、弥生など)によって異なります。各ソフトが提供する従業員向けマニュアルを用意することが不可欠です。
マイナポータル連携による控除証明書等の自動取得
年末調整では、生命保険料や地震保険料、住宅ローン控除などを受けるために、保険会社などから届く「控除証明書」を会社に提出する必要があります。この証明書を集めるのが面倒でした。
マイナポータル連携とは
- マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)と年末調整のシステムを連携させることです。
- あなたがマイナポータルを通じて、必要な情報を保険会社などに要求すると、それらの会社が発行した控除証明書等の情報をデータでまとめて取得できるようになります。
電子化後の変化
- 書類集めの手間が激減: 紙の控除証明書を保管したり、紛失したりする心配がなくなり、複数の控除証明書をデジタルデータとして一箇所に集めることができます。
- 申告書作成が簡単に: 取得したデータを利用して、前述の年末調整の申告書をより簡単に、正確に作成できるようになります。
つまり、年末調整の作業が「紙と手書き」から「データとオンライン」に変わり、書類作成・提出・証明書集めの全てが簡単でスピーディーになるという変化です。
具体的な流れ
マイナポータルを通じて控除証明書等のデータを取得する際、まずアクセスするのは、マイナポータルの以下の画面(またはメニュー)です。
基本的な流れとしては、マイナポータルにログインした後、「年末調整」または「確定申告の事前準備」に関するメニューから進みます。
マイナポータルで最初に入る画面:メニュー
- マイナポータルにログインする(マイナンバーカードとパスワードが必要です)
- ホーム画面から「年末調整」または「確定申告の事前準備」のメニューに進むマイナポータルには、通常、年末が近づくと「年末調整」や「確定申告」といった項目やバナーが表示されます。
- 多くのケースで、ホーム画面から「確定申告」などのメニューをタップし、表示される「証明書等の取得をはじめる」などのボタンから進みます。
- このメニューの中には、一般的に以下の3つのステップが含まれています。
- 取得したい証明書等の選択
- 外部サイト(保険会社など)との連携
- 証明書等の準備状況の確認
重要な事前準備
このマイナポータルの画面に進む前に、控除証明書等を発行する保険会社や金融機関のサイトで、「電子データでの発行」や「マイナポータル連携(民間送達サービス連携)」の手続きを済ませておく必要があります。
これは、マイナポータルが直接あなたの保険の契約情報を持っているわけではなく、保険会社などが発行した電子データをマイナポータル経由で受け取れるように設定する作業だからです。
- 保険会社・金融機関のサイトで「電子発行」の手続きを行う
- 生命保険会社や証券会社の契約者向けWebサイトにログインし、「控除証明書を電子データで受け取る」または「マイナポータル連携を申し込む」といった手続きを行います。
- この手続きの中で、多くの場合、マイナンバーカードを使った認証が必要になります。
ポイント
最終的に控除証明書のデータを「まとめて取得」できるのはマイナポータルの画面ですが、そのデータが届くようにするための「設定」は、事前に各保険会社などのサイトで行う必要があります。