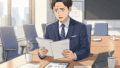懲戒処分の手続きを定めた規程のひな形を示します。
懲戒処分の手続きに関する規程(サンプル)
第1章 総則
(目的)第1条
本規程は、就業規則に定める懲戒事由に該当する行為を行った従業員に対する懲戒処分について、その手続き、調査、審議及び決定に関する事項を定めることにより、処分の公正性及び適正を確保することを目的とする。
(適用範囲)第2条
本規程は、当社の全ての従業員に適用する。
第2章 懲戒処分の手続
(報告)第3条
各部門の管理監督者は、所属する従業員に懲戒事由に該当する疑いがある行為を認知したときは、速やかに事実関係を調査し、その結果を添えて人事部長に報告しなければならない。
(調査および証拠収集)第4条
- 人事部は、前条の報告またはその他の情報に基づき、懲戒処分を行うか否かを判断するため、事実確認と証拠収集を行う。
- 調査にあたり、必要に応じて関係者(被処分対象者を含む)からの事情聴取、資料の提出を求めることができる。
- 違反行為が疑われる従業員およびその関係者は、会社が行う調査に誠実に協力しなければならない。
(弁護の機会)第5条
- 会社は、懲戒処分(特に諭旨解雇または懲戒解雇となるおそれがある場合、および出勤停止、降格、減給等の重い処分を検討する場合)を行おうとするときは、原則として、事前に被処分対象者に対し、弁明の機会を与える。
- 弁明は、口頭または書面により行うものとし、会社が指定する期日までに弁明書を提出させるか、または会社が指定する場所・日時で事情聴取を行うものとする。
- 正当な理由なく弁明を拒否し、または指定された期日に弁明書を提出しない場合は、弁明の機会を与えたものとみなして手続きを進めることができる。
(懲戒委員会の設置)第6条
- 会社は、懲戒処分の適正を期すため、懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 諭旨解雇、懲戒解雇、出勤停止、降格等の重い懲戒処分を検討する場合、原則として委員会の諮問を経るものとする。けん責、戒告、減給等の処分については、必要に応じて委員会に諮問することができる。
(懲戒委員会の構成)第7条
- 委員会は、委員長および委員をもって構成する。
- 委員長は社長(または社長が指名する役員)とし、委員は人事部長および社長が指名する5名以内の者をもって充てる。委員のうち1名は、従業員の代表者または人事・労務に関する専門知識を有する者を含めることができる。
- 委員会の事務局は、人事部内に置く。
(懲戒委員会の審議)第8条
- 委員会は、懲戒処分の必要性、処分の種類および量定の適否について審議する。
- 審議にあたっては、提出された調査結果、証拠資料、および被処分対象者の弁明内容を十分に考慮しなければならない。
- 委員会の議事は非公開とし、委員会の構成員には守秘義務を課す。
(懲戒処分の決定)第9条
- 懲戒処分は、委員会の審議を経て、最終的に社長が決定する。
- 決定にあたっては、行為の性質、態様、会社に与えた影響、過去の処分歴、本人の反省の度合い、他の従業員との均衡等を総合的に考慮し、客観的かつ公正に行うものとする。
(懲戒処分通知)第10条
- 懲戒処分が決定したときは、会社は速やかに被処分対象者に対し、懲戒処分通知書により通知する。
- 懲戒処分通知書には、以下の事項を明記しなければならない。
- 懲戒処分の種類
- 懲戒処分の具体的な内容(例:減給の額と期間、出勤停止の期間など)
- 処分の理由(懲戒事由となった具体的な事実)
- 就業規則上の根拠条文
- 始末書または誓約書の提出を求める場合はその旨及び提出期限
(自宅待機命令)第11条
- 会社は、懲戒事由に該当する疑いがある行為について調査中または処分決定までの間、業務の適正な遂行を確保するため、従業員に対し自宅待機を命じることができる。
- 自宅待機を命じる場合、賃金の取り扱いについては自宅待機の期間中は出勤したものとして取り扱う。
留意すべき点
懲戒処分は、必ず就業規則に懲戒の種類と、それに対応する具体的な懲戒事由が定められていることが大前提です。本規程は、その就業規則に基づき、具体的な「手続き」を定めるものです。
このサンプルは、中規模の会社を想定して作りましたが、あくまで一例であり、貴社の実態や法的な要件に適合するように、専門家(社会保険労務士や弁護士など)のアドバイスを受けて調整することが重要です。このひな形をベースに、貴社の状況に合わせて内容を詳細化・具体化してください。