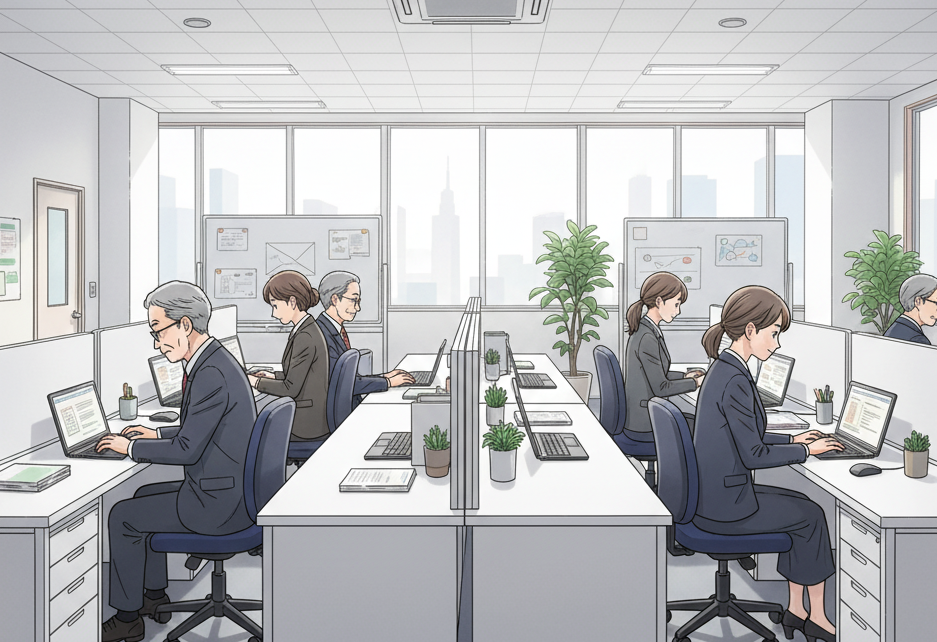不合理な待遇差に対する法規制
「同一労働同一賃金」とは、雇用形態(正社員、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など)に関わらず、同じ仕事をしている労働者には、同じ賃金を支払うべきという考え方です。
これは、単に「給料」だけでなく、賞与、手当、福利厚生といったあらゆる待遇の不合理な格差をなくすことを目的としています。
法的な位置づけ
日本において「同一労働同一賃金」の原則は、「働き方改革関連法」の一環として、以下の法律で定められています。
- パートタイム・有期雇用労働法
- 労働者派遣法
これらの法律では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、「不合理な待遇差」を設けることが禁止されています。
「同一」と見なされる要素
「同一労働」であると判断されるためには、以下の3つの要素が考慮されます。
- 職務の内容: 担当する業務の内容や、責任の程度が同じかどうか。
- 職務内容・配置の変更範囲: 転勤や異動の有無・範囲が同じか、将来の昇進の可能性が同じか。
- その他の事情: その他の特別な事情(例:個人のスキルや経験)があるか。
このうち、「1」と「2」が同じであれば、「均等待遇(差を付けてはならない)」が求められ、「3」を考慮してもなお不合理な場合は「均衡待遇(不合理な差をなくす)」が求められます。
対象となる待遇の具体例
同一労働同一賃金が適用される待遇は、基本給だけではありません。以下のような待遇のすべてに適用されます。
- 賃金: 基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、精勤手当、通勤手当、住宅手当など)
- 教育訓練: 職務に必要な研修機会の提供
- 福利厚生: 食堂や更衣室の利用、転勤者用社宅の利用、慶弔休暇など
ただし、「待遇差が不合理ではない」と判断される場合もあります。例えば、単身赴任手当や退職金は、職務内容や人材活用の仕組み(転勤の有無など)が異なるため、正社員と非正規社員で差があっても、それが「不合理ではない」と判断された最高裁判例も存在します。
待遇差が不合理ではない具体的例
同一労働同一賃金において、待遇格差が不合理ではないと判断される具体的な例をいくつか挙げます。これらの判断は、個々の企業の事情や、職務内容、責任の範囲などによって変わる可能性がありますが、これまでの最高裁判例やガイドラインから示唆される一般的な例です。
1. 職務内容や責任の範囲の違いに基づく待遇差
- 基本給: 正社員が総合職として転勤や多様な部署異動を経験し、幅広い業務や責任を負う可能性がある一方で、非正規雇用労働者が特定の業務のみを担当する場合、基本給に差があることは不合理ではないとされます。
- 役職手当・役職給: チームリーダーや管理職など、特定の役職に就いており、部下の指導やマネジメントといった責任を負っている正社員にのみ支給される手当は、不合理な格差とは見なされません。
2. 人材活用の仕組みの違いに基づく待遇差
- 退職金: 多くの最高裁判例において、正社員に退職金を支給し、非正規雇用労働者には支給しないことは不合理ではないと判断されています。その理由として、退職金は長期的な人材確保や、雇用関係の継続に期待して支給されるものであり、無期雇用である正社員の勤務実態とは異なることが挙げられます。
- 住宅手当・家族手当: 転勤がある正社員と、転勤がなく自宅から通勤する非正規雇用労働者との間で、住宅手当や家族手当に差があることは不合理ではないと判断されることがあります。これらの手当が、全国転勤やそれに伴う生活の変化を補償する目的で支給されている場合です。
3. その他、個々の状況に基づく待遇差
- 賞与(ボーナス): 会社の業績や個人の評価を考慮して賞与が支給される場合、その貢献度や評価に応じて支給額に差があることは不合理ではありません。ただし、同じ貢献度であれば同じ額が支払われるべきです。
- 病気休暇: 無期雇用である正社員に有給の病気休暇を付与し、有期雇用労働者には付与しないことが、直ちに不合理とは判断されない可能性があります。これは、雇用期間の定めの有無という人材活用の仕組みの違いに基づいていると見なされるためです。
これらの例は、単に雇用形態が違うからという理由で待遇差を設けることが許されるわけではなく、「なぜその待遇差が必要なのか」という合理的な理由が説明できる場合にのみ認められる、ということを示しています。
正社員間の賃金格差はどうか
現状では、正社員間の賃金格差は、同一労働同一賃金問題の直接的な対象にはならないと理解していただいて差し支えありません。
なぜ正社員間の格差は対象外なのか?
「同一労働同一賃金」の原則は、あくまで正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の「不合理な待遇差」を解消することを目的としています。
正社員同士であれば、多くの場合、以下の点が共通しているため、この法律の対象からは外れます。
- 雇用形態: いずれも無期雇用契約である正社員です。
- 人材活用の仕組み: 転勤や異動の可能性、職務変更の範囲、昇進の機会などが原則として同じです。
したがって、同じ「正社員」という雇用形態の中で、評価制度に基づいて賃金に差がつくことは、「職務内容や個人の貢献度、能力の違い」に基づく合理的な格差と見なされます。この評価は、同一労働同一賃金が認めている「均衡待遇」の考え方に沿ったものです。
ただし、同一労働同一賃金の原則が、より広い意味で「公正な評価」を求める流れを加速させていることも事実です。今後は、正社員間の賃金差であっても、その根拠が曖昧であったり、客観的な評価制度に基づかないものであったりする場合、説明責任がより強く求められるようになる可能性があります。
正社員間の学歴格差はどうか?
学歴によって初任給や昇給に差をつける制度は、「同一労働同一賃金」の流れに必ずしもそぐわないわけではありません。 重要なのは、その学歴の差が「不合理な待遇差」と見なされるかどうかです。
学歴による待遇差を合理的に説明する考え方
学歴による差を合理化する主な考え方は以下の通りです。
- 潜在能力や職務内容の違い企業が、大卒者には高卒者よりも高度な職務や責任を将来的に担うことを期待し、それを前提とした賃金制度を設けることは合理的な理由となります。これは、正社員の賃金が「職務内容や人材活用の仕組み」に基づいて決まるという考え方と一致します。この場合、学歴はあくまで将来の職務範囲や期待される役割を示す一つの指標に過ぎません。
- 教育コストの考慮大学での専門的な教育や研究経験が、入社後の業務に直接役立つと判断される場合、その先行投資分を初任給に反映させることは、不合理とは見なされない可能性があります。
どのような場合に問題となるか?
一方で、以下のような場合は「不合理な待遇差」と見なされるリスクがあります。
- 職務内容が完全に同じ: 大卒者と高卒者が、全く同じ業務を同じ責任範囲で、同じように遂行しているにもかかわらず、学歴のみで賃金に差がある場合。
- 昇給・昇格に学歴以外の要素がない: 評価制度が機能せず、単に学歴が高い社員が、より有利な昇給・昇格ルートをたどるような制度になっている場合。
アドバイス:制度の見直しと対応策
不合理な格差とみなされるリスクがある場合は、以下の点を検討することをおすすめします。
- 職務給の導入: 学歴ではなく、個々の社員が担う職務の価値や責任に応じて賃金を決定する「職務給」を導入します。これにより、学歴による初任給の差を徐々に解消し、実際の業務内容に応じた公正な評価へと移行できます。
- 評価制度の透明化: 昇給の基準を学歴ではなく、個人の成果、スキル、貢献度に明確に紐づけます。これにより、誰もが納得できる公正な評価制度を構築できます。
- 非正規社員との待遇差解消: 特に、学歴が同じであるにもかかわらず、正社員と非正規社員の間に不合理な待遇差がないか確認することが重要です。
学歴による差を設けることが直ちに違法となるわけではありませんが、「同一労働同一賃金」の流れは、より個々の社員の能力や貢献度に基づいた公正な評価を企業に求めています。この機会に、賃金制度をより透明で合理的なものへと見直すことが、将来的なリスクを回避する上で非常に有益です。
企業における取組手順
労働厚生省ホームページの「同一労働同一賃金特集ページ」を参考にして取り組み手順を策定しましょう。
概要は以下の通りです。
手順1 労働者の雇用形態を確認しましょう
社内の労働者のうち、対応が求められる労働者の範囲を確認しましょう。フルタイム労働者よりも勤務時間の短い短時間労働者と、労働契約の期間に満了日が設定されている有期雇用労働者が対象です。社内の呼称で分類してはいけません。
手順2 待遇の状況を確認しましょう
短時間労働者・有期雇用労働者の賞与、手当、福利厚生などの待遇について、正社員(フルタイムの無期雇用労働者)との違いを確認して、項目ごとに一覧表の形でまとめてみましょう。
手順3 待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認しましょう
待遇の違いを設けている理由を書き出してみましょう。「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」などの主観的・抽象的な理由ではなく、客観的・具体的な理由であることが求められています。
手順4 待遇に違いがあった場合、その違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理しておきましょう。
整理した内容を元に、労働者から説明を求められた場合に使用する、「待遇の違いの内容と理由」の説明書を準備しましょう。
手順5 法違反が疑われる状況からの早期の脱却を目指しましょう
以上の手順の中で、待遇の違いが「不合理ではない」と言い難い項目がある場合には、改善に向けた検討が必要です。
手順6 改善計画を立てて取り組みましょう
改善内容が明確になったなら速やかに計画を策定して改善を進めましょう。
まとめ
「同一労働同一賃金」は、単に「同じ給料」にすることではなく、「正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差をなくし、働き方に応じた公正な評価を行うこと」を目的としています。これにより、労働者のモチベーション向上や、企業の生産性向上にもつながることが期待されています。