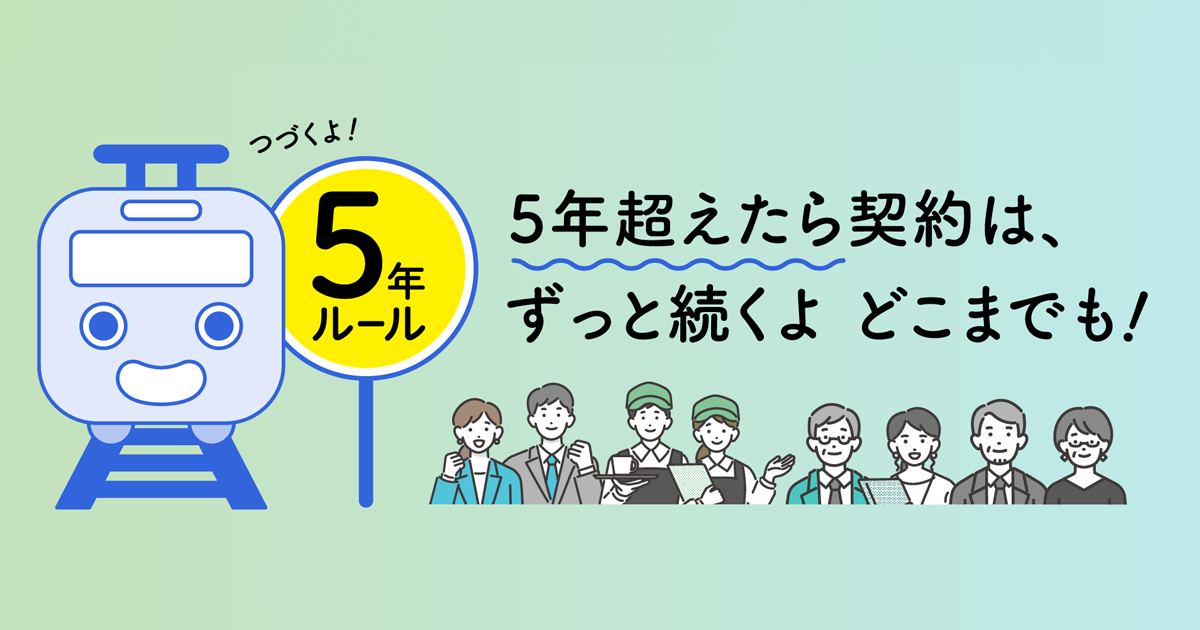無期契約への転換とは
有期労働契約が5年を超えて反復更新されたときには、労働者が申込みすることによって無期労働契約に転換できます。使用者に拒否権はありません。
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
労働契約法第18条(抜粋) 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
無期転換申込み権が発生する条件
1.有期労働契約の通算期間が5年を超えている
2.契約の更新回数が1回以上
3.同一の使用者に雇用されている。
通算5年を超えているとは
例えば、平成25年4月に1年契約で採用され、継続して更新されてきた有期労働契約の場合は、平生30年3月末でちょうど5年になるので、平成30年4月に契約を更新すれば無期転換申込み権が発生します。
3年契約であれば、1回目の更新をした段階でトータル6年の契約をしたことになるので、1回目の更新をして4年目に入ったときに無期転換申込み権が発生します。
該当する労働者が申込をしなかった場合でも、有期雇用契約が更新されれば、改めて無期転換申込みができます。
契約と契約の間に次のような空白期間があるときは、前の契約期間を通算しないことになっています。クーリング期間といいます。
空白期間が6ヶ月以上(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)あれば、期間が連続しないことになります。
つまり、契約期間と契約期間に次のように間が空くと契約期間が通算されなくなります。
有期契約期間が2ヶ月以下であれば1ヶ月以上の空白
有期契約期間が2ヶ月超〜4ヶ月以下であれば2ヶ月以上の空白
有期契約期間が4ヶ月超〜6ヶ月以下であれば3ヶ月以上の空白
有期契約期間が6ヶ月超〜8ヶ月以下であれば4ヶ月以上の空白
有期契約期間が8ヶ月超〜10ヶ月以下であれば5ヶ月以上の空白
有期契約期間が10ヶ月超であれば6ヶ月以上の空白
この規定の適用をねらって、一旦雇い止めして必要な空白期間を置いてまた有期雇用に戻すやり方も考えられますが、脱法的な行為とみられるおそれがあるので避けるべきです。
契約更新が1回以上必要
採用時の契約だけで、更新がまだ一度もされていなければ5年経っても無期転換申込み権が発生しません。通常は3年の期間制限があるので、該当するケースは少ないでしょう。
同一の使用者に雇用されていること
同一の使用者、つまり同じ会社で勤務してきたことも条件になります。同一法人内の別な事業場での勤務は通算されます。無期転換申込み権の発生を逃れるために形式的に他の使用者に切り替えても実態で判断されます。
親会社に3年、子会社に2年という場合には、別法人ですから形式的には同一の使用者ではありませんが、資本関係等から実質的に同一の会社とみなされる場合には、無期転換申込み権については同一の使用者とみなされるのではないでしょうか。この辺りの問題は明確ではありません。
通算5年直前に雇い止めがあった場合
無期転換申込権が発生する直前(1日前)に期間満了による雇止めをされたために無期転換申込みができなかったことを争う裁判が進行中です。
横浜地裁は雇用契約書に「当社における最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」という、いわゆる不更新条項を労働者が合意して雇用契約を「自由意思」で締結していたとして、雇止め有効の判決を出しました。(2021年3月30日)これに対して労働者は控訴したためまだ結論はでていません。
1日の違いで雇用が終了してしまうのは気の毒ですが、地裁においては法的にはこうした雇止めは違法ではないという判断のようです。労働者側は、不更新条項の承認が自由意志とは言えない、また、労働契約法第19条「更新されるものと期待することについて合理的な理由がある」などの点で争っています。
労働契約法第19条 (略)使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一(略)
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
手続き
申し込みが必要
条件を満たしても、自動的に無期雇用に転換されるのではありません。有期雇用のままでよければそのまま有期雇用を続けることができます。無期雇用に転換を希望する場合は、その旨を使用者に申し込む必要があります。
申込みは、進行中の契約期間内のいつでもできます。申込みをしないうちに契約期間が切れたときは、次回の契約が結ばれればその期間に無期転換を申し込むことができます。
契約期間以外の労働条件は継続する
無期転換された場合、契約の期間に定めが無い状態になりますが、このことがそのまま正社員雇用を意味するものではありません。
別段の定めがない限り、労働条件は、雇用期間の部分を除いては、従前と同一の労働条件が継続されることになります。無期雇用にするかわりに給料を下げるなどの変更をすることはできません。
労働契約法第18条(抜粋) この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
特例が適用される労働者
「専門的知識等を有する有期雇用労働者」、「定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者」、「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等」については、特例が適用されます。
通常の労働者への転換促進
上述の5年ルールは有期雇用から無期雇用へ強制的な転換ですが、これとは別に、パートタイム・有期雇用労働法において、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務付けられています。
パートタイム・有期雇用労働法
(通常の労働者への転換)
第十三条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。
二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。
三 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
要約すれば、正社員への転換を推進するために、正社員が必要になったときはパート従業員にも応募機会を与え、また、パート従業員から正社員になりやすいように、試験制度を設けることが求められています。
労働条件の明示についての改正
労働条件の明示に関する労働基準法施行規則等が改正されます。施行期日は2024年(令和6年)4月1日の予定です。なお、本改正については次の記事にも記載しておきました。合わせてご参照ください。
無期労働契約への転換に関係する部分は以下の通りです。
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約2の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
併せて、雇止め告示(有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準))の改正により下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込 3 むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
併せて、雇止め告示(有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準))の改正により「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
就業規則
また、厚生労働省は、無期転換された従業員に適用する就業規則例を示しています。
無期転換を機会に、新たな役割を期待し、正社員とも従来の契約社員ともパート社員とも違う新たな従業員群を作る試みがある場合は参考になると思います。
しかし、雇用契約の期間を有期から無期に変換するだけでその他の労働条件が全く変わらないのであれば、別規程を定めるまでもなく、既存の契約社員就業規則やパート社員就業規則において、無期転換に関する条を追加するだけで済むと思われます。