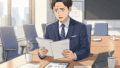受付の事前準備
受付で人の流れが滞ったりするとイライラする人が現れて険悪な雰囲気になることがあります。
受付で「バカにするな!」などと大声を発する者も稀に現れますが、ひるまずに、法律上、判例上に裏付けがある対応をすれば問題ありません。
しっかりした対応をするためには、場数も大事ですが、正確な知識が一番重要です。
法律的にはどのように対応するのが正解か、事前にシミュレーションし、しっかりしたマニュアルを作り、リハーサルをやっておけばスムーズに対応できます。
準備する物
□受付票:事前に送付した議決権行使書、または当日配布用の受付票。
□株主土産
□株主名簿:基準日時点の株主名簿の最新版。議決権数、株主番号、氏名、住所が確認できるもの。
□予備の招集通知(議案)
□案内表示:会場案内、受付場所への誘導表示、委任状や本人確認が必要な場合を案内する提示。
□筆記用具等:ボールペン、マジック、メモ用紙、書類トレー、ホチキスなど。
□その他:筆談器、拡大鏡、車椅子の方への配慮用具、感染症対策をするのであれば必要な用具、救急用品など。
受付の人数
前回までの出席株主数から今回の出席株主数を推定して、対応人数を決めます。何か注目される要素があれば激増することがあるので注意を要します。
人数が多い場合、仕事がない人は挨拶していればよいので困ることはありませんが、少ないと流れが滞って困ることになります。余裕をもって配置する必要があります。
受付の流れ
あいさつの言葉
「おはようございます」
「いらっしゃいませ」
「ありがとうございます」
など、ある程度は事前に決めておきましょう。無言で応対する人がいないようにしましょう。
議決権行使書用紙を受け取る
初めから差し出す人が多いので「ありがとうございます」と応えます。
何も言わずに受付に立った人には「議決権行使書はお持ちでしょうか」と問いかけます。
議決権行使書をチェックする
自社の株主総会のものかチェックします。(複数の会社の株主であることが多いので間違えて他社のものを持ってくる人も稀にいます)
本年度の議決権行使書かチェックします。(これも稀にいます)
イレギュラー対応
議決権行使が終わっている場合
インターネットにより既に議決権行使を行ったとの申出があれば、「提出済」と議決権行使書用紙に朱記します。
入場してもらうことに問題はありません。
議決権行使書を提示しない場合
議決権行使書を紛失、忘れた場合は、株主名簿にて、株主情報と照合し、本人であることを確認します。併せて、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の提示を求め、本人確認を厳格に行います。
確認が取れ次第、手書きで受付票を作成し交付します。
株主名簿にない場合は入場させることができませんが、一応、株取得の経緯を尋ねて確認します。
複数の議決権行使書が提示された場合
複数の証券会社に口座を持つ場合など、複数の議決権行使書を提示する人がいた場合、全ての議決権行使書を受け取り、それぞれの株主情報を確認・照合し、議決権数を合算し、合計議決権数を記載した受付票を交付します。
同伴者がいる場合
一枚の議決権行使書で同伴者がいた場合、原則として入場をお断りしますが、介助者等、やむを得ない事情がある場合どう対応するか事前に取り決めておきましょう。
名義人以外が来場した場合
来場者が会社が事前に送付した議決権行使書用紙を持参していれば、特段の事情がない限り、議決権行使書用紙の持参者を真正な株主とみなして、それ以上の確認をすることなく入場を認める扱いが多く行われています。ただし、そうした簡便なやり方により問題が生じることがあります。
代理人による出席の場合は、代理人であることを証明する有効な委任状(株主本人の署名・捺印があるもの)を提出してもらいます。また、来場者の本人確認が必要です。マイナンバーカード、運転免許証等の公的証明書の提示を求めます。
代理人が当社の株主でない場合はどう対応するか事前に取り決めておきましょう。
法人株主の場合は通常その法人の役職員が来場します。厳密に言えば委任状が必要ですが、委任状等がなくても名刺や社員証で確認して入場を許可する運用がなされているケースも見られます。
受付で資料の要求があった場合
「招集通知」は多めに用意しておくべきですが、それ以上の、例えば有価証券報告書等を求められることも稀にあります。
インターネットで開示することにより、提供したとみなされているので、法律上はその場で交付する義務はありません。その旨を丁寧に伝えましょう。
議決権行使書の集計
受付業務の中心は議決権行使書の集計です。
議決権行使書の集計をする係は、雑事に惑わされず集計に専念できるよう配慮しなければなりません。
チェック(数え直し)する人も必要です。
集まった議決権行使書は、どんどん集計係に渡します。集計係が別室にいるときなど、ある程度まとまってから渡す場合もあります。
集計係は、受付した議決権を前日までの集計分に加えて、当日の議決権を確定させます。
総会開始後直ちに議決権の数字が読み上げられるので、実務的には総会時刻の数分前で締め切る必要があります。
その結果、時間ギリギリに駆け込んできた株主の分は入らないことになりますが、後日作成する株主総会議事録には、本当の確定数を記載します。総会場で読み上げた数字と違うことになりますが、議決に影響を及ぼすほどのの違いでなければ問題になることはありません。
外部スタッフの協力
上場会社であれば、信託銀行等の株主名簿管理人から職員が派遣されてくることが多いようです。詳しい人がくるので、判断に迷うときは聞きながらやればよいでしょう。派遣されてこないときは、担当窓口に株主総会の時間を事前に連絡しておき、いつでも連絡できるようにしておきましょう。
トラブルが起きそうな予兆がある場合、あるいは、前の総会でトラブルがあった場合は、所轄の警察署に事前に相談すると、警察官を派遣してくれることがあります。
特に問題がない会社であれば自社で対応できますが、出席株主数によっては、念のため、警備会社と契約する会社も多いようです。