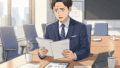定年後再雇用契約の雇止めに関する解説
定年後再雇用された高年齢労働者に対する雇止めは、高年齢者雇用安定法(高年法)による雇用確保義務と、労働契約法の雇止め法理が適用されるため、通常の有期契約労働者よりも厳しく判断されるのが特徴です。
高年齢者雇用安定法による規制
高年法第9条により、事業主には希望する従業員を65歳まで継続雇用する義務があります。
- 継続雇用の原則: 定年後再雇用制度は、この雇用確保義務を果たすための措置の一つです。この義務の存在から、65歳に達するまでの間は、合理的な理由がない限り、企業は再雇用契約の更新を拒否することはできません。
- 65歳までの保護: したがって、再雇用契約の更新拒否が認められるためには、正社員の解雇に相当するほど厳格な理由が必要とされます。
労働契約法による規制(雇止め法理)
有期労働契約の更新拒否については、労働契約法第19条(雇止め法理)が適用されます。
- 雇止め法理の適用要件:
- 過去に反復更新されており、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態であると認められる場合。
- 労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合。
- 高年齢労働者への適用: 定年後再雇用の場合、65歳までの雇用確保義務があるため、上記2.の「更新の合理的な期待」が特に認められやすい傾向にあります。
- 雇止めの有効性: 雇止め法理が適用される場合、更新拒否が「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当であると認められない」ときは、雇止めは無効となり、契約が更新されたことになります。
雇止めが認められる「客観的に合理的な理由」
継続雇用の雇止めが例外的に認められる可能性があるのは、以下のいずれかの事由に該当し、かつ社会通念上相当と判断される場合に限られます。
経営上の理由
事業の縮小や廃止、部門の閉鎖など、人員削減の必要性があり、配置転換などの回避努力を尽くしたにもかかわらず、やむを得ないと認められること。
労働者の能力不足・勤務態度不良
契約上の職務が遂行困難なほど能力が著しく不足している、または重大な規律違反があるなど、解雇事由に相当するほどの状況であること。
労働者の心身の故障
病気や怪我により労務提供が不可能であり、回復の見込みが極めて薄いと医師の診断などで客観的に認められること。他の業務への配置転換も不可能であること。
「病気や怪我により労務提供が不可能」を理由とする場合、会社は以下の点を厳しく検討する必要があります。
- 業務遂行能力の有無: 担当業務だけでなく、配置転換によって他の軽易な業務に就く可能性はないか。
- 回復の可能性: 医師の診断に基づき、次の契約期間中に復職が期待できないことが客観的に証明できるか。
- 休職制度の有無: 再雇用契約に休職制度がない場合でも、制度がないことをもって直ちに雇止めできるわけではないため、慎重な対応が必要です。
契約更新拒否(雇止め)のリスク
不当な雇止めと判断された場合: 裁判等で雇止めが無効と判断されると、会社は従業員に対し、契約が継続していた期間の賃金(未払い賃金)を遡って支払わなければなりません。
紛争のリスク: 高齢者からの雇止めは紛争に発展しやすく、会社の社会的信用にも影響を及ぼします。
【まとめ】
定年後再雇用制度により雇用中の従業員についての雇止めを検討する場合、使用者側には、経営上の理由、労働者の能力不足・勤務態度不良、労働者の心身の故障という理由があるとしても、「解雇回避努力」を含む客観的かつ合理的な説明責任と証明責任が求められます。 実務においては、紛争を避けるため、弁護士や社会保険労務士と相談の上、合意による解決を模索することが安全な方法です。