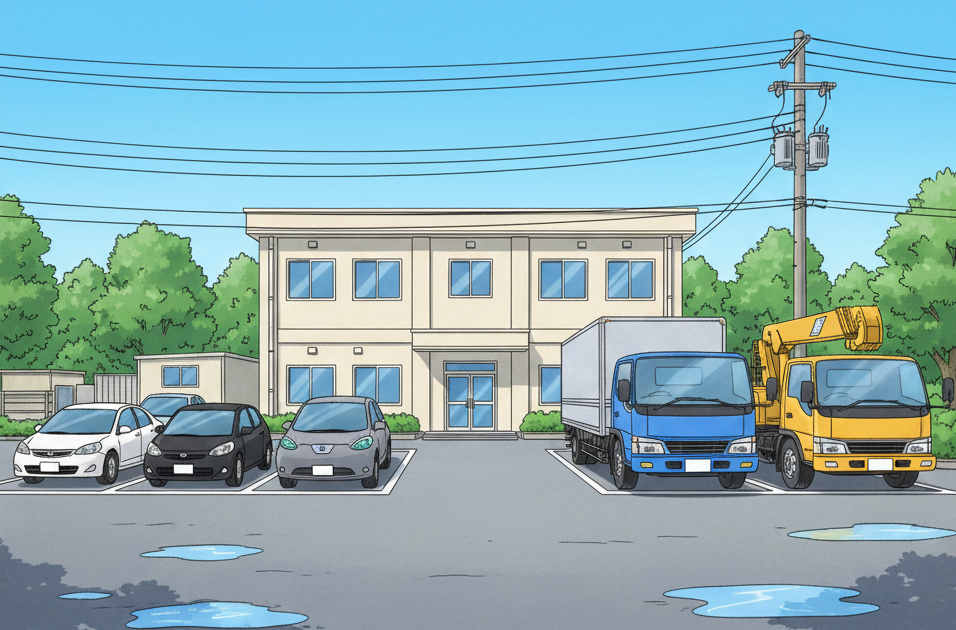シフト制とは
シフト制とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどによって、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
「シフト制」という言葉は、労働基準法で定められた法的な制度名ではありませんが、長時間営業の店舗や年中無休の事業所など、従業員が交代で勤務する必要がある職場で広く採用されている、勤務の運用方法を指します。
シフト制の仕組みと特徴
1. 勤務日・勤務時間の決定方法
一般的な「固定勤務制」(例:月曜から金曜の9時~18時)とは異なり、シフト制では労働日や労働時間が流動的です。
- 勤務時間の流動性: 早番・遅番・夜勤など、複数の勤務パターンや、短い時間(例:3時間、4時間)の勤務が組み合わされます。
- 決定プロセス: 従業員が希望する勤務日時を申告し、企業側が業務の必要人員や他の従業員の希望と調整した上で、最終的なシフト表(勤務割表)を作成し、労働者に通知することで、具体的な労働日・時間が確定します。
2. シフト制の種類
主に、シフトの自由度によっていくつかの種類に分けられます。
| 種類 | 特徴 | 主な採用例 |
| 自由シフト制 | 従業員の希望を最大限考慮し、働く日時を申請に基づいて調整する。 | 飲食店、小売店、アルバイトが多い職場 |
| 固定シフト制 | 働く曜日や時間帯が、原則として一度決めたら変わらない。 | コールセンター、オフィス清掃、安定した勤務が必要な職場 |
| 完全シフト制 | あらかじめ複数の勤務パターン(日勤、夜勤など)が設定され、それらを組み合わせて交代勤務を行う。 | 24時間稼働の工場、病院、介護施設など |
3. 法定制度との関係(最も重要な点)
シフト制は運用方法であり、労働基準法上の制度ではありませんが、以下の法的な枠組みの中で運用されます。
| 項目 | 関係 |
| 法定労働時間 | シフトを組む際も、原則として1日8時間、週40時間の法定労働時間を遵守しなければなりません。これを超えて労働させる場合は、残業として割増賃金を支払う必要があります。 |
| 変形労働時間制 | 企業が特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて労働させたい場合、「1ヶ月単位の変形労働時間制」などの変形労働時間制という法的な制度を導入し、その中でシフトを運用することが一般的です。これにより、残業代を抑えつつ、業務の繁閑に合わせて労働時間を弾力的に配分できます。 |
4. 運用上の留意点
シフト制では、労働日・時間が直前に決まることで労働者の生活に影響を与えるため、トラブルを避けるために以下のルールを就業規則などで明確にする必要があります。
- シフトの通知期限: 確定したシフトを、いつまでに労働者に通知するかを定めること(例:前月25日まで)。
- 労働条件の明示: 労働契約の締結時やシフト確定時に、具体的な労働時間だけでなく、「〇時から〇時の間でシフトにより決定する」「週〇日程度勤務」といった労働の目安や決定方法を明示すること。
シフト制における就業規則の記載方法
シフト制の場合、就業規則に具体的な労働日・時間そのものを画一的に書くのは難しいため、決定方法や原則となる事項を記載することが適切です。
就業規則には、労働基準法で定める「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇」などの事項を必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」があります。シフト制の場合は、以下の点を明確に定めることで対応できます。
1. 始業・終業の時刻および休憩時間
具体的な時刻を一つに定められないため、考えられる時間帯の範囲や、シフト作成のルールを記載します。
記載の原則:
「始業および終業の時刻、休憩時間は、会社が定めるシフト表による」と明記します。
ただし、「シフトによる」だけでは不十分とされる場合があるため、最も早い始業時刻と最も遅い終業時刻の範囲、および1日の労働時間(例:6時間から8時間)や休憩時間の付与条件(例:労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上)を記載することが望ましいです。
記載例:
(始業および終業の時刻、休憩時間)
第〇条 始業および終業の時刻、休憩時間は、会社が定めるシフト表による。
2 シフトは、原則として〇時〇分から〇時〇分までの間で指定するものとし、1日の所定労働時間は〇時間から〇時間とする(休憩時間を除く)。
3 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間与えるものとする。
2. 休日
休日についても、具体的な曜日ではなく、休日の付与のルールとシフト表による決定を明記します。
記載の原則:
「休日は、会社が定めるシフト表による」と明記します。
労働基準法の定めに基づき、「原則として4週を通じて4日以上」または「1週に1日以上」といった最低限の休日付与ルールを併記します。
記載例:
(休日) 第〇条 休日については、会社が定めるシフト表による。
2 会社は、労働者に対し、原則として4週を通じて4日以上の休日を与えるものとする。
3. シフトの作成・通知に関する事項
シフト制を円滑に運用するために、シフトの作成・通知方法に関するルールを記載します。
記載例:
(シフトの作成・通知) 第〇条 会社は、毎月〇日までに翌月分のシフト表を作成し、〇日までに労働者に通知するものとする。
2 労働者は、シフト作成に際し、会社が指定する期日までに勤務希望を申し出ることができる。ただし、最終的な決定権は会社にあるものとする。
就業規則には、これらの原則や決定方法を記載したうえで、個々の労働者へ交付する労働条件通知書や雇用契約書において、シフトにより労働日・時間が決まることを具体的に明示し、誤解が生じないようにすることが大切です。
記載内容をより正確にするためには、社会保険労務士などの専門家へ相談することをおすすめします。