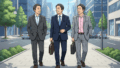労働時間の状況の把握
長時間労働者に対する面接指導を実施する前提として、管理監督者を含むすべての労働者を対象として。労働時間の状況の把握をしなければなりません。
安全衛生法第66条の8の3 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
面接指導を実施するため
労働時間の把握は、長時間労働者に対する面接指導を実施するために行うものです。
厚生労働省令で定める方法
これは、労働安全衛生規則第五十二条の七の三に、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。と定められています。 具体的な点は後述します。
次条第一項に規定する者を除く
これは、高度プロフェッショナル制度対象者のことです。高度プロフェッショナル制度対象者は、別な方法により管理することになります。管理監督者や裁量労働制の適用者は除かれません。
労働時間の把握方法
労働時間の状況は次の方法によって把握する必要があります。
ア タイムカードによる記録
イ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法
ロ その他の適切な方法
タイムカードによる記録
多く採用されている方法は、タイムカードの打刻時刻を始業及び終業の時刻として記録する方法です。
これらの方法は、必ずしも労働時間と一致していないという難点があります。
朝、タイムカードを打刻してもすぐに仕事を始めるとは限りません。帰りのときも、仕事が終わってすぐにタイムカードを打刻しているとは限りません。
なお、タイムカードを労働基準法に定めがある「出勤簿」としている事業場もありますが、タイムカードは出勤簿の代わりにはなりません。
パソコン等の使用時間で把握する
業務用パソコンへのログイン、ログアウトにより就労時間を把握する方法です。
ICタイムカードを使って就労時間を把握する方法もあります。ICタイムカードを利用した場合は、勤怠管理システムと連動させることで、出社・退社時間をPC操作履歴や入退室時間と照らし合わせた確認作業ができるため、労働時間の把握や管理がしやすくなります。
この方法による場合は、パソコンやスマホで有給休暇、時間外労働の申請・承認もできるため、管理上の利点も増します。
パソコン等の記録で勤怠を管理するときは、社内のパソコンでデータ管理するよりも、クラウド型勤怠管理システムが有効です。初期費用も抑えられます。
その他の適切な方法
具体例として、通達では「事業者の現認」を挙げられています。
「現認」とは、従業員が出社した時間と退社した時間とを、上司などが実際にその目で見て確認した時間を記録することです。
しかし、上司が部下の行動をすべて把握することは現実には困難なことから、この方法によるには相当無理があるでしょう。
自己申告制については、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合には可能とされています。
ただし、現実的には、客観的な方法を利用できないケースは考え難いでしょう。通達でも、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められない」としています。
みなし算定
「みなし」というのは実際にかかった時間にかかわらず、そうなのではないかと仮定して労働時間を決めることです。労働時間のみなし算定は厳密には問題がないとは言えませんが、例えば制服への着替え時間について、実際にそれぞれ要した時間ではなく一律で着替え時間は何分とするという方法が実際に行われています。例としては1回3分または5分があります。一日の労働時間に自動的に6分または10分を加算するわけです。この時間は、かかっている時間の平均ではなく、実際にこのくらいあればよいだろうという納得感のある時間を設定しなければなりません。
着替え時間にみなし時間を設定することがあるのは、何分かけて着替えするかは人によって異なるし、意図的に時間をかけることも可能だからです。そうした現実を無視してそれぞれの実際に要した時間を労働時間として加算すれば不公平感が生じることもあるからです。
労働時間を管理する者の職務
会社は「客観的な記録があればそれで終わり」ではなく、その記録が実態と乖離していないかを確認し、必要に応じて是正する努力を求められています。
記録の保管義務
把握した労働時間の状況は、その記録を5年間保存しなければなりません。